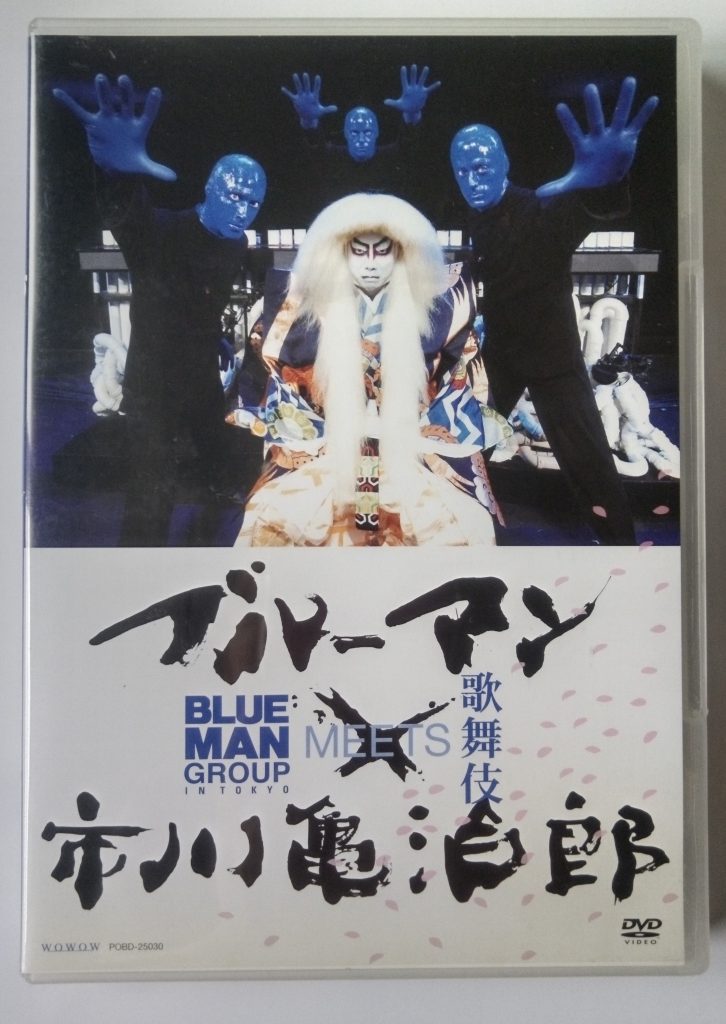NHKの大河ドラマの「平清盛」が色々取りざたされていたが、2回で見るのを止めてしまった。基本的にテレビの続き物のドラマを見続けるのが苦手で映画派である。
村上元三「平清盛」を読んだところ面白い。帝、上皇、法皇と院政が形作られて行くのが解かるし、武士の台頭していく様も面白い。殿上人の世界の魑魅魍魎さ。そして今とは違う寺社の力。寺院の強訴というのが、神輿を担ぎだして京に入り込み混乱を起こすという手法は仏に仕えるというよりも、子供が衆人の真ん中で寝転がってバタバタ手足を動かし大人達を困らせているようで苦笑ものである。清盛はその辺も利用し武士が居なくては貴族は成り立たないと認めさせていくのだが。
今は信仰よりも美術品的にあるいは観光的に鑑賞してきたお寺などの名前が出て来て、その、木造建築、歩いた道、周辺の風景が平安後期に移動して小説の中に現れ、ただ見てきただけの浅はかな旅も少しは役に立つようだと思ったりしつつまた小説の中に入って行ったりした。
<延暦寺の僧兵は日吉社の社人(しゃじん)とともに、日吉社の神輿(みこし)を担ぎ、総勢五百人ほどで洛中になだれ込んで来た。>
観光バスで延暦寺から琵琶湖側に降りて来た時、日吉大社を通り坂本の町を眺めここにはまたいつか来ようと思った。そして三井寺、坂本と尋ねる事ができた。そのことが荒法師の猛り声と共に浮かび上がり、現世に変遷してきた寺院もまた人間の欲得にまみれていたと思うと親しみも湧くものである。延暦寺と三井寺(園城寺)も派閥問題等で対立していたようで、かの弁慶も延暦寺の荒法師で三井寺の鐘を戦利品として叡山まで引き摺り上げたという伝説も残っている。
旅の小話・・・・・ 三井寺には近江の昔話「三井の晩鐘」のはなしもある。この話を題材にした日本画を残され夭折した三橋節子さんのことも偲ばれる。(「湖の伝説 三橋節子の愛と死」梅原猛著)
三井寺を訪ねた時は、33年に一度開扉される秘仏 如意輪観音坐像にも御会いでき思い出深き旅となった。そして坂本では穴太衆(あのうしゅう)積みの石垣をいたるところで眺めることができた。
弁慶の主人義経は鞍馬であるが、常盤御前を母とする牛若の兄・今若・乙若は醍醐寺にて出家する。醍醐寺というと秀吉の<醍醐寺の花見>が浮かぶが、まだ武士が権力を握れ無い頃、醍醐寺で命を救われた若子が出家したという時間空間もあったのである。
そんなこんなを考えつつ小説を読み終わり遅ればせながら大河ドラマを見始めた。面白い捉え方をしている部分と誇張され過ぎてる部分と半々である。清盛の新しい国造りの発想は面白い。ただ濃すぎる演技には閉口する。ドラマは役者の演技も楽しむものだが、そこまでやらなくても貴方の役どころは解かりますよと言いたくなる部分も或る。
自分が大河ドラマを見続けるには、それにそくした小説を読んで自分の中で筋を組み立ててからでなければ楽しめないようである。