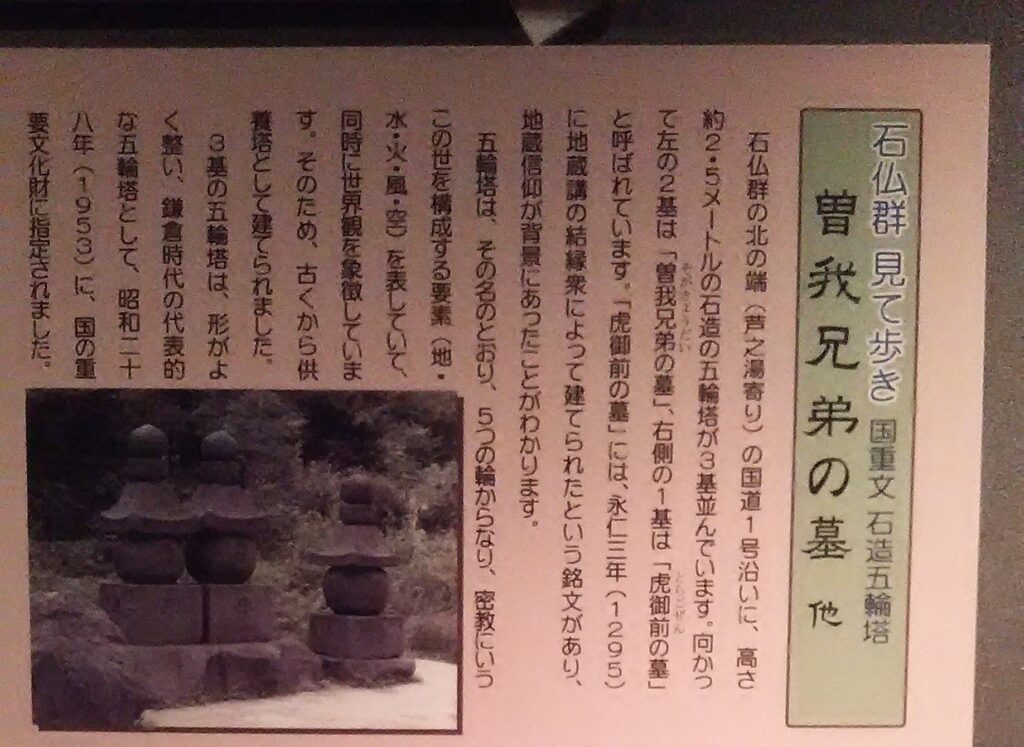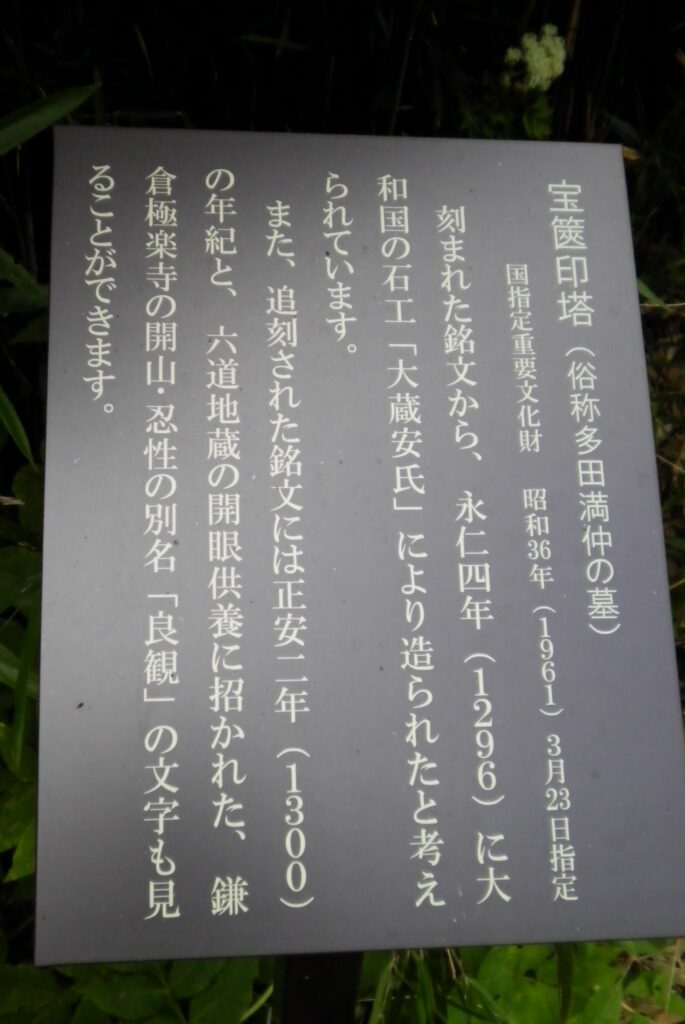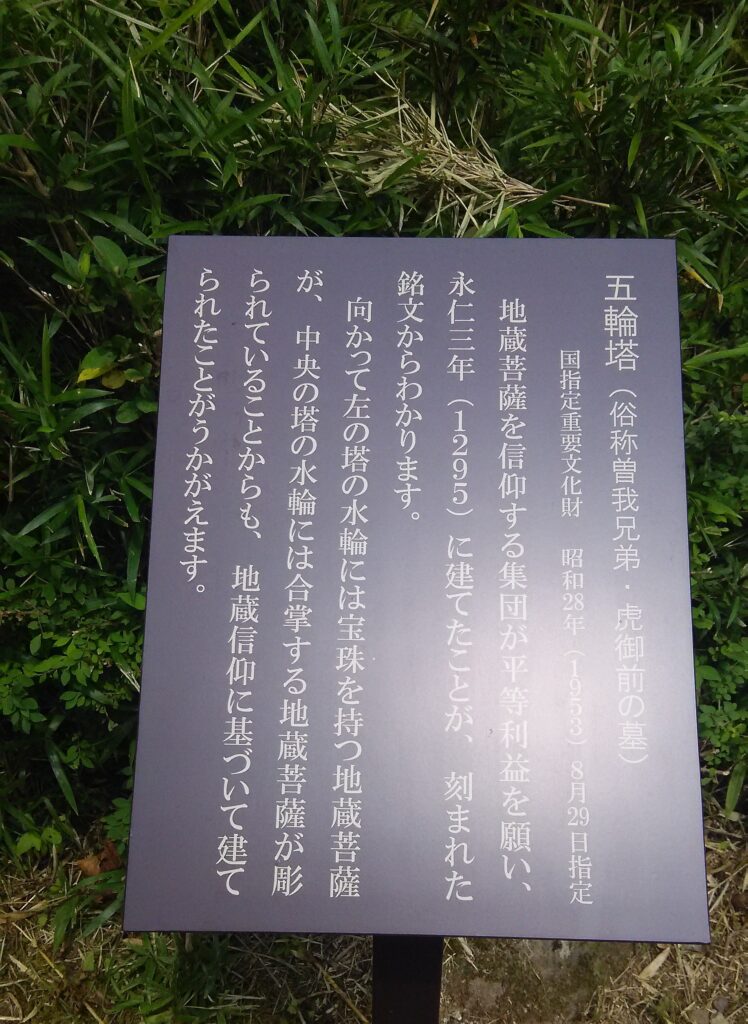『滝沢家の内乱』は再演である。2011年に加藤健一さんが劇団で100本目のプロデュース作品として選んだ作品である。『南総里見八犬伝』を書いた滝沢馬琴家の内幕である。
劇作家の吉永仁郎さんが、馬琴さんの残っている日記を探り、文字の演劇の馬琴像を作り上げた。あの『南総里見八犬伝』を書いた戯作者がどんな生活をしていたのか興味があるが、自分で日記を読んで馬琴像を作り上げる努力をする気がないので、吉永仁郎さんとカトケンワールドに任せることとする。
これが、面白かった。よく<面白かった>という言葉を使うと自分で自覚しているが、先ずは何かを食して「美味しかった。ご馳走様でした。」の感覚である。それから、味わいがあれば、何か言葉が生まれて来るであろう。
登場人物は、馬琴と、息子の嫁のお路である。初演も再演も、馬琴は加藤健一さんで、お路は加藤忍さんである。滝沢家の家族構成は、馬琴、妻のお百、息子の宗伯、嫁のお路、その後孫が二人と増える。お百は、高畑淳子さんが、宗伯は風間杜夫さんが声だけでの出演である。基本的に二人芝居であるが、声の出演の応援もあって、『滝沢家の内乱』がよくわかる。お百は神経の病気で宗伯も身体が弱く明るさの微塵もない家庭である。さらに暮らしは慎ましく、観ていると逃げ出したくなる状態である。
お路は二人の子を産み、筆記など出来ないほど目の不自由な馬琴に代わって口述筆記の代筆をして、『南総里見八犬伝』を完結させるのである。それが、7か月半の間で、漢字の書けないお路は漢字を馬琴から習いつつ書き上げるのである。初演のパンフレットに、代筆を始めたころの文字と八犬伝脱稿の文字の写真が載っていたが、信じられないほど美しい文字となっている。
再演のほうが、笑いが多くなった。なぜか。馬琴とお路の生き方のすれ違いである。それが顕著になり可笑しさを誘うのである。お路は、家族皆で話しを楽しむ家庭で育ち、『南総里見八犬伝』の作家の家に嫁にこれて、楽しい話しが沢山あるであろうと思ったのに、想像外のしつけに厳しく、倹約、節約の家である。お路の驚きと落胆、馬琴のお路に対する驚きと教育が、他人ごとなので可笑しい。お路の加藤忍さんが、どうすりゃいいのよこの私、バージョンである。
それに輪をかけて、声の出演だと思って勝手なこと言わないでよの高畑さんと風間さん。馬琴の加藤健一さんは屋根の上でしばし、現実を忘れるしかないのである。
お路さん次第に馬琴さんが、一人で滝沢家を守っていることが分って来る。世間で本が人気でも、その頃の戯作者の手にするお金は、今の流行作家の足元にも及ばない。さらに、滝沢家の内乱は、馬琴さんが戯作を書きたいう願望と息子を自分の思う方向に育てたいとの願望から生じた亀裂なのであるが、それは口にせず、お路さんは自分の役目を自覚する。そして、一度だけ、渡辺崋山が幕府からお咎めを受けた時、自分の気持ちを主張する。魅力的な女性である。馬琴さんが、ちょっと夢をみるのもわかる。
最期のお路さんの活躍は『南総里見八犬伝』の代筆である。お路さんが、滝沢家で我慢出来たのは、お路さんが『南総里見八犬伝』の読者であり、現実から逃避できたのは、『南総里見八犬伝』があったからで、漢字を知らないお路さんが代筆ができたのは、登場人物らがお路さんの中に生きていて、その名前などが漢字となる事に、お路さんは喜びを感じていたのであろう。ふりがなで読んでいたものが、自分で漢字を書くことが出来、登場人物との関係に新たな光がさし、読者として一番に八犬伝の先がわかるのである。これこそ、『南総里見八犬伝』の戯作者の家に嫁に来た時の自分の気持ちになれるのである。
演出の髙瀨久男さんがお亡くなりになられ、加藤健一さんが今回演出をされたようであるが、髙瀨さんの演出されたものに、二人の役者さんのさらなる演技が加味され、滝沢家の内乱は、より明確に個々を確立してくれた。偏屈であったと言われる馬琴さんも<馬琴の事情>として加藤健一さんの馬琴はよく判ったし、加藤忍さんのお路も大戯作者馬琴に負けないだけの生き方を示してくれた。『滝沢家の内乱』も<忠・孝・悌・仁・義・礼・智・信>をもって納まったわけである。
下北沢・本多劇場 8月26日~30日
滝沢馬琴さんは、江戸時代で亡くなられている。今、河竹黙阿弥さんと三遊亭圓朝さんが、江戸から明治を超えて生きたことに興味がある。
そして、やっと山田風太郎さんの『忍法八犬伝』に入れる。『滝沢家の内乱』を観てからと思っていた。山田風太郎さんのことである、滝沢馬琴さんもびっくりの世界であろう。