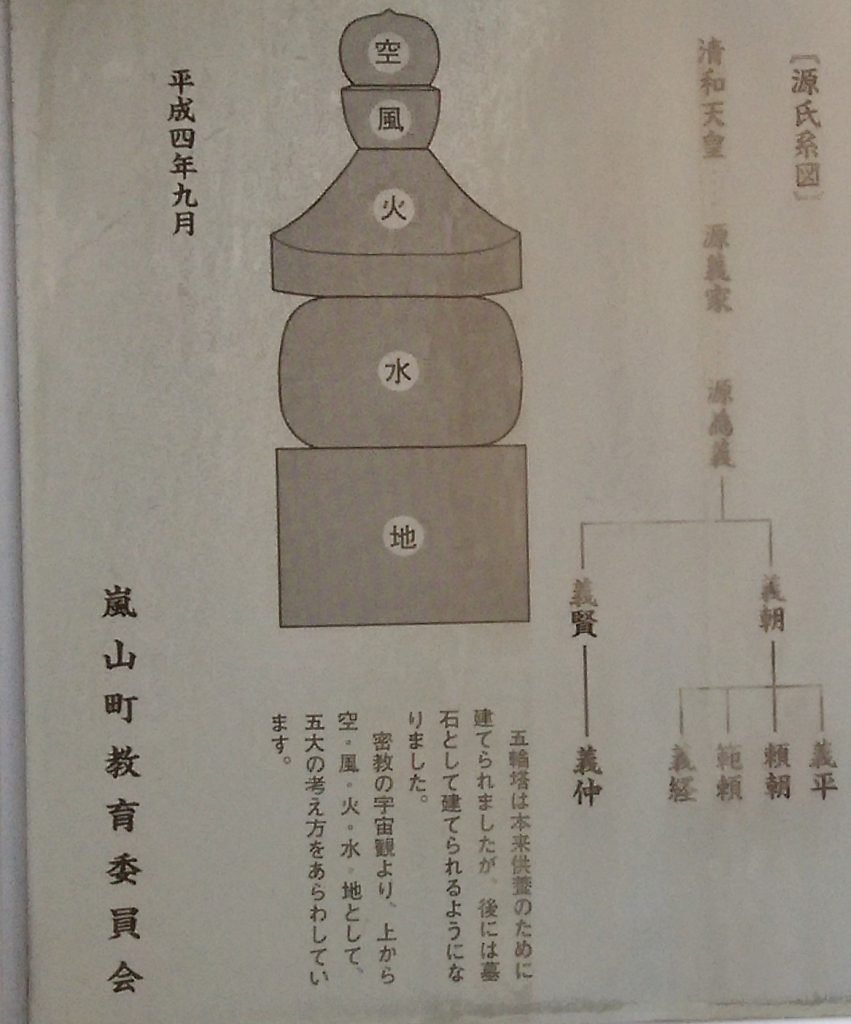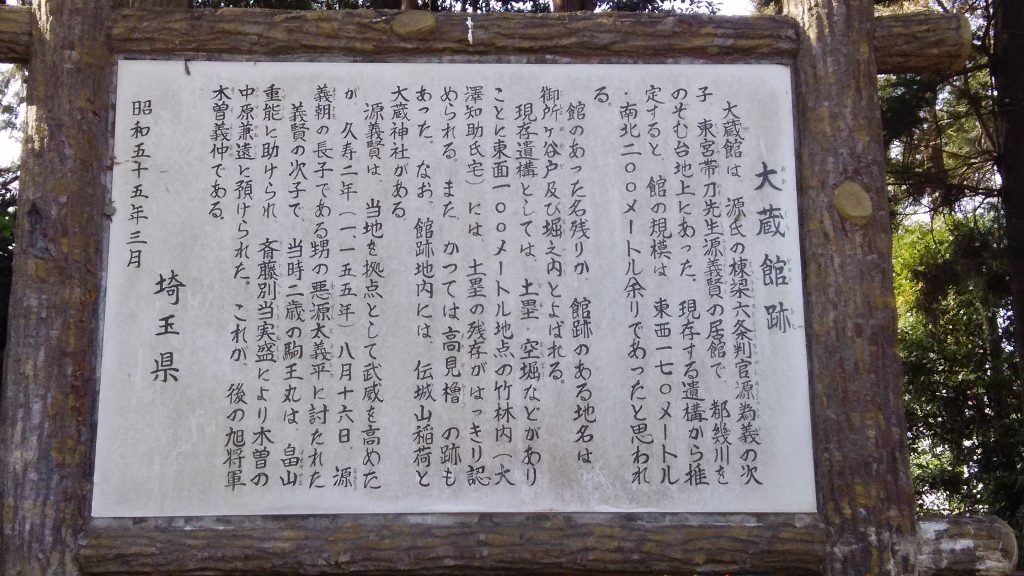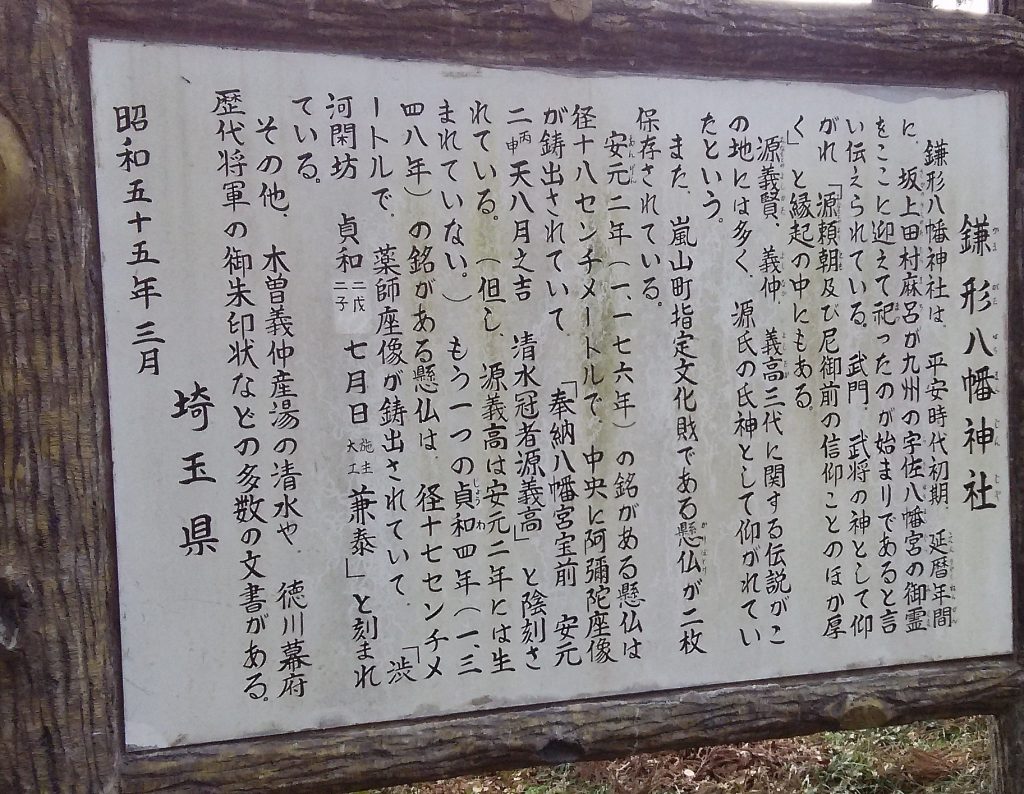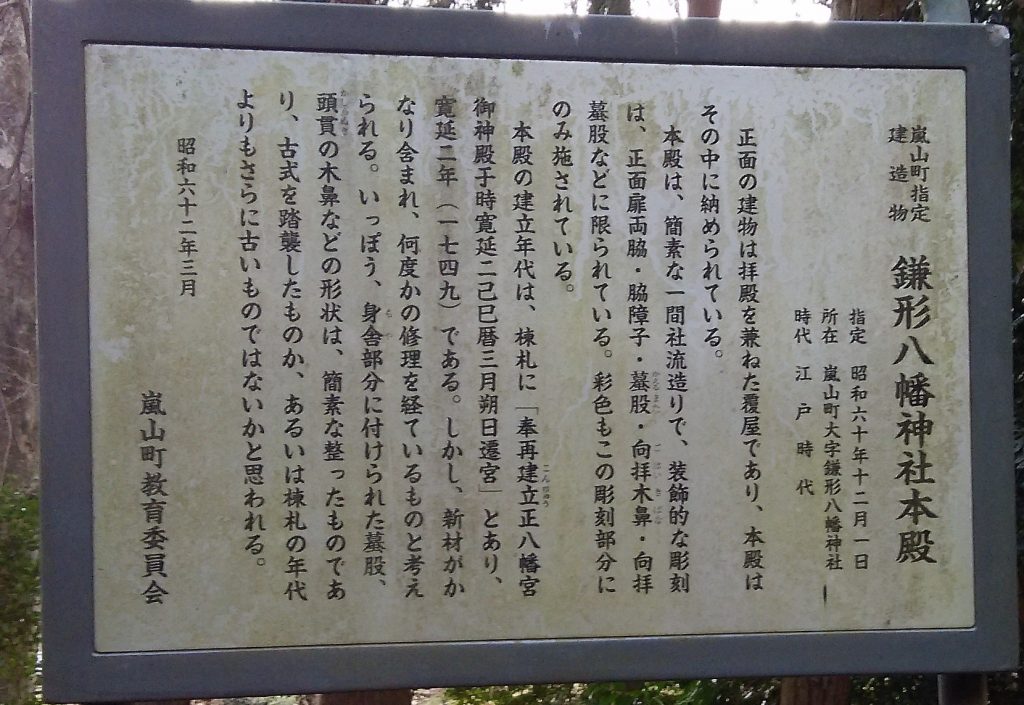- 『吉例壽曽我』は初めてで、曽我兄弟物のこれまた一つである。今度は場所が大磯の「鴫立澤 対面の場」であるから歌舞伎の飛びようは変幻自在である。ただ、東海道という万民周知の設定は外さない。曽我兄弟の仇である工藤祐経が箱根権現に参詣に行くというのであるからこの道である。曽我兄弟は、春駒門付けとしての登場で呼び出すのは小林朝比奈の妹・舞鶴の児太郎さんで、新橋演舞場との掛け持ちである。
- 春駒門付けの兄弟は弟・箱王の芝翫さんと兄・一万は七之助さん。そして鴫立庵にいたのは、工藤祐経の奥方・梛(なぎ)の葉の福助さんである。そのため居並ぶのも女中たちで、馬入川、藤沢、花水橋などの風景を現わすセリフもあり、時期は冬。雪の対面なのである。こういうのも歌舞伎ならではの、小さい舞台に大きな風景を乗せる趣向の定番である。そして、福助さんにその風景を背景とした曽我物にふさわしい大きさがある。今のこの声が好きである。
- 『廓文章』は染五郎さんの伊左衛門のどうしょうもない上方のぼんぼんのダメさ加減と可笑しさをたのしむ。花道でのし所に女形かなと思わせるところがちらっとみえたのが気にかかり、ここが上方の和事の形の難しさなのかなとふっと思わせられた。吉田屋の座敷での場は、よくこうまで夕霧を待つ間に考えるものだと思える一人芝居。会いたい、不満、しっと、不安など様々の心の中の葛藤が身体で表される。観ているほうは笑うしかない。笑えるのは、その身体表現にほころびがなくなっているということである。七之助さんは傾城の大きさと夕霧の本心をゆったりとみせてくれた。
- 『一條大蔵譚』はめずらしく白鸚さんの一條大蔵卿である。若手での記憶が残っているのであるが、今回は、常盤御前が魁春さん、お京が雀右衛門さん、鬼次郎が梅玉さんで、やはり平家時代物の厚さが浮かび上がりその違いを感じた。それぞれの役どころが時代を背景として人物像がはっきりする。それぞれが、秘して生きている。鳴瀬の高麗蔵さんと勘解由の錦吾さんも加わって、大蔵卿の仮りのあほうが明らかになる。大蔵卿のここぞの方向性の示し方、それを受け取る者とがはっきりする濃密な短い時間。そして再び秘密の扉は閉じられる。
- 『絵本太功記』も、光秀の吉右衛門さん、妻・操の雀右衛門さん、母・皐月の東蔵さん、敵側の久吉の歌六さん、正清の又五郎さんでしっかり構成された。息子・十次郎の幸四郎さんと許嫁・初菊の米吉さんが再度のコンビでさらに悲哀を深くした。『松竹梅湯島掛額』で幸四郎さんは吉三郎という若い役で、猿之助さんがそれとなく、若くみせてますが40過ぎていますからといって観客を笑わせていたが、40過ぎようと50過ぎようと若者を演じられなければ歌舞伎役者ではないのである。
- 幸四郎さん、芸の力で若くみせていた。手の置き方、横座りの脚の位置、はやる心の若武者の走り方など上手く調和した身体の芸で、今回はそれがさらに身についていた。米吉さんの初菊も前はただ教わった通りを無我夢中でそれが可愛らしさにつながっていたが、今回は少し落ち着きを持って気持ちを発露させる。このお二人がアップした分、吉右衛門さんの私憤だけではない主君春信を討った動かぬ覚悟のほど、雀右衛門さんのくどき、孫と共に死に臨む東蔵さんの最後、そして結婚したばかり若い二人の哀れさなどが凝縮された。小さな庵で出会ってむかえる家族の悲しみが大きな歴史の一端を展開する。
- 『松竹梅湯島掛額』はこんな笑いも歌舞伎にはありますよという芝居である。時代性も変則ではあるが加味している。木曽の源範頼が攻めてくるということで、町人の娘たちは本郷駒込の吉祥院に逃げ込んでくる。おくれて美しい八百屋のお七の七之助さんもやってくる。範頼は義朝の息子で、頼朝や義経と兄弟ということになるが、木曽とつけているのは木曽義仲を意識して、京に上った時乱暴であったという印象とを重ねているのであろう。そしてこの範頼がお七が美しという話から家来に連れてくるよう命令する。
- ところが、お七は吉祥院の小姓の吉三郎と夫婦になりたいと思っている。八百屋は借金のためお七の母の門之助さんは結婚相手をきめてあるのだがそれも覆しお七は吉三郎一筋に突き進み、最後は「櫓お七」の人形振りとなる。そこまでの悲劇を喜劇でつなぐのが紅屋長兵衛の猿之助さんである。皆にベンチョウと呼ばれていて、お七が悲しむのがいやでお七が笑顔になるように一生懸命にあれこれ考えるのである。それがベンチョウならではのアイデアである。範頼の家来なども巻き込んでのてんやわんやである。お正月にテレビでも放映されていたが、それ以上に松江さん、吉之丞さんらは喜劇役者となっていた。どなたの仕込みであろうか。(竹三郎さんは休演で代役は梅花さん。)
- 初春にふさわしく三番叟の芝翫さんと千歳の魁春さんの『舌出三番叟』と、梅玉さんを筆頭に若い鳶の者が加わり、にぎやかに獅子舞の登場する『勢獅子』の舞踏。踊りあり、重厚な時代物あり、笑いありの歌舞伎座であった。