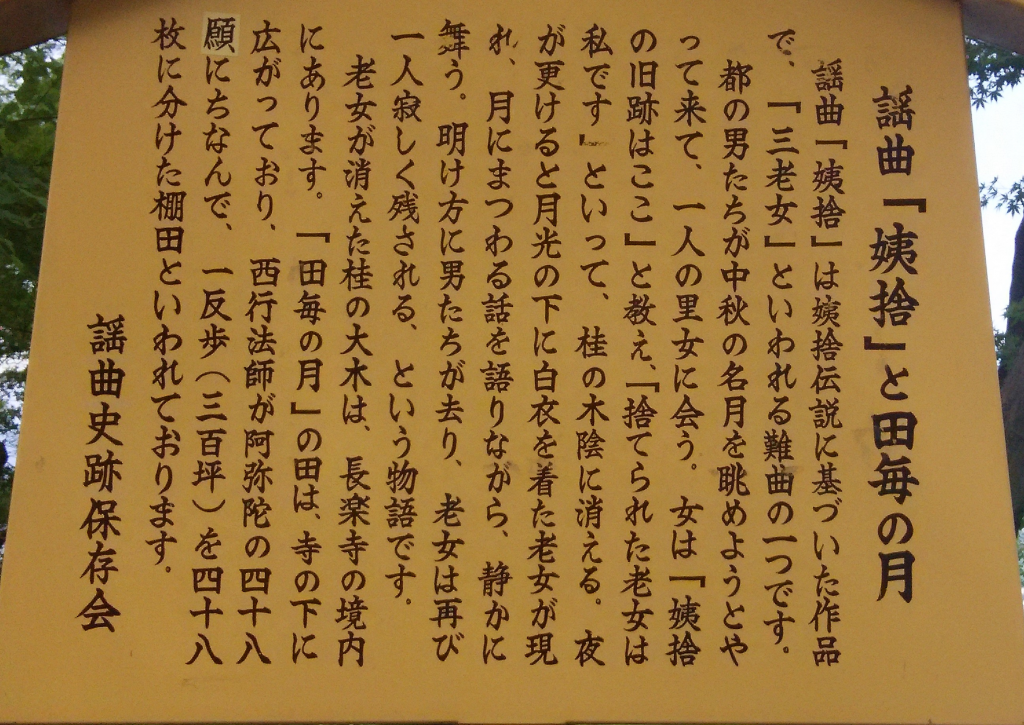終わるつもりがどんどん深入りして道に迷い始めている。楽しいので横路があれば曲り、行き止まりになってもどったりとなかなかの味わいある迷走路である。
『荷風追想』。荷風さんを追想する59人のかたの文章が集められている。
その中に於菟さんの『永井荷風さんと父』、小堀杏奴さんの『戦時中の荷風先生』、茉莉さんの『「フジキチン」ー 荷風の霧』がのっている。類さんの文章はのっていないが、茉莉さんの文章に登場している。それも不律(ふりつ)という名前にしていて、不律さんは亡くなった茉莉さんの弟であり、杏奴さん、類さんのお兄さんである。『荷風追想』に鷗外さんの5人の子供たちが登場したことになる。
於菟さんは、『荷風全集』の附録に書かれたもので、荷風さんの『日和下駄』の「崖」の章の一節に書かれている観潮楼の内部の様子が「情緒を最もよく表している」とし、「時を同じゅうし齢を異にし、しかも心と心とのぴったり合った二文人の出会いを描いた『日和下駄』」をしみじみ読み直してもらいたいとしている。
小堀杏奴さんはご夫婦で荷風さんを訪ねられ、交流があり、戦時中ゆえ品物を届けられたりした様子などが書かれている。これほど親しくされていたというのは初めて知り驚きであった。戦後も市川の菅野の住まいまで訪ねられたようである。
茉莉さんのは、小説となっている。主人公の私は弟の不律と浅草で映画を見たあとにレストラン「フジキチン」に入る。この店は新聞記者が永井荷風を見つけたという場所であった。店の内部の様子から荷風は「欧羅巴(ヨーロッパ)を思い出すんで、くるんだね。」と不律はいう。姉と弟は自分たちの世界に入り込み荷風の話をする。ここでの弟は不律の名をかぶせられた類さんである。
茉莉さんの弟であり類さんの兄である不律さんは1907年8月に生まれ次の年の2月には亡くなっているのである。半年という短い命であった。不律さんと茉莉さんは百日咳にかかり、この可愛い弟が亡くなった時彼女の容態も風前の灯状態であった。もしかすると茉莉さんも駄目かもしれないと一緒に弔うことになるかもという状況であったが奇跡的に茉莉さんは回復するのである。
不律という名前を登場させたのは、あの弟が生きていればこのように語り合ったかもしれないし、もっと違う話をしていただろうかとの想いがあったのかもしれない。他の兄弟とは違う特別の想いが時々生じていたような気がする。
類さん(不律)の状況を姉はみつめる。「不律は頭蓋を締めつけている、コンプレックスという鉱鉄(かね)の輪を、決して脱いではならない冠のように、頭に嵌(は)めていた。途って遣ろうと思う人があっても、除って遣ることが出来ない、それは神が嵌めた輪のように、みえた。自分自身だけの狭い、固い考えの中に縮んまっている為に不律は、人間に馴れない鳥のような眼をした、純朴な男のように、見えるのである。」的確に表現されている。
杏奴さんは、『晩年の父』を荷風さんに贈ったとき「鷗外を語るもののうち、大一等の書と存ぜられ候」との言葉をもらっている。そして対面するのである。
茉莉さんは終戦後、市川真間の荷風さんを訪ねている。自分の原稿を読んでもらうためである。原稿を差し出すや荷風さんの「笑顔は忽ち消えた。」市川真間時代の荷風さんは「他人への心持ちも、変っていたようだ。」茉莉さんは鴎外の子という特権を利用したわけではない。純粋に文学者荷風の眼で文章をみてもらいたかったのである。
真間時代の荷風は杏奴さんが接したころの荷風とは違う人であった。しかし茉莉さんは「荷風の文学が、鷗外なぞは遠く及ばぬ情緒の文学であることは、それらの欠点を帳消しにして、尚余るものであることも、私は知っている。」と荷風文学の魅力に対し変わることはなかった。これは茉莉さんの『ベスト・オブ・ドッキリチャンネル』に書かれているがこの著書が鷗外周辺を離れての上級の迷走路の糧でもある。
類さんの『鴎外の子供たち』(ちくま文庫)も手にすることができた。『森家の人びと 鷗外の末子の眼から』に載っていない文章があり、写真もあり、観潮楼の図面があってこれによって飛躍的に森家の人々の行動の立体化の助けとなってくれた。
写真の中に志げ夫人の写真があり、ちょっと衣装に不思議な気がした。この疑問は杏奴さんが編さんしている森鴎外『妻への手紙』でわかったのである。鷗外さんは妻に写真を送るようにと手紙に何回か書いている。志げ夫人は、花嫁衣裳を着て写したのを送ったことがありその写真であった。結婚の時写真を撮っておかなかったのでこの時撮ったのである。花嫁さんらしくないとして杏奴さんには結婚記念写真は当日撮っておきなさいと告げている。
『妻への手紙』は鴎外さんが細やかに志げ夫人を気づかっている様子がうかがえる。志げ夫人の正直なところそこがいいのだと書いている。そのことで暴発しないことを気づかっている。詩や文学に興味が行くようにそれとなく誘いかけてもいるが、志げ夫人はそれには答えていないようである。すでに自分の実家の貸し家に暮らしていて、鷗外さんは茉莉さんの冬の洋服が千駄木から届くだろうとか、お金のことなど心配しないように気を使っている。鷗外さんの母が財布を握っているので、志げさんの苦労も想像出来る。
鷗外さんんを中心に回るいくつかの惑星はそれぞれの回転で様々な表情をみせてくれる。そこにはまり込むとこちらは迷走するしかないが、驚きと発見に楽しさも与えてもらうことになる。気が向けばそこから抜け出しまた入り込むのである。
『類』を読んで類さんの妻である美穂さんの生きる力に敬服し、あの茉莉さんを疎開先で面倒をみたということに驚愕したが、茉莉さんが『贅沢貧乏』のなかで志穂さんの様子を書かれていた。「弟の家内になった娘は八人家族の家で、母親の代理をやっていた娘である。家族八人だが、三日にあげず客があるから、食事は大抵十五六人前である。母親の方は専ら社交の方面を受持っていた。娘の方も社交に敏腕で、彼女は客があると、台所と客間とを往復し、台所では料理の腕を振るい、客間に入ると、社交の言葉と笑いの花を、ふりこぼした。」「弟の家内という人は自由学園の羽仁もと子式で薫育された、才媛(さいえん)である。」
疎開先ではこうなる。「百姓が舌を巻く位の畑仕事の腕を見せ、薄く柔らかな眉のある眉宇(びう)の間に、負けず嫌いの気性を青み走らせながら、遣(や)ったことのない和服の裁縫を、数学の計算のように割出して遣りおおせた。月が空の中でかちかちに凍っている夜、一人で何百個かの馬鈴薯(ばれいしょ)を土に埋めた。通りがかった知合いの工員が涙を催して手をかしたという、逸話の持主である。」やはりなあと思わせる。
茉莉さんは回転の加速をあげて、どこに飛んで行くかわからないかたである。『ベスト・オブ・ドッキリチャンネル』などは、ベットの上でずーっとテレビを見ていただけあってその感想というべきものはかなり鋭い針のような感触すらある。
ただ多種多様の範囲で見ているのには脱帽である。テレビでみた内容が説明され、あれっ、これは家城巳代治監督の青春映画ではないか。こちらも正確な題名を探す。『恋は緑の風の中』である。原田美枝子さんのデビュー作で原田さんがダントツに光っていたが、その少年少女たちの事ではなく、周囲のおっ嚊あ(おっかあ)たちのことなのである。母親たちのことである。大変立腹していてその一つの例にされたのである。
個人的にはどうして家城監督はこういう青春映画を撮られたのかわからなかったが、茉莉さんが見るとそこを突くのかとこちらの見どころの甘さを感じないでもないがそう立腹するほどの描き方でもないような気がする。
『春琴抄』の山口百恵さんの春琴はほめている。笑わないからである。百恵さんが白い歯をだして笑うのは彼女を嫌う最大の原因としている。茉莉さんの基準は難しいのである。ほめていても、谷崎の小説の中の春琴ではなく、山口百恵の春琴である。それはわかる。
そんなわけで、突然の茉莉流の標識出現に右往左往されつつ笑い、いぶかしがり、喝采しつつ嬉々として迷走させてもらうのである。
そうそうヒッチコック映画に対しても興味深かったのですが、書いていたら際限がなくなりますので、一人密かに楽しみつつ2020年とお別れすることといたします。新しき善き年がむかってきてくれていることを祈って。
![]()