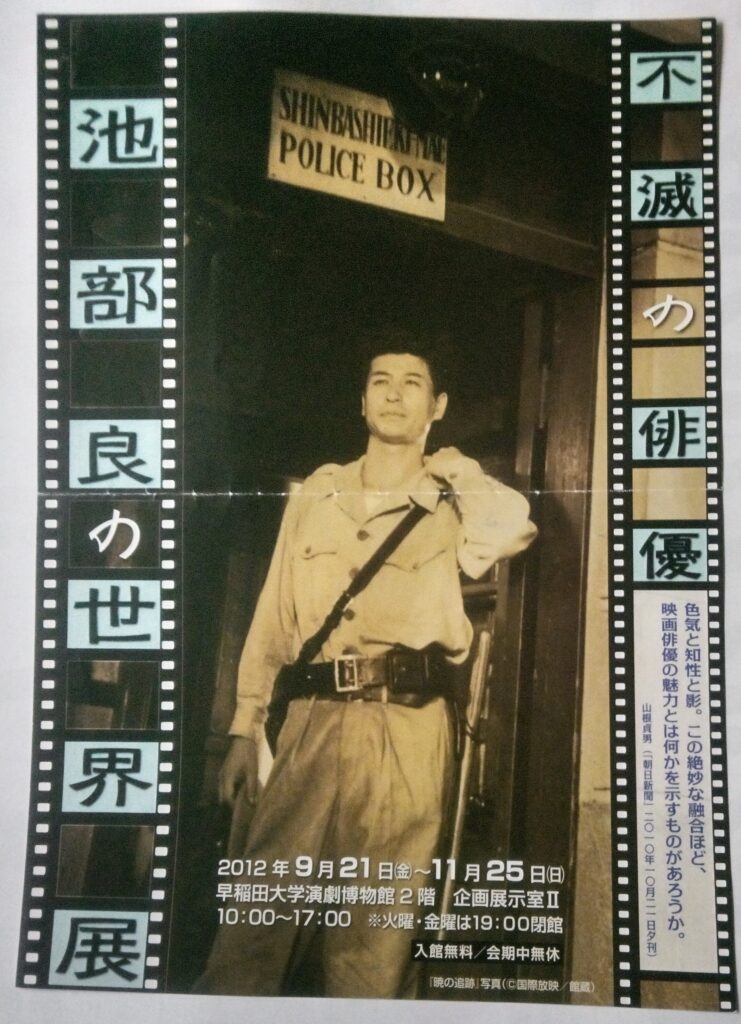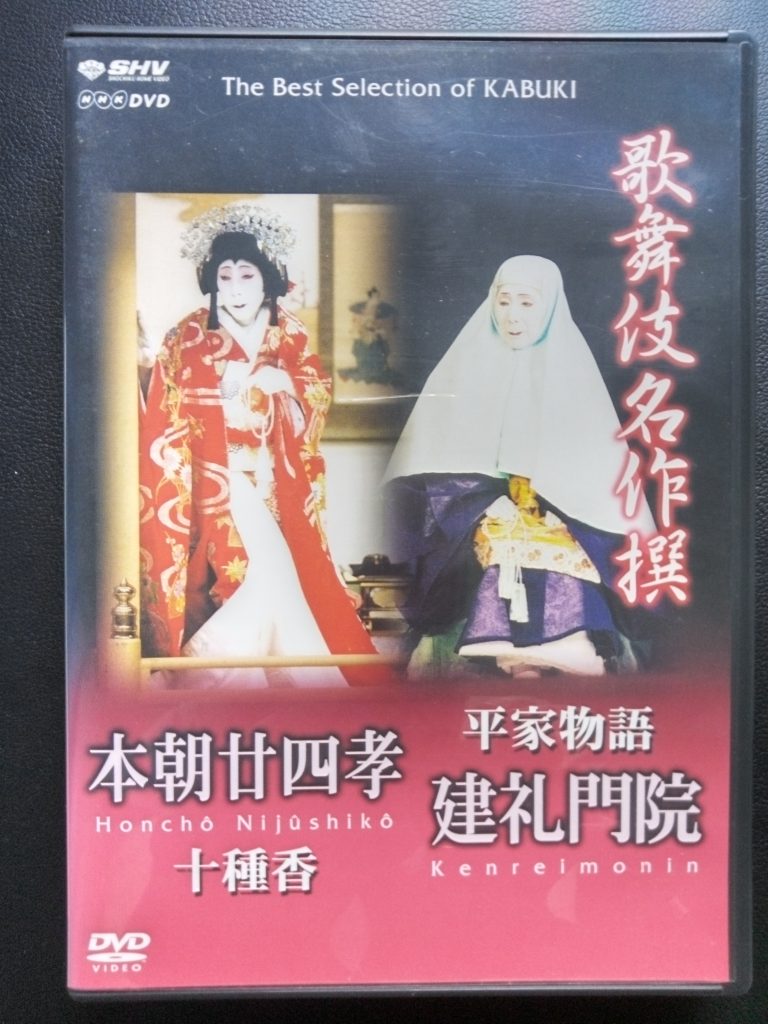友人がNHK「にっぽんの芸能」「歌舞伎・将軍江戸を去る」での市川海老蔵さんの声の出し方が変わったのではないかと思うが、との感想があり急いで録画を見る。この演目は澤瀉屋襲名の演目の一つである。
海老蔵さんが渋い。お腹のあたりが膨らんだりへこんだり。複式呼吸である。台詞の声の幅が豊富で安定している。声を荒げるわけではない。あれだけの呼吸の上下運動があれば声にその息の動きが響くのではと思うがいたって穏やかである。ただ慶喜に対しての場面であるから役柄として当然力の入るところであるが、力みは押さえ、慶喜を刺激し過ぎず、慶喜に<時には裸身に成りたい時も或る>と言わせるあたりの引っ張り方も、ついに慶喜が<鉄太郎を呼べ>と言わせるまでもって行く手順の運びもこの声でやるのである。こういう脇も固められるのだと歓心した。
『将軍江戸を去る』は、江戸城を渡す日、徳川慶喜が水戸に隠棲するため静かに江戸を去るまでの前日と当日のはなしである。
大政奉還も終わり、江戸城無血開城も決まり、慶喜(市川團十郎)は上野大慈院の一室に謹慎している。ところが明日水戸に退隠する予定が慶喜病気のため延期になったと聴き伊勢守(市川海老蔵)がその真意を確かめにくる。謀反を勧めるものもあり慶喜が退隠の意志を翻すのではとの心配からもう一度真意を確かめたいとするのである。同じ様に思った山岡鉄太郎(市川中車)と門前で行き会い鉄太郎を拒む彰義隊を静め同道する。
伊勢守は槍の指南役で慶喜の薩長に対する怒りを一身に引き受ける。慶喜の気持ちが解かりすぎるくらいわかるのである。そう思わせる海老蔵さんの伊勢守であった。そこに別室に控えていた鉄太郎の声が響く。水戸は幽霊勤皇だと叫んでいる。(このあたり意味不明であった)慶喜はついに我慢できなくなり鉄太郎をそばに呼ぶ。ここから鉄太郎=中車さんの見せ所である。
鉄太郎は時には慶喜を刺激し熱弁である。意味不明であった<尊王>と<勤皇>の違いもなんとなく理解できた。<頼朝以来の武士の政権を壊す><国土と民を皇室に返し徳川家は一代官となる>そこまでやらなくては徳川家の権力をまだ夢見ている人々と薩長との争いで江戸は火の海となり、罪無き江戸の民が巻き込まれてしまう。(そのように理解した)鉄太郎は二回ほど言ったと思う。自分も時の流れの中でそのことが解かったのだと。
このあたりは鉄太郎=中車さんの何とか慶喜の怒りがあらぬ方向へ行かせず決めた真意を貫かそうとする姿と襲名した一役者の一生懸命さが重なる。
印象的なのが後ろに控えている伊勢守である。鉄太郎の考えをじっと聴きつつ、そっと目線が慶喜の方に動く。その目が何とも言えない。慶喜に対する不安と慈愛と祈りが混ざりあっているように見える。そこで初めて解かる。伊勢守は自分では慶喜の気持ちが解かり過ぎ慶喜の情に負けてしまうと考え、鉄太郎なら慶喜の進むべき道を間違わせずに解き明かすであろうと考えたのだと。
鉄太郎もそのところは解かり、慶喜も二人の思いが解かったと思う。
次の朝、千住大橋で江戸の人々に見送られる。鉄太郎が<その一歩が江戸の端です>と。焼け野原の江戸ではなく、昨日と同じ江戸を残して慶喜は江戸の人々と別れをつげるのである。
山岡鉄太郎は山岡鉄舟である。あの『塩原太助一代記』を書いた圓朝と一時期住まいが近く交流もあった人である。またまたここでお会いできるとは、まだ他でもお会いしてるのです。映画「勢揃い東海道」で片岡千恵蔵さんの清水次郎長に市川右太衛門さんの山岡鉄舟。実際に繋がりがあったようで、山岡鉄舟という方はかなり広範囲の方と交流のあった方らしくその辺を考慮するなら中車さんはもっと味のある山岡鉄太郎も作りあげられるのではなどとも考えたのだが。
作・真山青果の維新三部作の三部目である。『江戸城総攻』『慶喜命乞』『将軍江戸を去る』