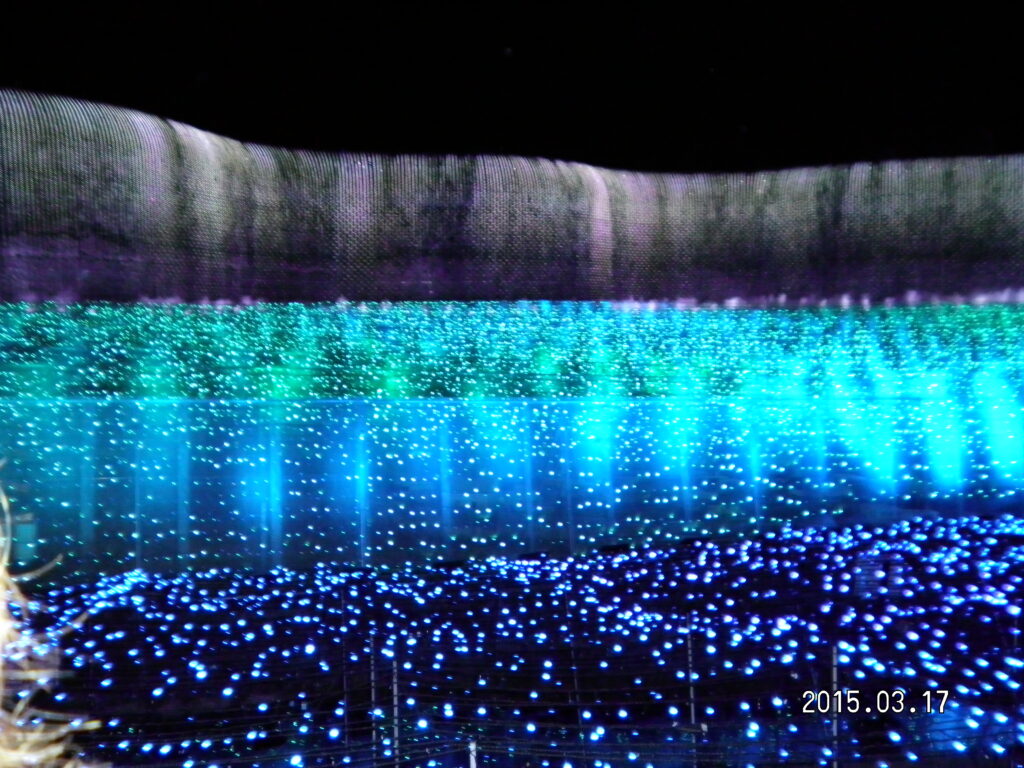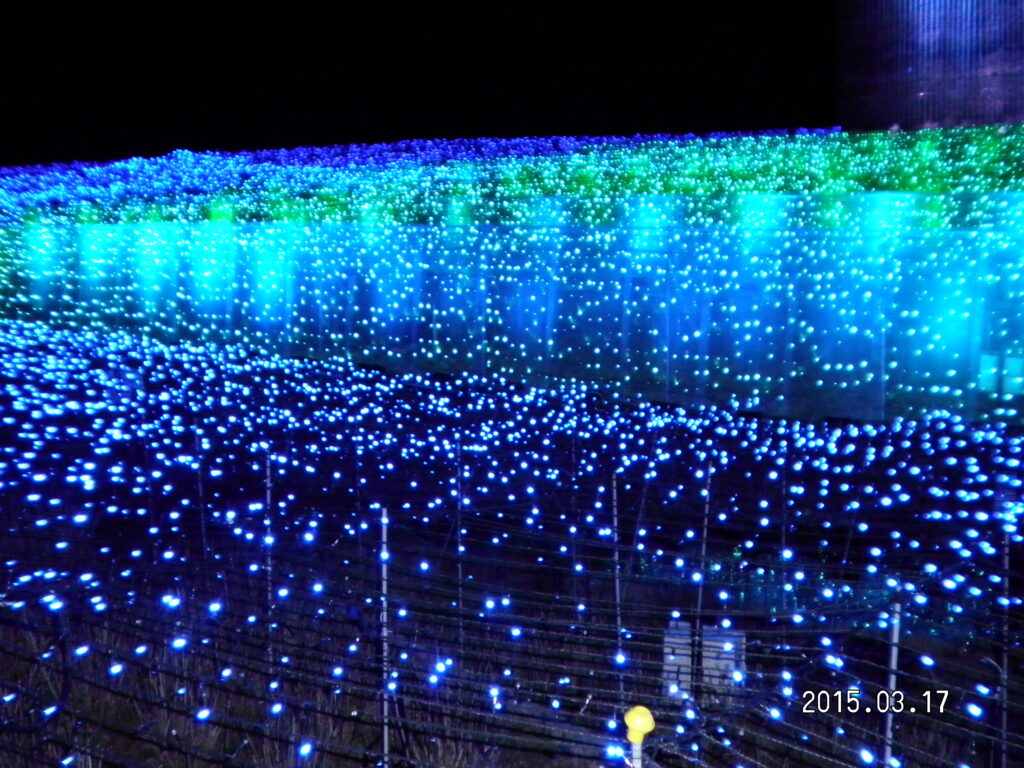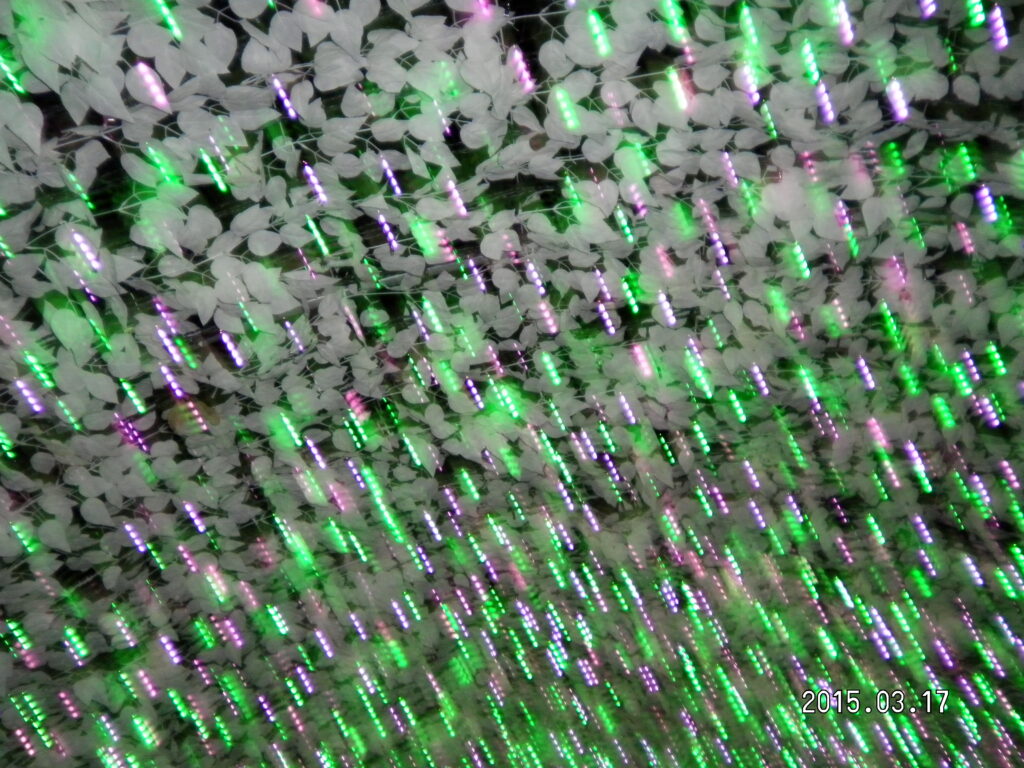永代橋『梅雨小袖昔八丈(つゆこそでむかしはちじょう)ー髪結新三ー』。この<八丈>というのは、材木商・白子屋の娘・お熊が着ていた着物が黄八丈であり、芝居では、新三に騙され駕籠で運ばれる時、駕籠から黄八丈の着物の袖が出ている。そして、雨が降ったり止んだりしている。初演は明治であるが、河竹黙阿弥作の江戸の風物たっぷりの作品である。
地域設定が隅田川(大川)に架かる<永代橋>を挟んで、日本橋(新材木町)と深川(冨吉町)であり、蔵の連なる町と漁師町との違いがある。髪結新三は、店を持たない渡りの髪結い業である。大店を回り愛想よくご機嫌も取りつつ髪を結い直したり、なでつけたりする賃仕事である。この新三は、実は上総無宿者で、左腕には二本の墨が入っている。
材木商の白子屋では、娘のお熊の婿取りが決まり結納のお金が届けられる。それが相当の金額である。白子屋は主人が亡くなり相当家運は傾いていて、お熊に持参金つきの婿を取ることで、建て直しを図ろうとしている。お熊は、手代の忠七と恋仲であり連れて逃げてくれと云うが、手代ではどうする事もできない。そこへ目をつけたのが新三である。しかし、新三は白子屋が傾いていることは知らず、このことは新三の誤算であった。このことは、こちらも、今まで重要と思っていなかったが、一つの要となっていた。
新三は忠七に、想い焦がれた人に裏切られたとお熊が身投げでもしたら不忠になるから、お熊を外の風に当たらせ親の気持ちを考えさせ、そこで説得して家にもどせば、お熊の命も助け、主への功であると持ち掛ける。ここが、大店の手代で、新三の裏など見抜くことが出来ない。まんまと乗せられてしまう。新三の家に一時居させてもらうということで、お熊は籠で運ばれ黄八丈の袖が覗くのであるが、新三の子分の勝奴がそれを駕籠中に押し込む。
後から一つの傘に入った新三と忠七は、永代橋にさしかかる。ここから、髪結いの新三は、上総無宿の新三に変る。下駄、番傘の小道具、雨音、川音、下駄音等をふるに生かしての新三の変身の見せ場である。そして傘尽くしの台詞が加わる。新三の罠にはまった忠七は大川に身投げしようとするが、乗物町の弥太五郎源七親分に助けられる。
永代橋を渡った深川富吉町の長屋に新三は住んで居る。冨吉町は今もある江東区の正源寺の北側に位置し、東に向かうと富岡八幡宮である。
富吉町の長屋の新三内からは、江戸庶民の生活が映し出される。もともと粋がっている新三は、白子屋から百両は届くと思って居るから、ますます態度も大きい。朝湯から浴衣姿で花道を戻って来る。この浴衣、白地に大きな文字や模様が入り、特に<ひら清>の文字が目についた。筋書の説明によるとこの<ひら清>は、富岡八幡宮のそばにあった有名な料亭の名で、こうしたところの手ぬぐいをつないで作った浴衣だそうである。面白く染め抜いた浴衣地と思っていたので、新知識いただきである。住居内に掛けられるときも、この<ひら清>が見えるようにかけられた。
花道で新三は初鰹を買う。長屋の住人に言わせると、この初鰹一本の値段で合わせの着物が整うだそうである。魚屋の鰹さばき、新三の着替え、髷にさしていた今でいう歯ブラシの竹ようじの扱いなど、新三の粋がる仕草は随所にある。
そこへ、乗物町の親分が仲裁にくるが、その金額が少ないのと、大川からあちら側の人間に対する今までの新三の鬱憤が爆発する。乗物町も新木材町側であり、さらに親分風を吹かされることに、新三は勘弁出来ないのである。親分も白子屋の事情を知って表ざたに出来ないし、親分も内密に納めるには十両では少ないと思ったとおもうが、自分の顔で新三も折れると踏んだのであろう。粋がっている若いチンピラとその子分に散々<おじさん>と悪態をつかれ恥をかかされた親分は、怒り心頭であるが、忍耐してその場を去る。この辺りにも、白子屋のお金の無さの事情が絡む。親分が来た時、客の為にゴザをひくのも面白い。
今度は、大家が仲裁に現れる。鰹を半身もらい、刺身にした鰹の一切れを口にする。このとき、箱前の食器に目がいった。新三は自分の使った箸を、盃洗いで洗い、箸の雫を器に音を立てて払う。この辺りもさりげない粋な道具使いである。
渋谷の戸栗美術館で『江戸の暮らしと伊万里焼展』を見て来たので、盃洗い、刺身をのせる皿などに興味がいく。お金のある者の大皿料理のための色絵付けの器が、会席料理の登場や江戸庶民の外食産業の発達により、庶民の生活の中にも、器の模様に藍色が一色入って来る。蕎麦猪口などは、小鉢の代わりとして楽しんだりしている。その絵も謎解きのように、歌舞伎の演目などをあしらったりしている。
新三のような無宿者は、面倒を起こされては叶わないと大家も避けるが、ここの大家はお金になればよいので、反対に新三の腕の二本の入墨を脅しにの材料にしてしまう。新三より上手である。百両入ると思って居た新三も、大家の悪知恵には叶わなかった。半身の鰹にかけた金の勘定と家賃を取られて、二つ名前の弥太五郎源七親分の十両に少し色がついた形でお熊を返すこととなる。
しかし、傷つけられた侠客の意地は消せない。閻魔堂橋で新三と弥太五郎源七の刃物沙汰となる。
橋之助さんは、初役ということもあり、一つ一つの動きを身体に教え込むように丁寧に演じられる。そのため、こちらは橋之助さん独特の、台詞の妙味や味わい、動きのリズム感を楽しむよりも、黙阿弥さんが描きたい、江戸というものの風俗、習慣、土地柄などを味わわせて貰った。黙阿弥さんの台詞、動きは見るたびに発見させてもらう。無理な笑いを取らない、すっきりとした新三だったので、橋之助さんはこれから、その間、小悪党の汚れなどが加味していくのか、このままの切れ味で大きくしていくのか興味のあるところである。
児太郎さんの黄八丈が映える。最初に児太郎さんのお熊を観たときは、周りに支えられてるなと思ったが、今回は、しっかりお熊の役どころを考えての工夫だなと感じられた。新三宅から解放される時は、やつれが見えた。戸だなを叩いていた必死さが想像できる。
白子屋で、持参金のお金の額に目を行かせてくれた、加賀谷藤兵衛の松江さんの貫禄もよかった。何んとか困っている白子屋の役に立とうとする善八の秀調さん。その姪の芝のぶさん。手代忠七の門之助さん。白子屋の女主人の芝喜松さん。家主の女房の萬次郎さん。周りをきちんと固めている。
弥太五郎源七の錦之助さんは、新三より年上のおじさんであるが、おじさんにこだわらず、新三なんぞなんだ小童がとの意気込みで臨んで欲しい。大家の團蔵さんは悪のほうに力を入れた化粧でもあり、それはそれで、橋之助さんの新三には合っていると思う。勝奴の国生さんも新三の子分として背伸びの粋がりで頑張った。
『三人形』。常磐津舞踊である。若衆<錦之助>・奴<国生>・傾城<児太郎>が人形の箱から出て来て踊るという趣向である。この若衆のことを丹前侍ともいうらしいが、そこのところがよく解らない。名作歌舞伎全集には「古風な丹前振りを見せる」とあるが、奴と二人での花道での踊りであろうか。背景は、吉原の桜が満開の仲之町に変わり、廓の話など出てきて、最後は三人での<さんさ時雨>の手踊りがあり、艶やかに幕となる。錦之助さんは二枚目の若衆を品よく、奴の国生さんは勢いよく、傾城の児太郎さんは、背の高さを上手く使った衣裳と踊りで、花見の座での一服の茶の味である。