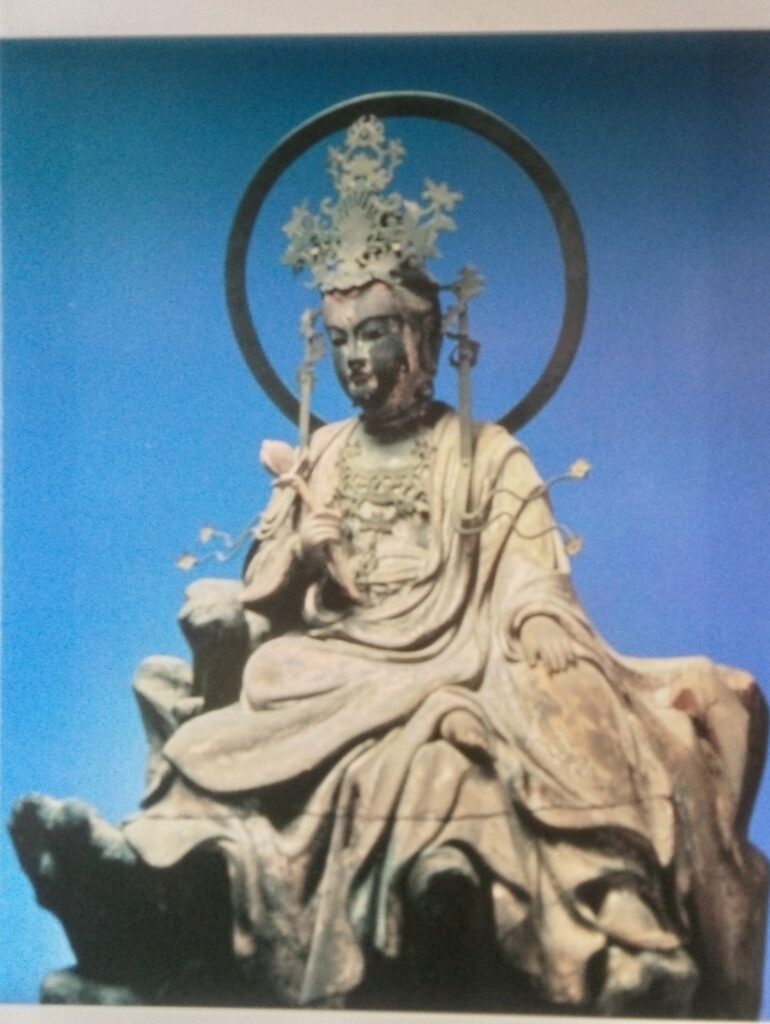2014年1月の最大イベントは、遠方より友が来て、東京の町歩きをして、飲み語らうことであった。町歩きは谷中周辺から上野と決めた。谷中・根津・千駄木の谷根千となるとかなり範囲が広くなり、さらに上野に抜けるとなると時間的無理が生じる。
何時ものことながら内田康夫さんのお世話になって『上野谷中殺人事件』を読む。<谷根千>の命名者・森まゆみさんをモデルとしているらしき人も登場する。森まゆみさんは世田谷文学館の『幸田文展』の監修者でもある(堀江敏幸さんと)。世田谷文学館 『幸田文展』 この小説に出てくる江戸川乱歩の乱歩から名前をとった喫茶店「蘭歩」は三崎坂にあることになっていて、三崎坂につながって千駄木にあるのが、団子坂である。団子坂には青鞜社発祥の跡や森鴎外の旧居「観潮楼」跡に森鴎外記念館がある。そして、乱歩もこの辺りに住んでいて乱歩の小説『D坂殺人事件』のD坂は団子坂のことである。『D坂殺人事件』が大正時代に倒錯した性、錯覚の説明などを書き表しているのには驚いた。江戸川乱歩は、エドガー・アラン・ポーからとっているが、ポーの『モルグ街の殺人』を鴎外は『病院横町の殺人事件』のタイトルで訳している。『上野谷中殺人事件』には、谷中銀座、昔藍染川だったよみせ通りが出てくる。
風野真知雄さんの『耳袋秘帖 谷中黒猫殺人事件』は時代物で、三崎坂は三遊亭圓朝作の『牡丹燈籠』の舞台の坂と説明している。三崎坂を上がりきったところに岡場所があり、そこを左に曲がると五重塔で有名な感応寺(かんのうじ)でのちに天王寺となったらしい。今は無きこの五重塔が幸田露伴さんの小説『五重塔』のモデルである。その他、七面坂、千駄木坂、三浦坂、芋坂なども出てくる。時代ものであるから、今は流れていない藍染川が流れている。
谷中・千駄木は数回歩いているが、時間も立っており心もとないのと、地図を見ていると歩きたくなり日暮里から下調べである。日暮里から御成坂を上がって左手の朝倉文夫の朝倉朝塑館を確認。御成坂にもどり右手の諏訪神社をめざしそこから富士山の見えていた富士見坂を下り、適当なところから夕焼けだんだんの谷中銀座へでる。そこを抜けるとよみせ通りにぶつかる。それを左に千駄木方面に向かうと三崎坂にぶつかり右手は団子坂。三崎坂を渡りへび道へ。この道は旧藍染川のながれにそってヘビのようにくねくねと曲がった道である。そこからあかじ坂、三浦坂を探し不忍通りに出て忍ばず池を目指す。不忍池は琵琶湖に見立て、弁天島は竹生島を模している。水上音楽堂をすり抜け下町風俗資料館へ。そこから、不忍通りを渡って森鴎外の『雁』の舞台である無縁坂から岩崎邸へ。これはかなりきつい。検討しなければならない。
谷中を歩くと知った他の仲間が千駄木に指人形のお店があるらしいと教えてくれる。指人形劇もあり、そのお店「笑吉」に電話で尋ねると、三人集まれば人形劇をやってくれるとのこと。4人であるから、それもその時の状況に合わせよう。今回はその時の皆の乗りに合わせることにする。