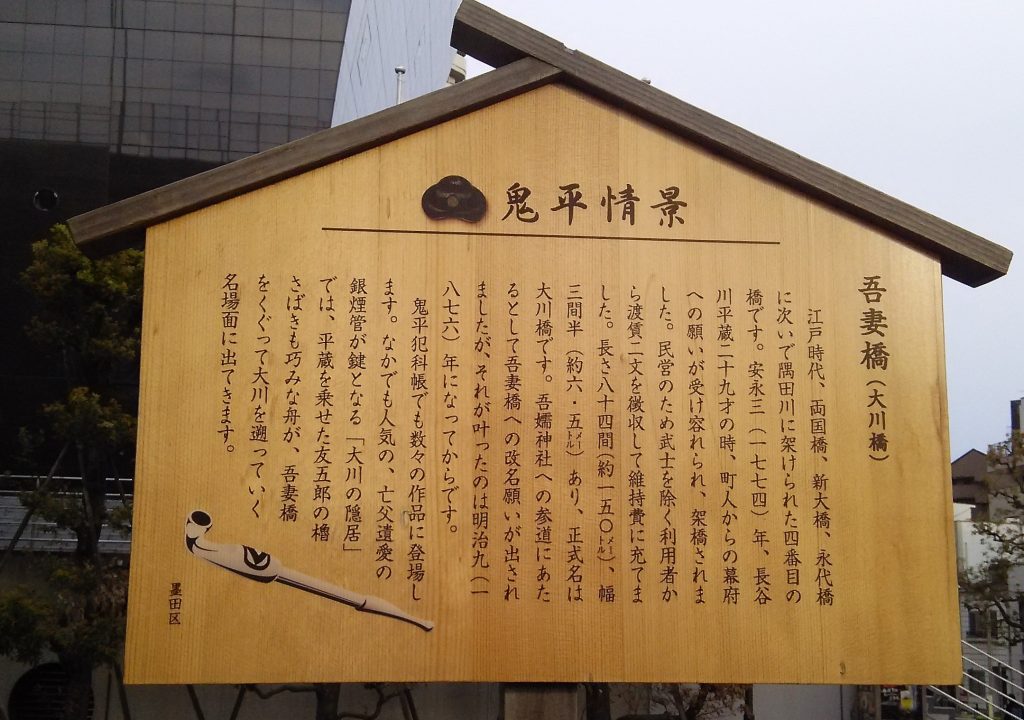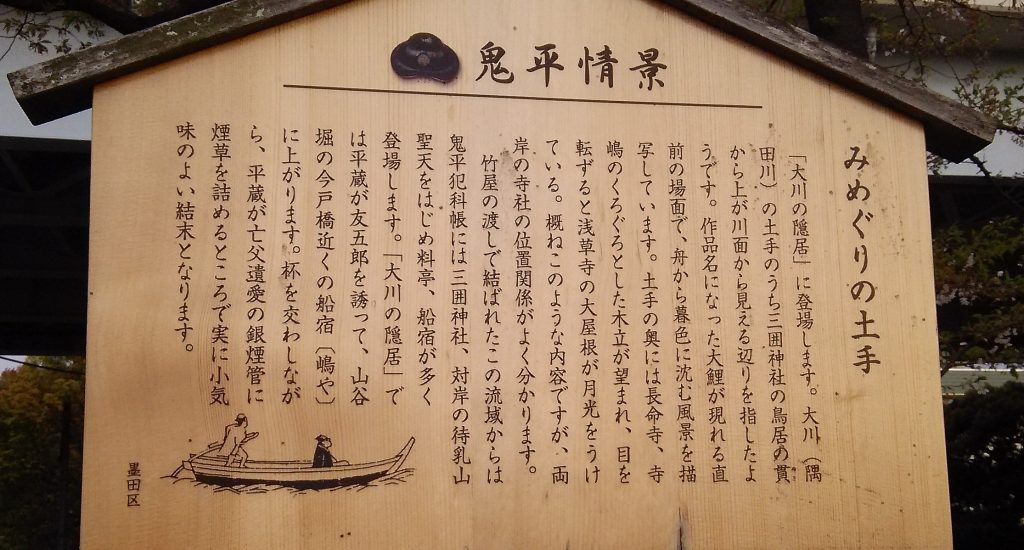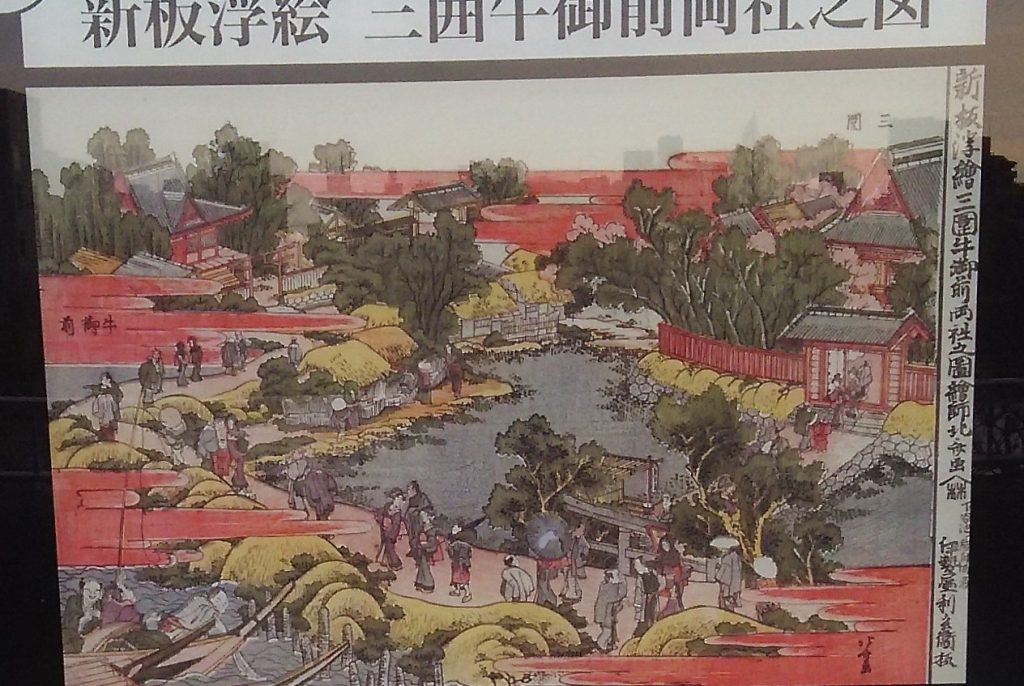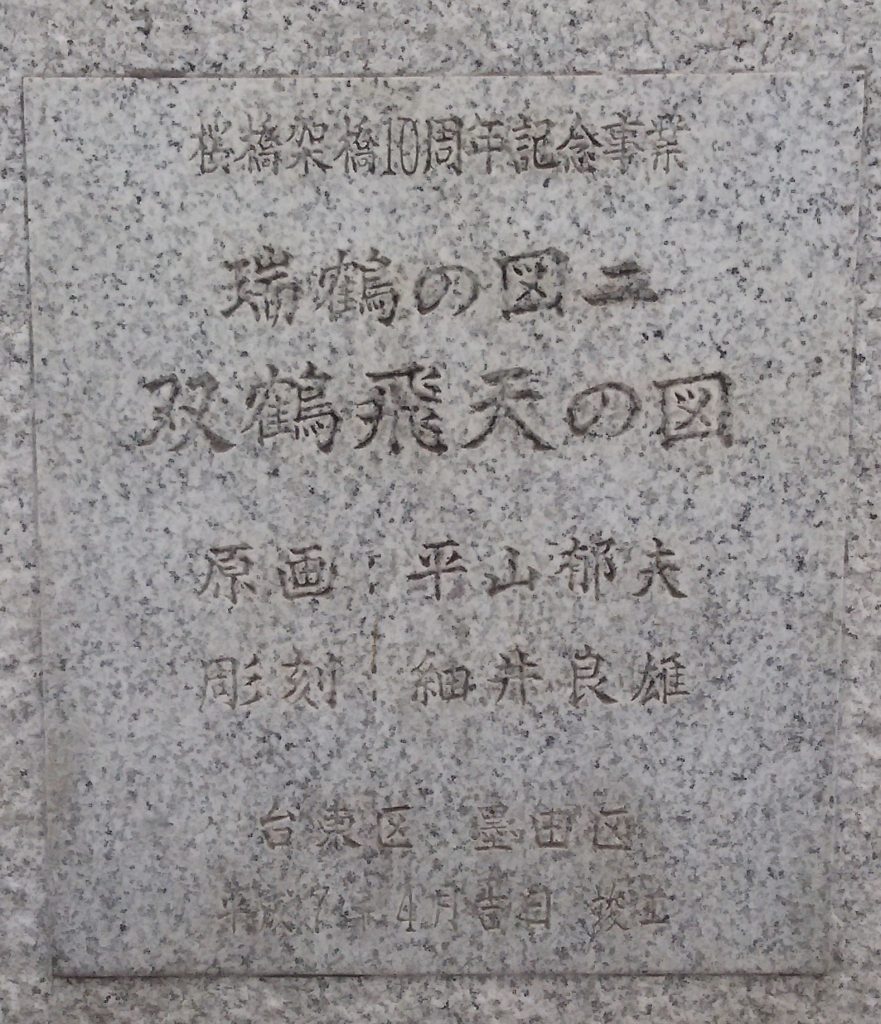江東区『深川江戸資料館』へ新内を聴きに行った。常設展示室の火の見やぐらの下まで流してきて、簡単な解説を入れて新内を聴かせてくれ、また流していく。少し休憩があって、また流してきてとこれが一時間の間に三回ある。
資料館での「新内流し」は初めての体験である。演者は新内多賀太夫さんと新内勝志壽さんである。演目は『狐と弥次郎兵衛』で、新内と言えば心中物とされるが、『狐と弥次郎兵衛』のように滑稽な内容の物もありチャリ物と言われると説明がった。
内容は、弥次郎兵衛が喜多八とはぐれてしまい、赤坂の松並木で自分に化けた小狐に会い一緒に踊ってしまい、狐は逃げ出してしまう。その話を簡単に置き、クドキなどの三つにわけ、三回分のそれぞれの聴きどころを押さえて語られたのである。吉原かぶりのこと、縞の着物は新内が流行らせたこと、三味線は細いヒモで支えられていること、上調子の三味線のバチがとても小さいことなどを説明してくれ、新内に少し近づいた気分にさせてくれ、高音で聴かせどころを語ってくれた。
知らなかった新しい知識ももらい楽しかった。帰ってからCDで『蘭蝶』を聴いてしまった。こちらは端物という。
企画展『杉浦日向子の視点 ~江戸をようこそ~』(11月10日まで)とゴールデンウイーク特別展『深川モダン ~文化で見る近代のKOTO~』(5月6日まで)も開催されていて、いやいや、ごっつあんです、である。
杉浦日向子さんとはアニメ映画『百日紅』以来であろうか。 『肉筆浮世絵 美の競艶』展
杉浦日向子さんの原作でもう一本映画があるのを知る。映画『合葬』である。彰義隊の若者たちの青春群像を描いている。漫画の実写化で原作は読んでいないが何となく杉浦日向子さんの社会性から少しずらした若者の心情が出ていて漫画の一コマはこんな絵かなと想像してしまう。
三人の若者が彰義隊に参加する。徳川慶喜が江戸を去る時に見送った秋津極は、その姿をみて慶喜の敵討を決意する。福原悌二郎は妹・砂世が極と婚約しているのでそれを反故にするのかと極にせまる。そこに居合わせた吉森柾之助は養子先の父が仲間内の争いで殺されその仇を義母から言い渡され、都合の良い養家からの追放であった。三人は幼い頃から知っており、写真を撮り三人の若者が彰義隊に参加する。
徳川慶喜が江戸を去る時に見送った極は自分から彰義隊に入るが、柾之助は行くところがないので何となく引っ張られて入隊。長崎で蘭学を学んだ悌二郎は彰義隊など意味がないとして解散を説得するためについてゆく。彰義隊の指導的立場の森篤之進は、新しい生き方を望む者は去らせ、それでも志を曲げない者たちの死に場所を作ってやりたいと思うが、上のほうは何の方針もなく、ただ若者たちを鉄砲玉の替りとしか考えていない。
腰抜けだと森は若い彰義隊に殺されてしまう。森の想いを知っていた悌二郎は、彰義隊を離れるが妹のお嫁に行く前に極に一度会いたいという想いを遂げさせるため再び彰義隊にもどる。そして開戦に居合わせ、二人だけ死なせるわけにいかないと残るのである。
柾之助が好きになった娘が極を好きであったりと淡い恋い心も挿入されている。そして三人のその後は・・・
(監督・小林達夫/出演・柳楽優弥、瀬戸康史、岡山天音、門脇麦、オダギリジョー)
『杉浦日向子の視点』の展示内容も杉浦日向子さんの江戸ワールドが展開されている。江戸で人気があった三男が火消、力士、与力とある。これは、『一日江戸人』にも書かれていることであるが、与力とあるのが面白い。与力は上下色の違う裃(継裃)であったが、幕末には羽織となる。しゃべり方が「来てみねえ」「そればっかり」「そんななァ嫌(きれ)ぇだよ」と庶民に親しみを与え、金銭的にも余力があり、こせこせせず遊びにも精通していたようである。杉浦日向子さんの好みと研究の深さがわかる展示である。
もう一つ『深川のモダン』の展示は、深川の出てくる書物を探し出しその書物を展示し、さらにそれを書いた著者も紹介している。その数が多いのである。よく探し出されたと思って係りの人の尋ねたところ、この資料館の館員さんたちが探し出したのだそうである。
小津安二郎監督、谷崎潤一郎さん、永井荷風さん、泉鏡花さんなども別枠となっていて、泉鏡花さんはタウン誌『深川』で特集「鏡花と歩く深川」となっており、これでまた鏡花さんの歩いた深川めぐりを楽しむ機会が増えた。