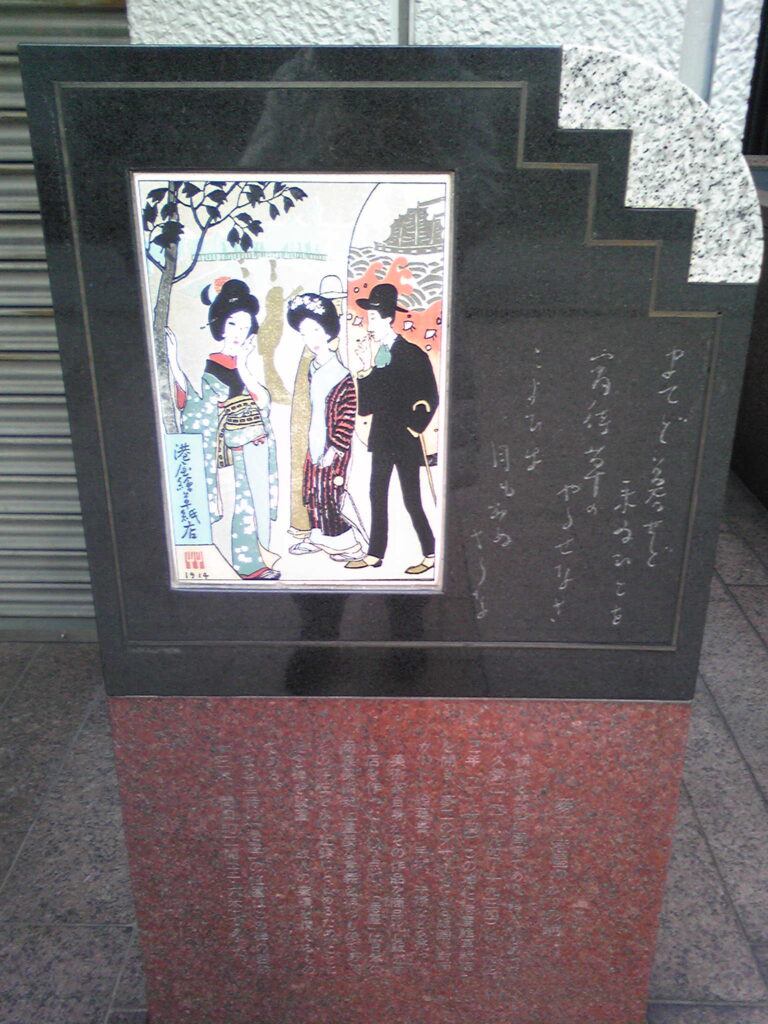久々の新作映画鑑賞である。と言っても「ヒッチコック」は映画「サイコ」に関連していているので、「サイコ」をまた鑑賞するような雰囲気であるが、様々な舞台裏が出て来て面白かった。まず、アンソニー・ホプキンスのヒッチコックがぴったりである。太り具合はもちろんであるが口の動かし具合からしてしっかり捉えている。「サイコ」を撮ろうとの動機からの奥さんとの会話が何ともお互い機知に富んでおり楽しい。儲からない仕事はどこもそっぽを向くもので、それを内心の動揺をかくしつつも奥さんに吐露しそれを軽くいなす奥さん役のヘレン・ミレンも適役。
色んな問題が山済みでさらには奥さんと男友達との関係も目が離せない。それでいて美人女優でなければ撮りたくない。「サイコ」のモデルである異常殺人者の実物の犯人ともヒッチコックの中で語り合わせ、誰の中にでもある異常心理の狂気としてヒッチコックを追い込んで、それがあのシャワーシーンの成功へと結び付けていくあたりは上手い展開である。ジャネット・リーが雨の中追いかけられるように車を走らせる場面の撮り方など裏が見れてわくわくする。
アンソニー・パーキンスの出は短いが、雰囲気はわかり、彼はやはり「サイコ」の実際の彼を見るのが一番でそれを邪魔しない出し方である。検閲官の厳しい制約が、反って映画の撮り方に工夫する結果となり、そのやり取りから撮影方法が浮かび上がるのもさすがである。宣伝の仕方、公開されてシャワーのシーンにロビーでその音楽に合わせて身体を揺り動かし満足する稚気さら、映画を見ている観客をもどんどん巻き込んでゆく。この音楽を入れることを提案したのは奥さんである。
そして、奥さんをやり込めるつもりが、反対にやり込められ、その時のヘレン・ミレンはさすが「クイーン」女優と思わせる。やり込められて唖然とし、それでいて安心しているアンソニー・ホプキンスの繊細さを判らせない余裕の演技も見事である。最後お決まりのヒッチコックの登場で次のサスペンスへのお誘いで肩にカラスが。でも当然「サイコ」を見直したくなる。
「舟を編む」。2012年の本屋大賞第一位のベストセラーを映画化したものである。本の題名がそこらに転がっていそうもない発想である。内容も、辞書を作る編集部に集う人々の話で、心躍る事件も起こりそうに無いが、そのとおり起こらないで辞書の役目のような役目をする、そこに有ってくれれば、そこに居てくれればいいなあ思わせる人々の話である。
原作を読んでいたので、これを壊されるといやだと思いつつ観たが、なかなか味のある映画になった。松田龍平さんが主人公の馬締光也をだんだん男前にしていってくれた。それもそれに気がつくか気がつかない加減で進んでいく。それを助ける軽薄なオダギリジョーの西岡の役目も上手くはまった。小説もそうであるが、人間関係の暖かさと同時に辞書ともっと仲良くしなくては勿体無い事であると思ってしまう。映像での辞書の言葉たちが本よりも強く印象づけた。沢山の言葉に触れたい人は小説の方がいいと思う。作業などは映画のほうが動きがあって流れが飲み込める。人間関係の下手な馬締くん(まじめの当て漢字が何とも冴えている)を無理に変えようとせず、そのままで上手く周るようにした脚本も芯がある。観ているほうもやはり馬締くんはこう来るのかとこちらも楽しい笑いと先輩達に対する気持ちにほろリとする。舟を辞書「大渡海」のカバーデザインだけで、海の映像に出さなかったのも懸命である。「大渡海」の辞書編集部は嫌々行っても夢中にさせるゆれ具合の舟である。