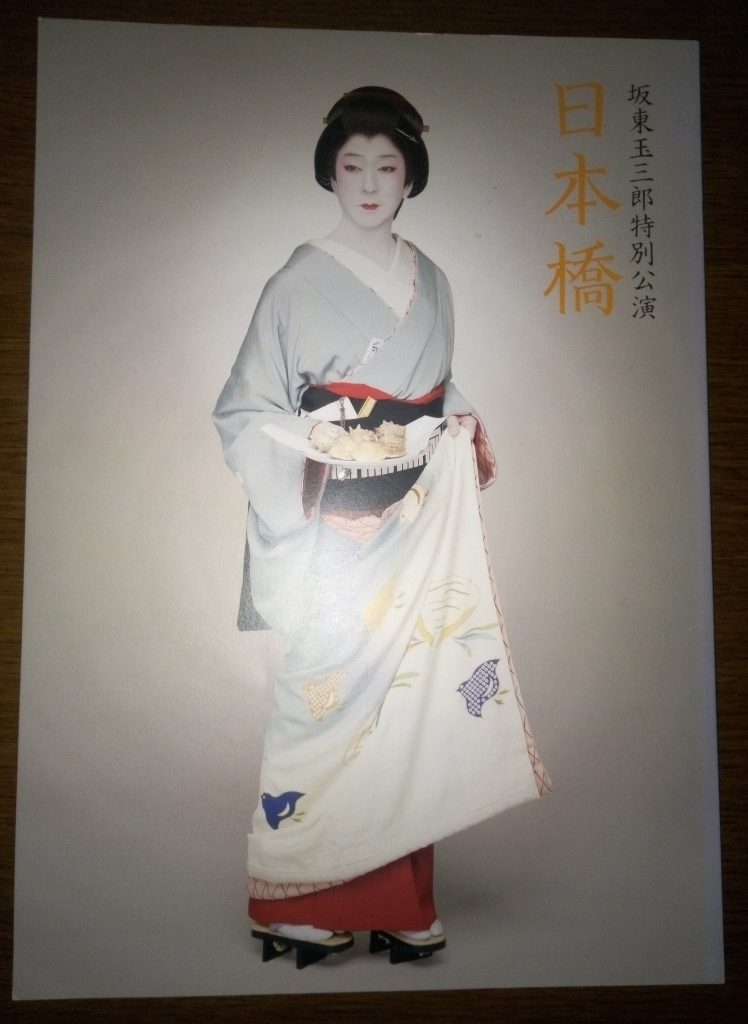新派は今年、125年を迎えるのだそうでその新春の演目が木下恵介監督の映画「お嬢さん乾杯」の舞台化である。木下監督は今年、生誕100年。映画「お嬢さん乾杯」は昭和24年(松竹)の作品で脚本が新藤兼人さん。新藤さんは昭和22年に映画「安城家の舞踏会」の脚本も書いていて、原節子さんがどちらも没落貴族の娘役であるが、「お嬢さん乾杯」はラブコメディである。「お嬢さん乾杯」で木下監督は原節子さんのあらゆる表情を映してくれた。その原さんに身分違いの朴訥で不器用な佐野周二さんが一目惚れをして楽しませてくれる喜劇である。
新派舞台は自動車修理工場で儲け人生はお金と思っている・圭三(市川月乃助)が、没落しかけている家のお嬢さん・泰子(瀬戸摩純)とお見合いをする。圭三は身分違いと思っているから断るつもりが一目惚れしてしまう。そこから圭三の喜びと悩みが始まる。この二人の生活環境は泰子は自分の家(池田邸)と家族。圭三は働く以外は入り浸るバー「スパロ」とそこに集う人々と弟。舞台はその二つの<池田家>と<スパロ>の場面を行き来することによって二人の置かれている環境の違いとそれぞれの場で大切にされ好かれている事がわかる。ところが繁栄していた池田家の人々は成金を受け入れる事には素直になれない部分がある。そのあたりの心理描写は新派の芸歴が物を言う。泰子の母(波乃久里子)を軸に元華族の人々を無理なく形づくり静かに主張し、圭三はその空気にドギマギする。しかし、お嬢さんの美しさと触れた事のないお嬢さんの持つ世界に驚きと喜びを感じる。そのゆれを月乃助さんは、ちょっと美男子すぎるが上手く表現した。
それに対する泰子は、圭三の世界に戸惑う。しかし馴染もうと努力する。素直な性格であるから次第に圭三の善良さが解かってくる。瀬戸摩純さんは頑な美人と思わせたお嬢さんの感情の変化を、自分を主張しつつじわじわと見せてゆく。そして飛び越すところが良い。手袋の上からのキス。さらに飛び越す術を「スパロ」のママ(水谷八重子)が教える。ママは圭三の暖かい仲間の中心でもある。
圭三は、人生はお金と思っているが女性を縛るためには使わない。その事が彼の戦争孤児を弟(井上恭太)として育て、弟の幸せを勝手に作っている自分に気づき結婚を許す。
圭三の<お嬢さん乾杯>は、お嬢さんの存在とその内面の世界なのである。
舞台美術も待たせる時間を短くし、<池田家>と<スパロ>を上手く移動させ、<場>ごとに二人の感情の起伏と変化を乗せていった。それぞれの<場>で、水谷八重子さんは明朗に圭三の聞き役として、波乃久里子さんは泰子の気持ちを確かめつつ複雑な感情の池田家のまとめ役として役どころを発揮した。新派のその時代の生活音や自然音を大事にする劇団の特色を今回は戦後間もない頃の歌謡曲の音響で時代を現す。<ピアノ>も重要な意味があり、実際に舞台にピアノが登場し、さらに泰子の瀬戸さんが実演したのは、この作品に大きな力と成った。映画では圭三がバレーの舞台を観て涙を流す良い場面があるが、それを出来ない舞台としての違う強さとなった。それが<スパロ>ではレコードとなる。繋がりもすっきりした。泰子がかつての婚約者の話をする時のギターの使い方も効果的である。舞台『お嬢さん乾杯』としてしっかり確立していた。
お嬢さんの家族/祖父(安井昌二)・祖母(青柳喜伊子)・姉(石原舞子)・姉の夫(児玉真二) 圭三の「スパロ」の仲間/川上彌生・鴫原桂・等 縁談を勧めた取引先の佐藤/田口守 [ 脚本・演出/成瀬芳一 ]
パンフレットに評論家の川本三郎さんが木下恵介映画について寄稿されていて、木下監督の実験的映画作りの一例として「カルメン純情す」では、カメラを斜めにし、「野菊の如き君なりき」では回想シーンを楕円型にトリミングしたとある。昨日、レンタル店で「野菊の如き君なりき」を手にしつつもどしたのが悔やまれる。川村さんの「銀幕の銀座」(中公新書)には『お嬢さん乾杯』も載っている。舞台では銀座とは限定していないが、新橋演舞場で花柳章太郎と初代水谷八重子の「鶴八鶴次郎」をやっている話題が出てくるので銀座なのかもしれない。
新派125年「初春新派公演」でもあり、艶やかに舞を取り入れた口上もある。