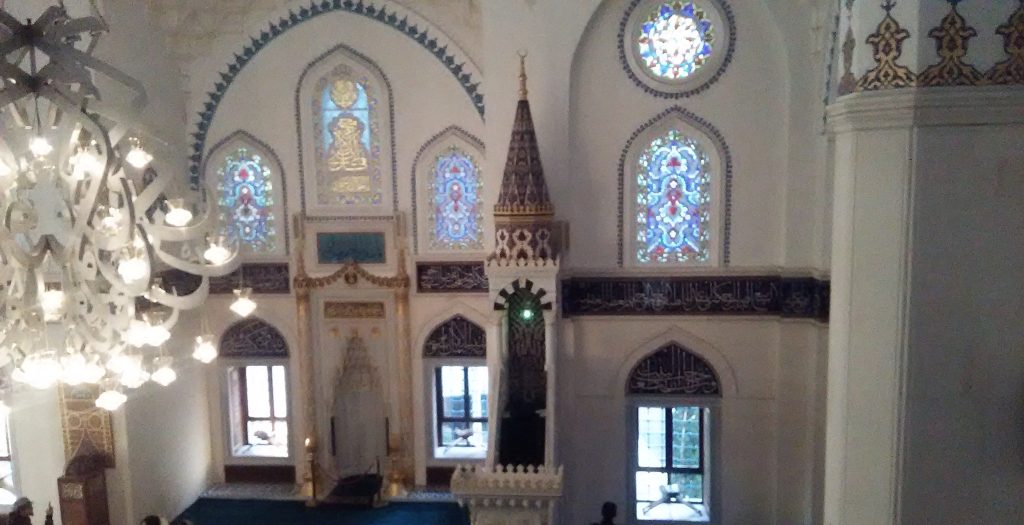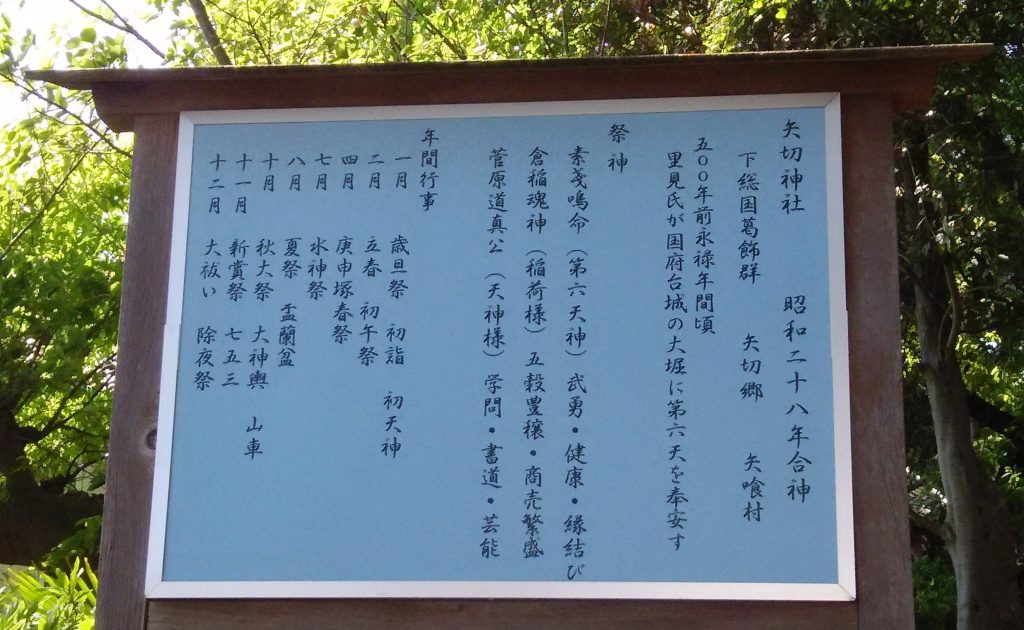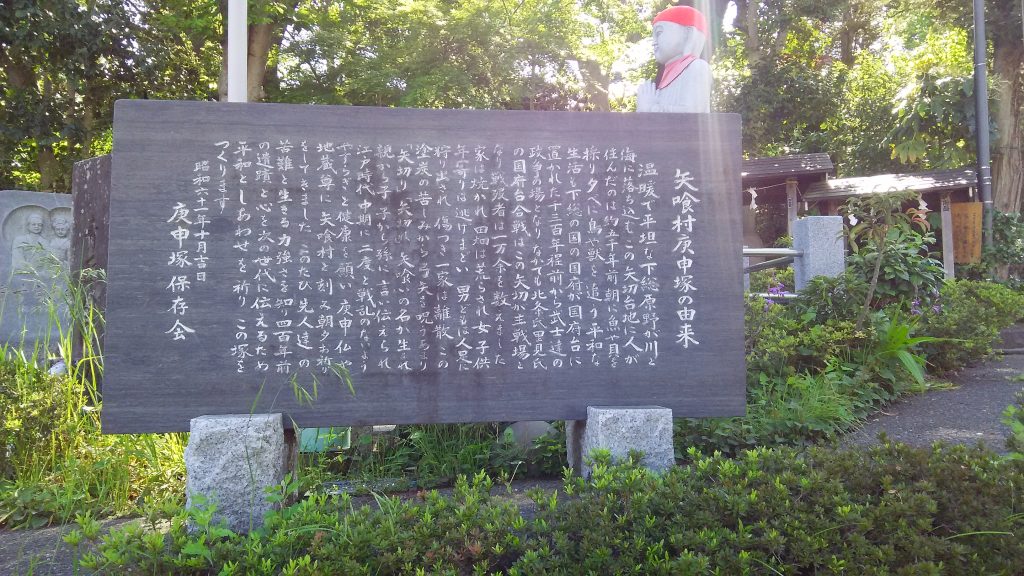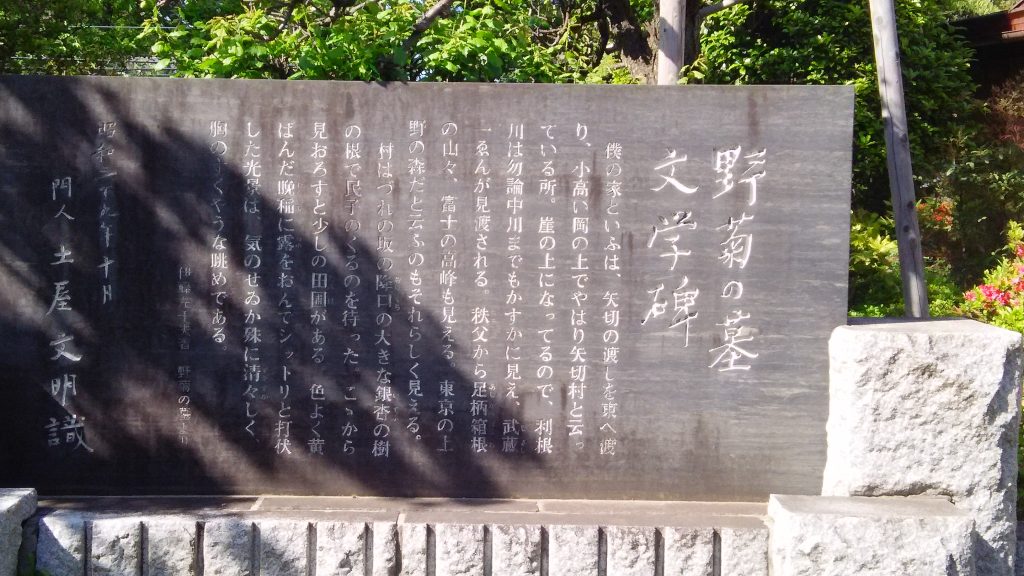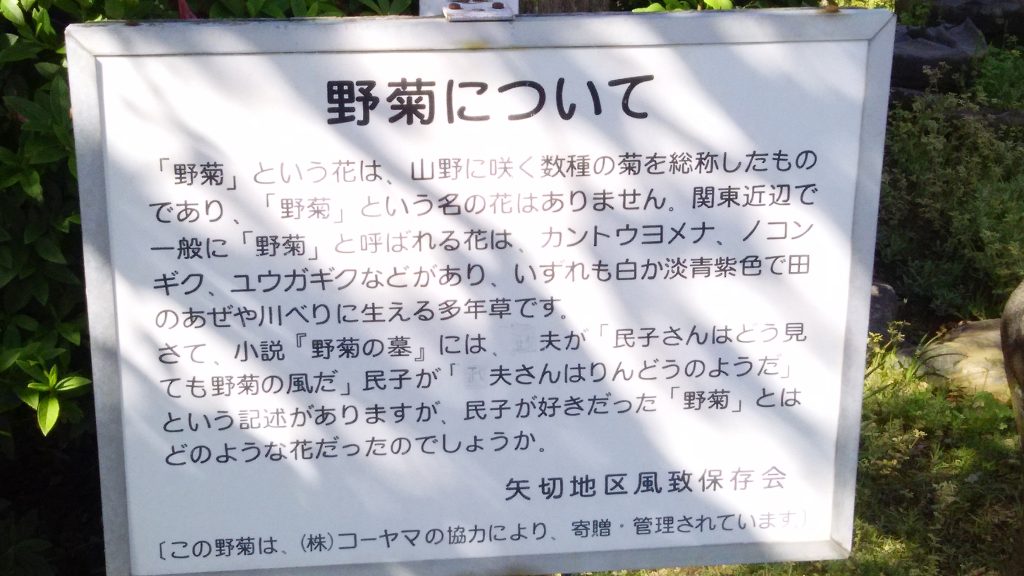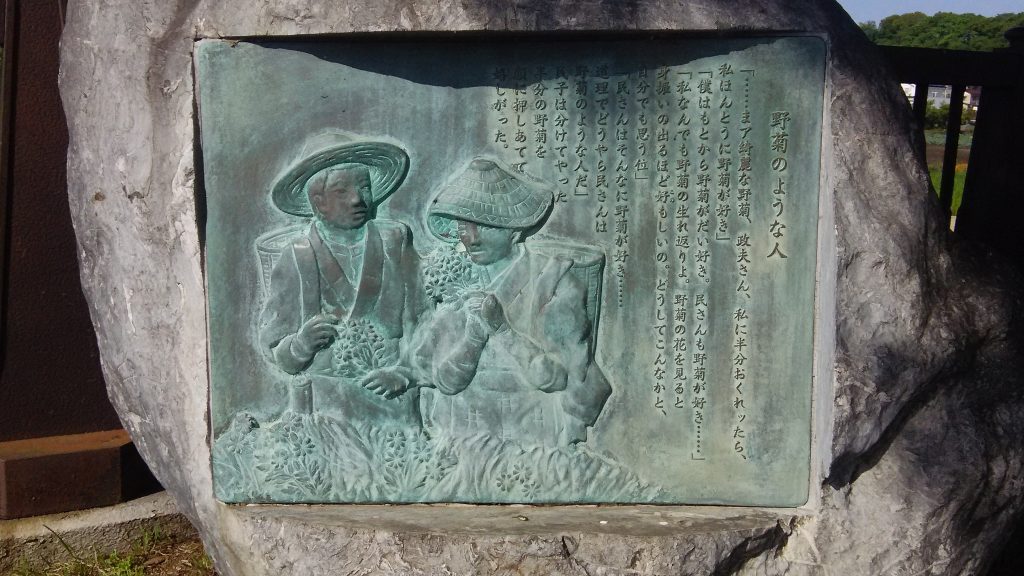映画『ビート・ストリート』と同年(1984年)に公開されたのが、映画『ブレイクダンス』、『ブレイクダンス2』である。この映画からブレイクダンスという言葉が拡散したといわれている。(原題は『BUREAKIN’』)
『ブレイクダンス』の場所はカリフォルニアのヴェニスビーチでストリートダンスのメッカということである。詳しくはわからないが他の場所でもストリートダンスが盛んな場所があり、それぞれに特色があるようだ。ブレイクダンスは体操競技、カンフー映画、ジェームス・ブラウンなどからも影響をうけ、様々な要素を取り込んでいき進化していく。
『ブレイクダンス』はケリー、オゾン、ターボの3人が主人公である。ケリーはジャズダンスサーを目指していてオーディションで表舞台に立ちたいと思っている。そのケリーがストリートダンスを踊るオゾンとターボに出会いブレイクダンスに魅かれそのダンスを取り入れていく。紆余曲折しつつケリーの提案で3人はミュージカルのオーディションに立ち向かい自分たちのダンスを認めさせるのである。
ターボの箒を使ってのダンスは多くのダンス場面でもイチ押しである。3人に敵対するクルー(チーム)の中に、マイケル・ジャクソンにムーンウォークを教えたというポッピン・タコも出演しているのを知る.
『ブレイクダンス2』は3人は同じメンバーで、その後ということになる。オゾンは子供から若者たちまでダンスなどを練習できる場所を見つけ、〔ミラクル〕と名付け活動する。建物は廃屋同然の公共の施設のため老朽化しており、資金がなく、民間が買い取りスパーにするという。皆の集まる場所が無くなるとオゾンとターボたちは反対する。ケリーはパリでの主役出演を蹴り二人を手伝い、資金集めのショーを成功させる。
この映画での見せ所の一つがターボの部屋の床、壁、天井での360度のダンス場面であるが、これはすでにフレッド・アステアが『恋愛準決勝戦』(1951年)で踊っているので驚かなかったが、ダンスの種類が違うのでその面白さはあった。振り付けの担当がマイケル・ジャクソンの「BEAT IT」の振り付け師、ビル・グッドソンということである。
『ブレイクダンス』『ブレイクダンス2』からマイケル・ジャクソンにつながったが、マイケル・ジャクソンのミュージカル映画『ムーンウォーカー』(1988年)はヒップホップ文化を意識してると思えるし、この映画から新たなB-BOYたちが生まれたことが想像できる。『ムーンウォーカー』では、「最高のワル」と自称する子供たちが自信たっぷりにストリートダンスを披露している。
B-BOYたちが口にする映画に『フラッシュダンス』(1983年)がある。この映画には、主人公が歩く前でブレイクダンスを踊り出すストリートダンサーが出てくるのである。映画を観た時、ブレイクダンスとは知らずになんという面白いパフォーマンスであろうか、こんな動きがあるのだと思った。
『ブレイクダンス2』では、自分たちのコミュニティーセンター〔ミラクル〕を守るが、もっと年齢が若い少年、少女が放課後に集まる児童館を守るためにダンスバトルショーを開催するという映画が『ストリート オールスターズ』(2013年)である。『 ストリートダンス TOP OF UK 』(2010年)、『ストリートダンス2』(2012年)の3作目で、3作の中で一番人気度は低いかもしれない。観始めたときはチルドレンものかとあなどった。
6人のメンバーがダンスチームを組むのであるが、言い出す少年が好きになった少女に恰好をつけて自分のダンスメンバーは凄いと出まかせを言い、急遽メンバーを集めるのである。言い出しっぺがダンスが駄目で、一人だけブレイクダンスが上手な少年、格闘技の少女、社交ダンスの姉弟、音楽がなんとかなる少年の6人なのである。期待できない6人が児童館のためにバトルダンスショーを成功させるのである。その6人の始めと最後の落差が見どころである。
印象的な場面があって、ダンスが得意な少年は、親の教育方針でダンス禁止で、優秀な学校への試験を受けるのである。その試験の最中、少年は違う世界に入り込んでいく。そこで、白い紙で作られた甲冑の武士とダンスで戦うのである。笛と尺八が流れなかなか素敵なシーンである。このシーンが映画を観る者を現実の世界につながり愉しませてくれた。
一つは、迎賓館赤坂離宮の正面屋根の左右に甲冑がのっているのである。この洋館の上で、武士の心が守るぜという感じで、歌舞伎の『暫』の衣裳のように左右に広がりをもたせている像である。映画をみたあとだったので遊び心のユーモアさが感じられ、その感性に違和感なく気にいってしまった。
もう一つは、スーパー歌舞伎Ⅱ「新版 オグリ」である。地獄の鬼兵士たちの衣裳と重なったのである。この鬼兵士たち踊るのである。照明にかなり助けられていたが。
追記: パリオリンピックでブレイクダンスも広く知られるようになりました。さらに中国映画『熱烈』が想像以上の面白さでした。ダンスシーンたっぷりでストーリーも笑わせて泣かせて観客を引き込んでいきます。驚きでした。
<気ままに「新版オグリ」> → 2020年1月21日 | 悠草庵の手習 (suocean.com)