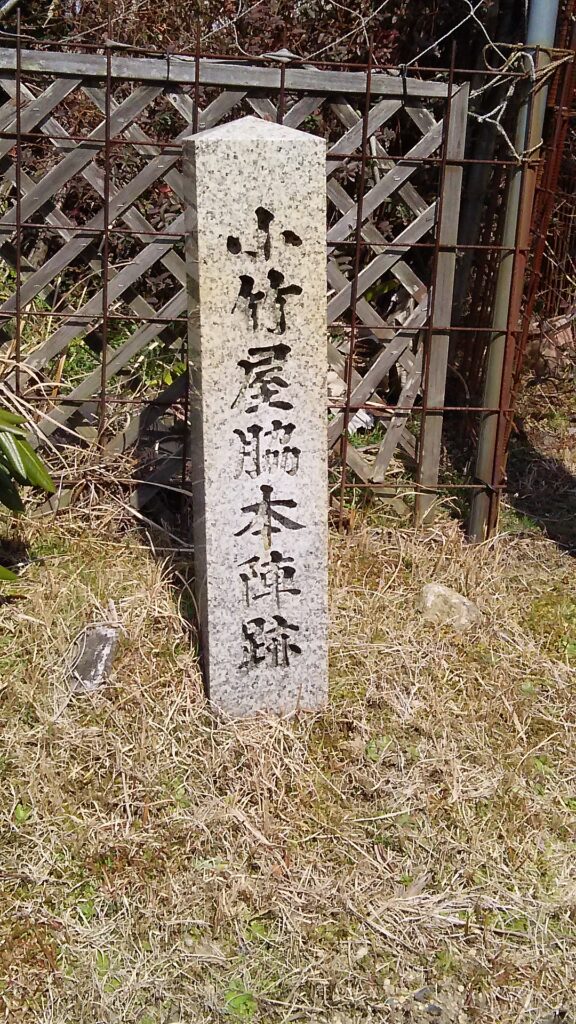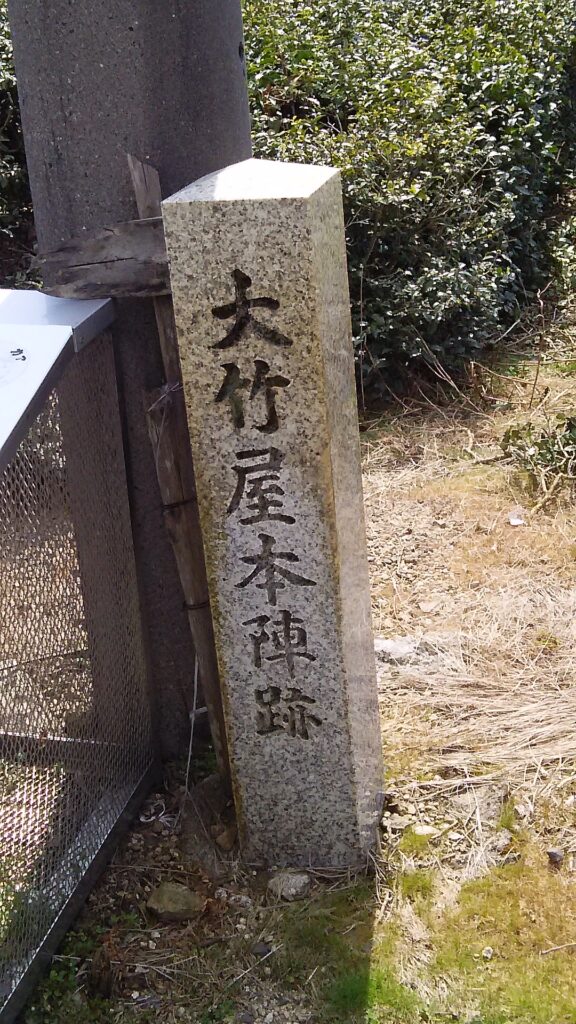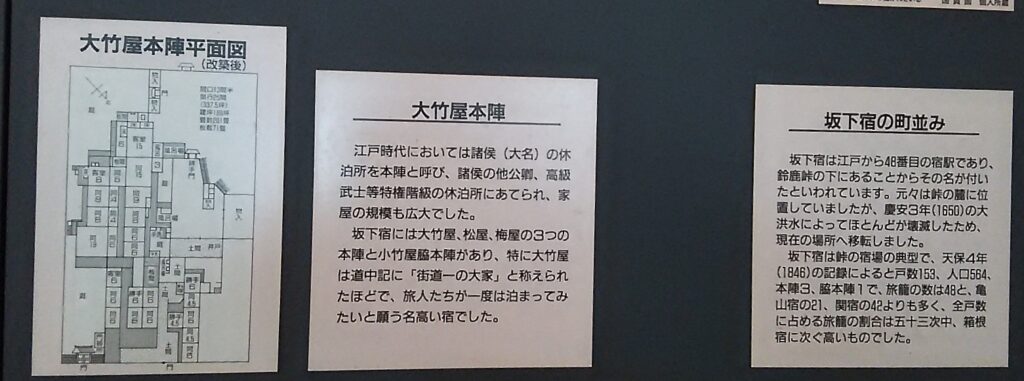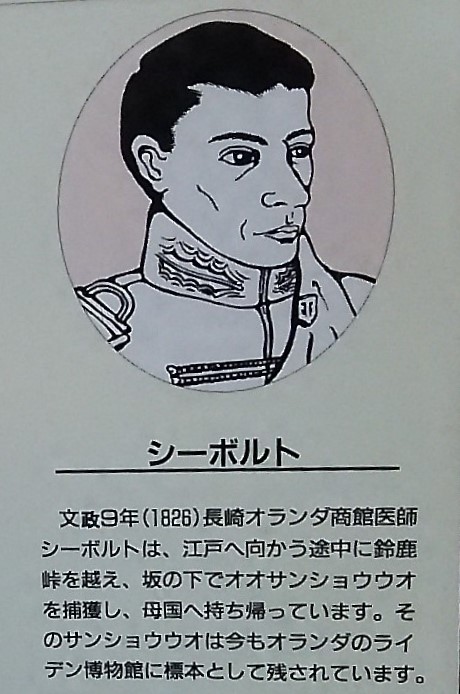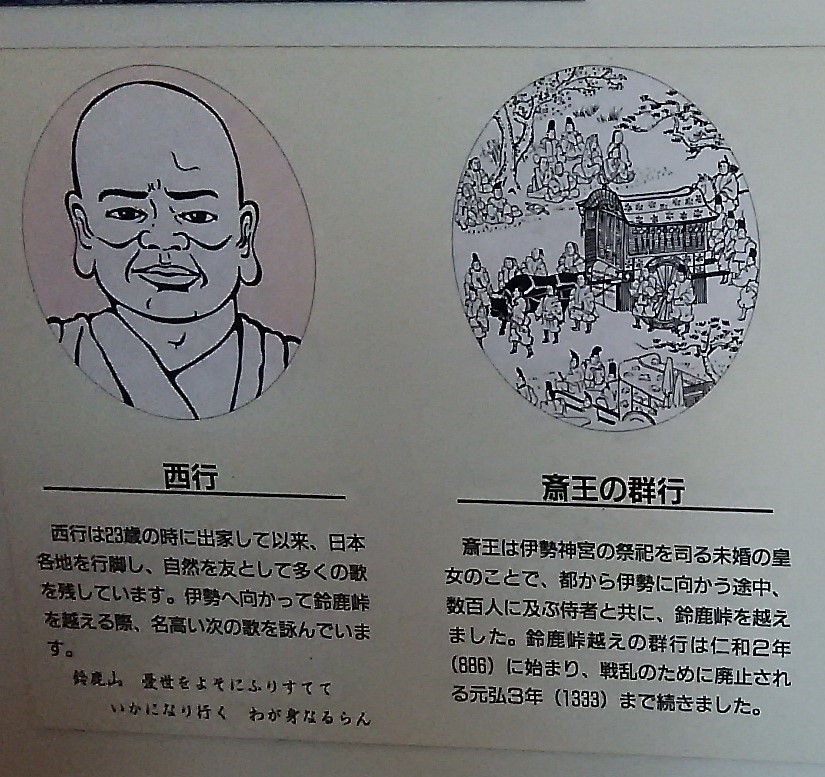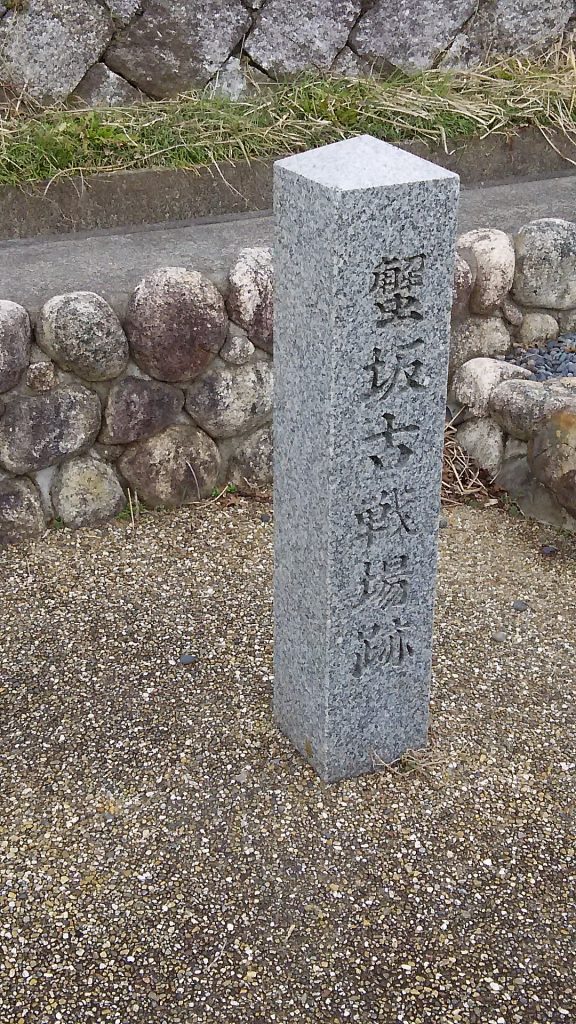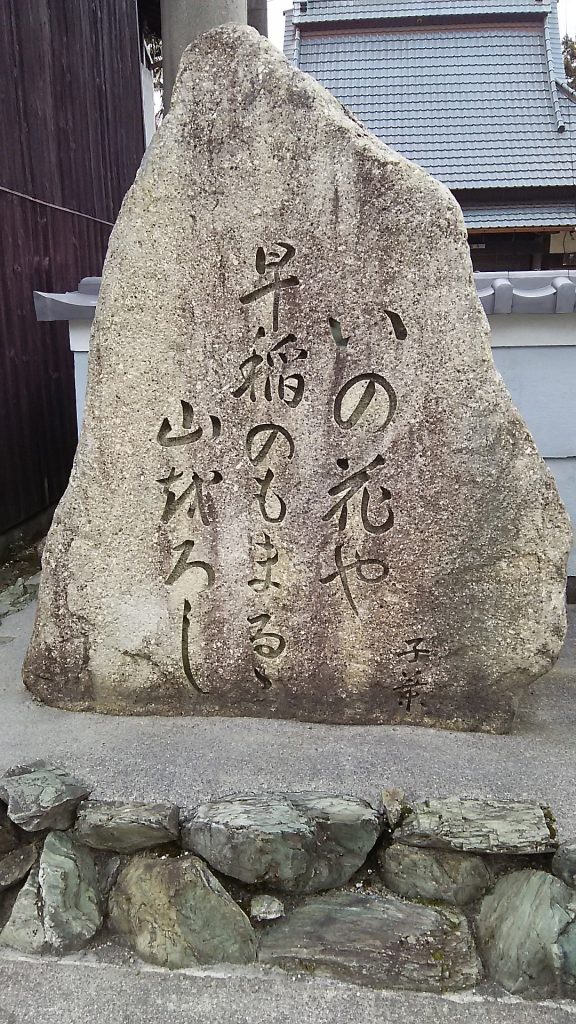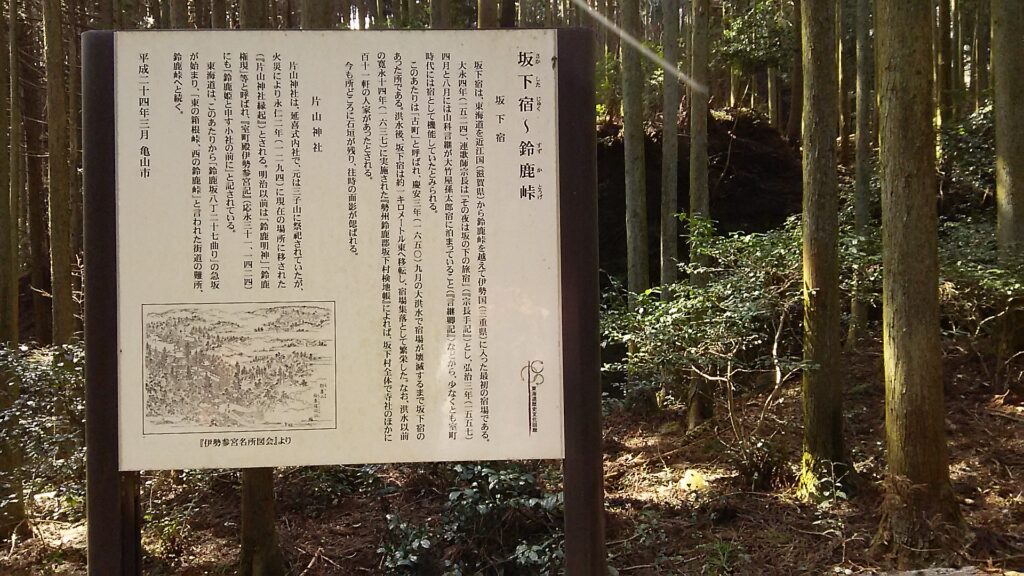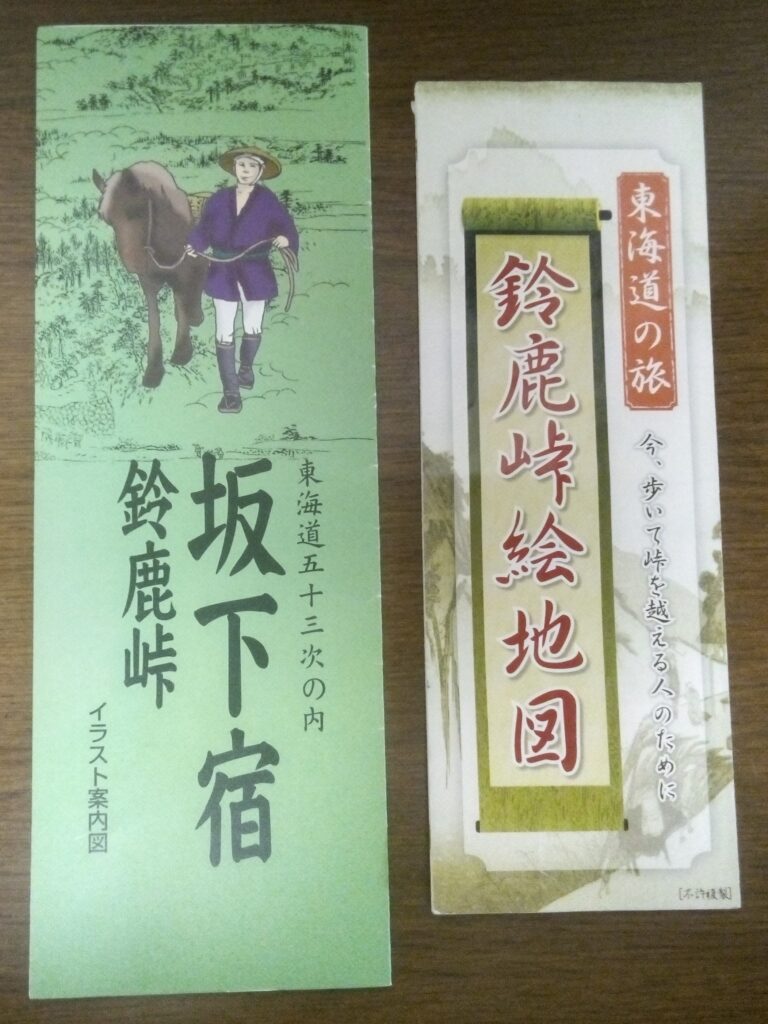『明君行状記(めいくんぎょうじょうき)』は、真山青果さんの作で、とらえどころがつかめなかったのです。名君といわれた岡山の城主池田光政の側に永く仕えている青地善左衛門が死罪にもあたる失態をしでかし、主君の本心が知りたいと裁きを待つのです。
光政の梅玉さんと善左衛門の亀三郎さんの弁舌さわやかなやりとりがお見事で、聞かせてくれるのです。結果的に、光政の機知が勝ちそれに対し善左衛門が感服して終わるというかたちなんですが、善左衛門が頑張っていたのは何なのか。
善左衛門は光政の本心が聞きたいのだと言うのです。光政は善左衛門の命を助けたいのが本心という建前を守ったのか。善左衛門は、法を破ってまで自分の命を守ってくれたことを本心としたのか。
光政からすれば、善左衛門の法に従う裁きをといって迫る善左衛門の考えに対して、そういう迫り方には応じられないという主君としてのプライドということなのであろうか。名君であろうとなかろうと、君主という者に本心というものなどないので、上手く治めるということだと言いたいのか。梅玉さんは、善左衛門の性格をよくしっていて、全くあいつはという大きさで情のある君主です。
善左衛門が主君の本心はなんてところに固執したところに、このはなしのややこしさの原因があり、光政の名お裁きとなるのですが、その終わり方がすっきりしなかったのはなんだったのでしょう。光政と善左衛門のやりとりに面白さがあったゆえにもう少し工夫が欲しかったとおもいます。
裁決の場の広い部屋の舞台は、光政の威光の大きさがうかがえる場面となり圧巻でした。そして台詞もそれに負けていなかったのですが。じれったいです。
『渡海屋(とかいや)・大物浦(だいもつのうら)』は『義経千本桜』のなかでの話しで、知盛が碇(いかり)を身体に巻きつけて入水する<碇知盛(いかりとももり)>としてよく知られている演目です。
仁左衛門さんの碇知盛は初めて観ました。銀平の仁左衛門さんは海風を切るように颯爽と花道から現れ、知盛の亡霊としてはその知略さと威厳を保ち、戦さの立廻りでの知盛は悲壮感にみちていて、安徳帝が「恨むなよ」と幼くも自分の立場を理解するかのような言葉に、それこそ亡霊となってでもこの方をお守りしたいという最後の力を振り絞っての入水となりました。
船問屋渡海屋の主人である銀平が兄から詮議をかけられている義経を客として泊めているのですが、鎌倉側からの詮索の侍が来た時、義経に聴こえるように義経など知らぬ、ただ客をまもるのだといって自分を義経に信用させます。ここがはっきりしていました。
銀平の女房・お柳の時蔵さんも、自分の夫の天候の変化の読みの確かさを義経(梅玉)一行に伝え、信用させて送り出します。この世話から銀平は白装束の知盛となり、お柳は安徳帝の乳人・典侍の局(すけのつぼね)に、娘・お安(市川右近)は安徳帝という本来の姿となります。
安徳帝を支え海を見つめる時蔵さんの典侍の局の十二単の後ろ姿に涼やかな気品があり、その後平家側の破れていく状況を受けつつ安徳帝を諭すところも品位を崩しません。右近さんの安徳帝も最後までしっかりとそれぞれに目線をむけ幼いながらも優位を保ちます。
知盛が血だらけになり、突き刺さった矢を抜きその矢に付着した血を口に含んだのには驚きました。このしどころは初めてみました。それが一層悲惨さをかもしだし、これでもかという戦いぶりで、勇壮というよりも、戦さの虚しさと悲しさが伝わってきました。
知盛の最後を見届けた義経一行、どこかはかなさを残して真っ直ぐ花道をさります。弁慶(彌十郎)が一人ほら貝を吹き後を追います。
『どんつく』の本題は『神楽諷雲井曲毬(かぐらうたくもいのきょくまり)』で、江戸の町の風俗を取り込んだ踊りです。十代目坂東三津五郎さんの三回忌追善狂言で子息の巳之助さんが、動きがにぶいドンな役どころのどんつくをつとめます。このどんつく太神楽の親方鶴太夫(松緑)、の荷持ちで田舎者です。太夫とどんつくが亀戸天神で踊っているのを見物しているのが、大工(菊五郎)、門札者(彦三郎)、芸者(時蔵)、田舎侍(團蔵)、太鼓持(彌十郎、秀調)、太鼓打(亀寿)、町娘(新悟)、子守(尾上右近)、若旦那(海老蔵)で、そこへ白酒売(魁春)が花道からあらわれます。
それぞれが、それぞれの持ち味で踊りを披露し、ときにはどんつくの指導で田舎踊りの総踊りとなり、その調子がどんどん早くなったりしてにぎやかな舞台となります。
どんつくドンドンと太鼓を叩いたり、太夫が籠毬をもっての踊り、どんつくがおかめの面をつけての踊りなど、亀戸天神の太鼓橋と満開の藤の花を背景に、皆さんに見守られての元気で愛嬌のある若いどんつくの追善狂言となりました。