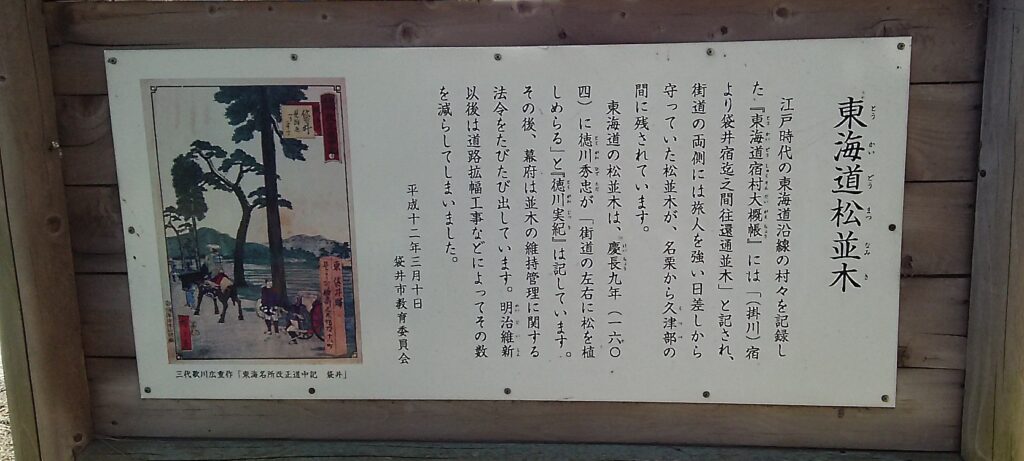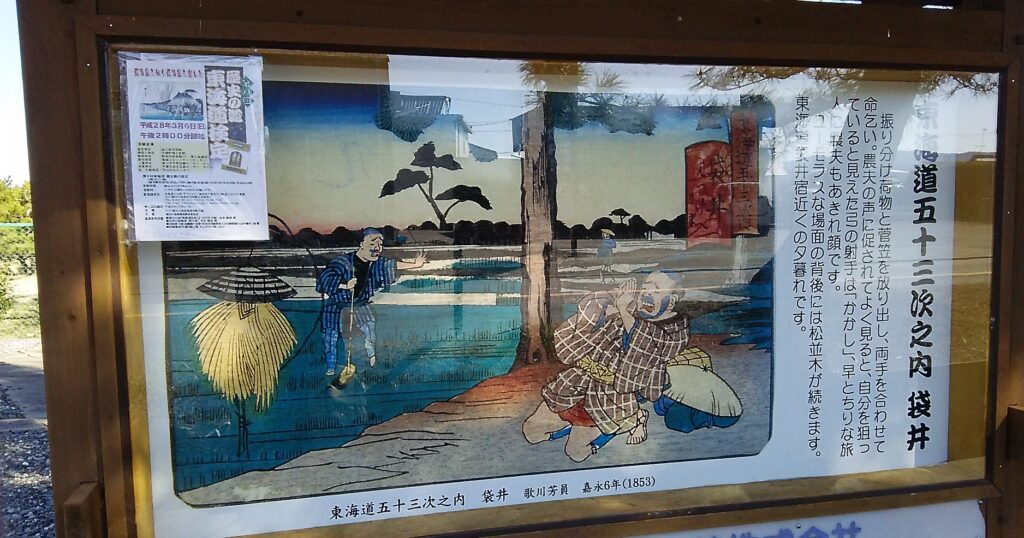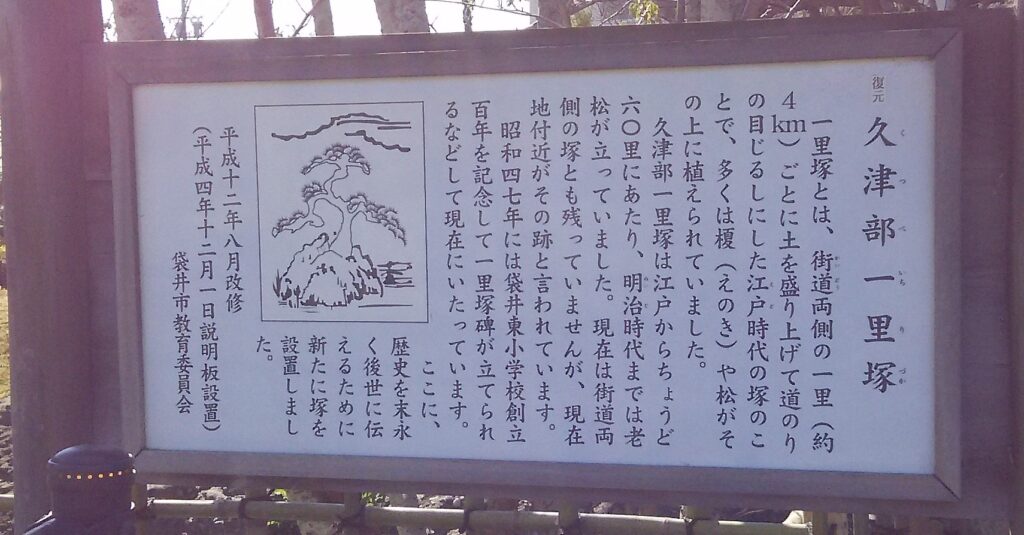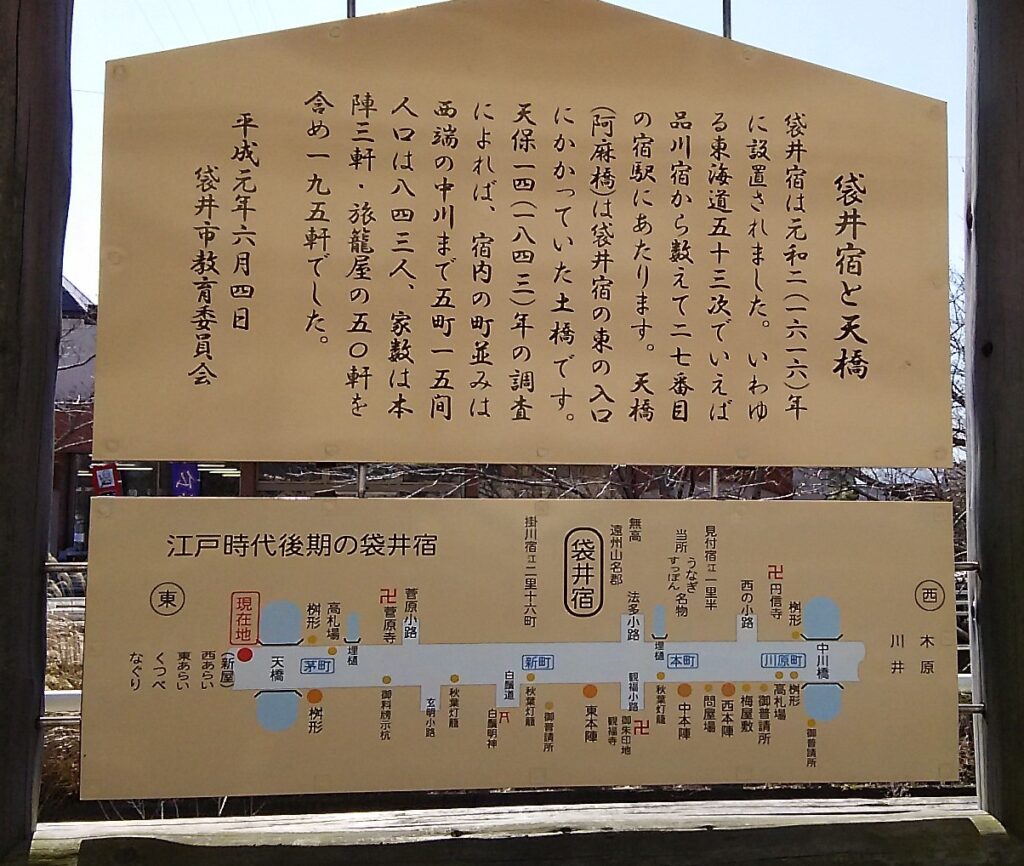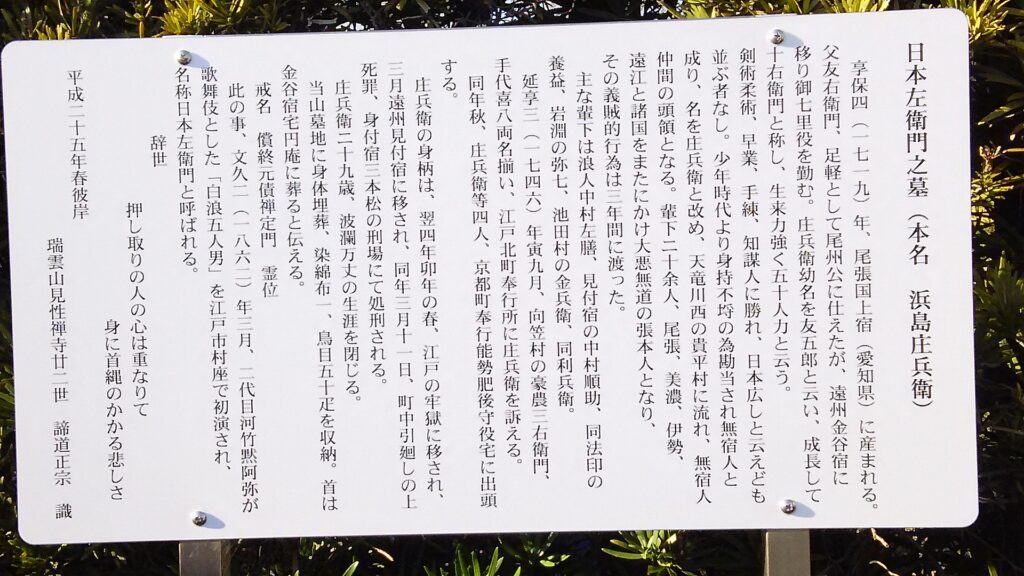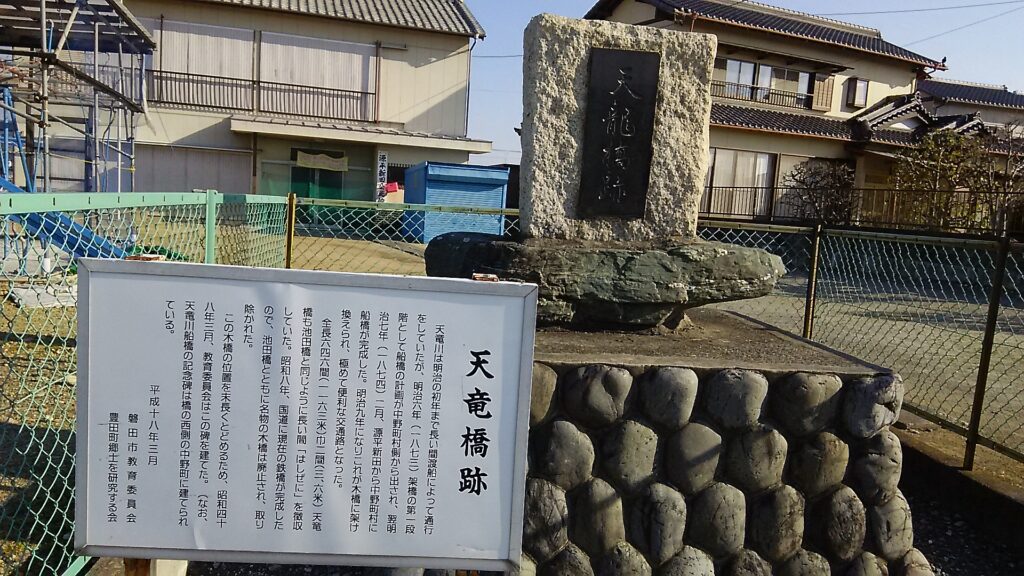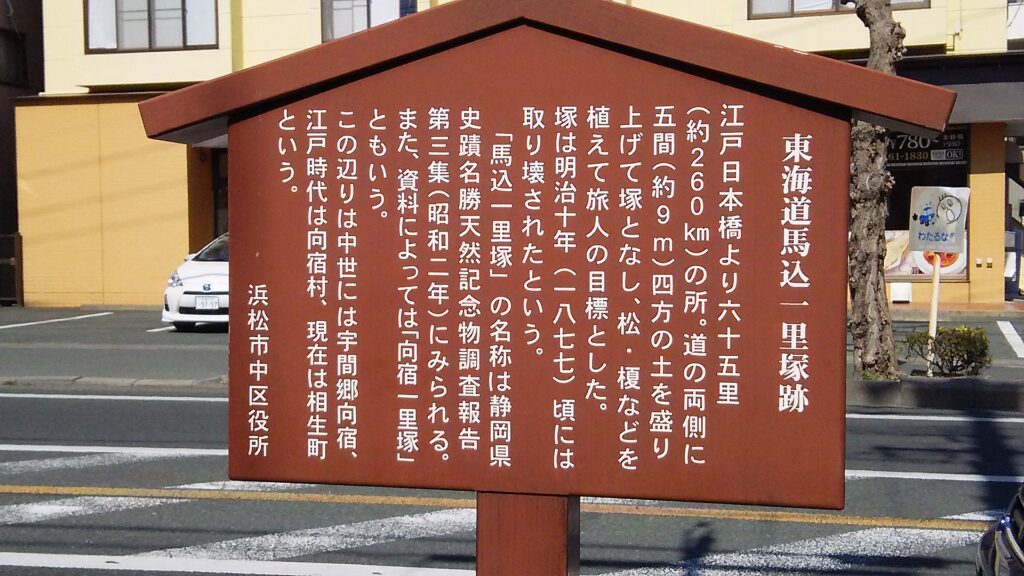函館の旅のあと追いをしている。映画、歴史、文学などであるが、同時進行で、さらに寄り道もあり無法状態である。
函館が出てくる映画が、25、6本あって、20本は見たのである。旧作レンタル10本で14日間の貸し出しサービス期間がかさなり、これが強い味方であった。さらに、見たいとおもっていた映画もレンタルする。
その一本が、阿久悠さんの「瀬戸内三部作」の一本であり、篠田正浩監督の「少年三部作」の一本である『瀬戸内ムーンライト・セレナーデ』である。それぞれの三部作に共通する作品として『瀬戸内少年野球団』があるが、個人的内は『瀬戸内ムーンライト・セレナーデ』のほうが好きである。
それよりも良いと思うのが、『少年時代』である。こちらは、東京から富山に疎開した少年と地元の少年たちとの交流を描いているが、少年の世界も美しいことばかりではなく、力関係があり、そのなかでどう生きて行くかが問われる作品である。その人間関係が大人社会とも類似しているのである。ただ過ぎてみれば少年時代は、甘酸っぱい涙とともに短時間で終わるということである。
『瀬戸内ムーンライト・セレナーデ』は、主人公が、阪神大震災のニュースを見つつ、「神戸が燃えている」状態から戦争中、淡路島から空襲で焼ける神戸を見た少年時代にもどるのである。
少年の父親は厳格な警察官である。長男は17歳の時志願兵となり戦死してしまう。次男は父親に反発してぐれている。少年は三男で下に妹がいる。母は、父親に従順ではあるが思ったことを時には主張する。
この5人の家族が戦後の混乱する中、淡路島から父の故郷である九州の宮崎に、長男の遺骨をお墓に納めるための家族旅行をするのである。
神戸からフェリーに乗り九州に向かうのであるが、そのフェリー上での、様々な事情をかかえた人々との交流が、考え方を変えない父親を中心に少年の前に繰り広げられる。
それぞれの過去を抱えつつ戦後を生きるために皆必死である。瀬戸内海には時として地雷が発見されたりもし、戦争が終わっても安全とは言えないのである。そうして中で甲板にしか居場所を作れなかった人々は、楽しくやりましょうと歌をうたったり、映画の弁士が阪妻の『無法松の一生』の映画を映してくれたりする。
雨で中止となると、少年の手の平に映画が映る。阪妻の『雄呂血』である。
弁士の活弁が見る者をひきつける。捕吏に囲まれ立ちまわりの場面。「平三郎はわれにかえりふっと気がついたとき、かれの眼に映じたのはまわりにある無数の屍であった。ああ!おれはついに人を斬った。ああ!おれはついに人殺しになった。」平三郎は慨嘆し刀を捨てとらえられるのであるが、その時の平三郎である阪妻さんの表情の絶望感が何とも言えない。痛快娯楽時代劇とはちがう人気をあつめたのが、この映画のなかの映像でわかった。
『無法松の一生』は、戦中は内務省か戦後は進駐軍から一部カットされ、『雄呂血』は進駐軍から禁止されたチャンバラ映画である。価値観の違いを上からのみ押し付けられる時代の流れである。
父と少年は、船を下りてから映画館で『カサブランカ』をみる。父は真剣に観ていながら少年にはアメリカ映画は嫌いだと言い放つ。
地震がなければ、この連休には瀬戸内海の別府航路を使って九州に入る観光客も大勢いたことであろう。いつの日か、この航路から大きな月を見たいものである。
この映画に、震災と戦争という映像が重なってどちらも残酷な現象であるが、戦争は人が起こす現象である。今回も不眠不休に近い状態の自衛隊の救助活動をみて、あの方達を人殺しとなるかもしれない場所に送り出していいのであろうか、やはりもっと時間をかけ冷静になって考えなければ。
そして、大きな災害を抱え込んでいるこの国は、若い人の力が必要である。非正規雇用という不安定な比率が増加しているような社会体制では土台も不安定である。そのあたりから考えて積み直しをしなければ、大切な減少している若い人の力を使い捨てにしてしまうことになりかねない。
映画のなかの家族の次男は、父親に反発しながら自分の生き方を探し、それでいながら父との約束を守る青年でもあった。
長男の遺骨の入っている骨壺に入っていたのは・・・・
震災の神戸港を歩くかつての少年は、今の人々と過去の人々から何かを受け取ったようである。
阿久悠さんの「瀬戸内三部作」(『瀬戸内少年野球団』『瀬戸内少年野団・青春篇/最後の楽園』『瀬戸内ムーンライト・セレナーデ』)
篠田正浩監督の「少年三部作」(『瀬戸内少年野球団』『少年時代』『瀬戸内ムーンライト・セレナーデ』)
監督・篠田正浩/原作・阿久悠(『飢餓旅行』)/脚本・成瀬行雄/撮影・鈴木達夫
出演・長塚京三、岩下志麻、笠原秀幸、鳥羽潤、吉川ひなの、羽田美智子、高田純次、火野正平、河原崎長一郎、麿赤児、余貴美子、フランキー堺、西村雅彦、竹中直人