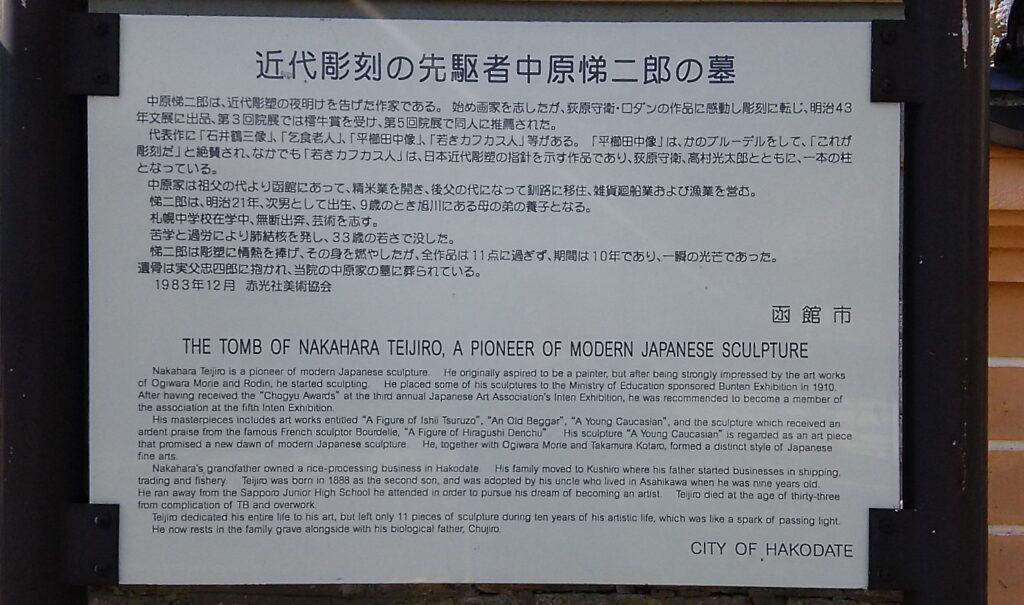小吉さん、あちこちうろうろして、やっと江戸に帰ることにする.
山の中で崖より落ちて大事なところを打ってしまいながら箱根に向かう。関所のことは出てこないが箱根から、三枚橋へ着いているから手形を持っていたのでろうか。書かれていない部分が気になる。小田原では漁師の家で漁師の仕事を手伝い息子にと請われるが、こんなことをしていてもつまらないとお金をちょっと拝借し江戸に入る。ところが鈴が森、高輪、愛宕山、両国橋、回向院の墓場と家の敷居が高く何日か帰る時間を伸ばしやっと家の敷居をまたぐ。四カ月ぶりの帰宅である。
21歳の時の出奔は、吉原に寄ってからである。剣術修行もしたが他の修行もしていたわけである。やはり、一泊目は藤沢である。昔の人は朝の出立が早い。朝4時である。先日、藤枝から途中までバスなので、朝一番のバスで初めて朝6時出立としたら予定より早く目的地に到着したので、早朝出立は検討の余地ありである。
さて、小吉さんは小田原で世話になった漁師の家により、盗んだお金も返し、三枚橋まで送られている。仲間にお酒もご馳走し、きっとにぎやかにあの道を歩いたのだろうと想像する。手形がないので、剣術の道具一式と雪踏(せった)のいで立ちで、剣術修行だからお通し下されと言って通してもらう。夜である。そこから三島に行く。真っ暗でなんぎしたとあるが、もっともな話である。三島宿に着いたのが夜中の12時である。
三島宿では、ひとり旅は泊められないという。問屋場(とんやば)に交渉する。ここは宿の事務手続きをするところである。そこでも断られるので、水戸のはりまの守の家来とうそをつき、脇本陣にとまる。旧東海道を歩くときは、宿場に入るとこの問屋場跡、本陣跡、脇本陣跡などを探すのである。小吉さんのお陰で流れが分るし、小吉さんもどうすれば人が動くかを学んでいて、堂々と嘘をついて押し出すのである。かごまで出してくれる。
14歳の時と大きく違うのは、剣術を身につけたことである。「なんぞあったら切り死に覚悟して出たからは、なにもこわいことはなかった。」
大井川である。96文川になっている。川の水位によって渡しの値段が違うのである。私が見た説明板では、一番深いのが人の脇のしたで94文、約2820円であった。96文川とは増水で渡れないということである。名前が功を奏し水戸のはりまの守の家来はきちんと渡っている。蓮台がついた渡しである。4人が担いだとして、前を4人水よけをしていて、荷物は別の人足が担いで運んでいる。川越人足は、12、3歳から先輩のお茶出しや食事の世話などの雑用をやり、15、6歳で荷物を運び、それから一人前に人を運べるようになる。14歳の時の小吉さんは、大井川のことは何も書かれていないが浅いときは、大人の股下くらいであるから自分の力で渡ったのかもしれない。
川止めの最高は28日ということである。川止めとなると、宿が幾つか前の宿場まで宿泊客で埋まり相部屋となる。そこを狙うゴマの蠅もいるわけで、旅人にとって川止めは大変である。大井川に架かる大井川大橋は渡る時間12分であった。
小吉さんそこから掛川宿に入っているが、私たちは掛川まで入れなかったのである。この前に<小夜の中山>があり、東海道の三難所の一つであった。七曲り坂は、日光のいろは坂の徒歩バージョンと名付けたが、小吉さん元気であれば、難所などありはしない。
掛川から遠州の森町の昔の知り合いのところで逗留していたが、甥が迎えに来て江戸へ帰ることとなる。遠州森は、実在したかどうかは判らないが森の石松さんの生まれ故郷である。そして小吉さんは江戸にて座敷の三畳の檻の中である。
これにて、小吉さんとの東海道の旅も終了である。
舟木一夫さんの芝居『気ままにてござ候』は、この後からの話となるのであろう。斎藤雅文さんの脚本である。
『夢酔独言』(勝小吉著・勝部真長編)のまえがきに、坂口安吾さんの『青春論』『堕落論』、大仏次郎さんの『天皇の世紀』に『夢酔独言』に触れているとする編者の一文も好奇心を誘う。