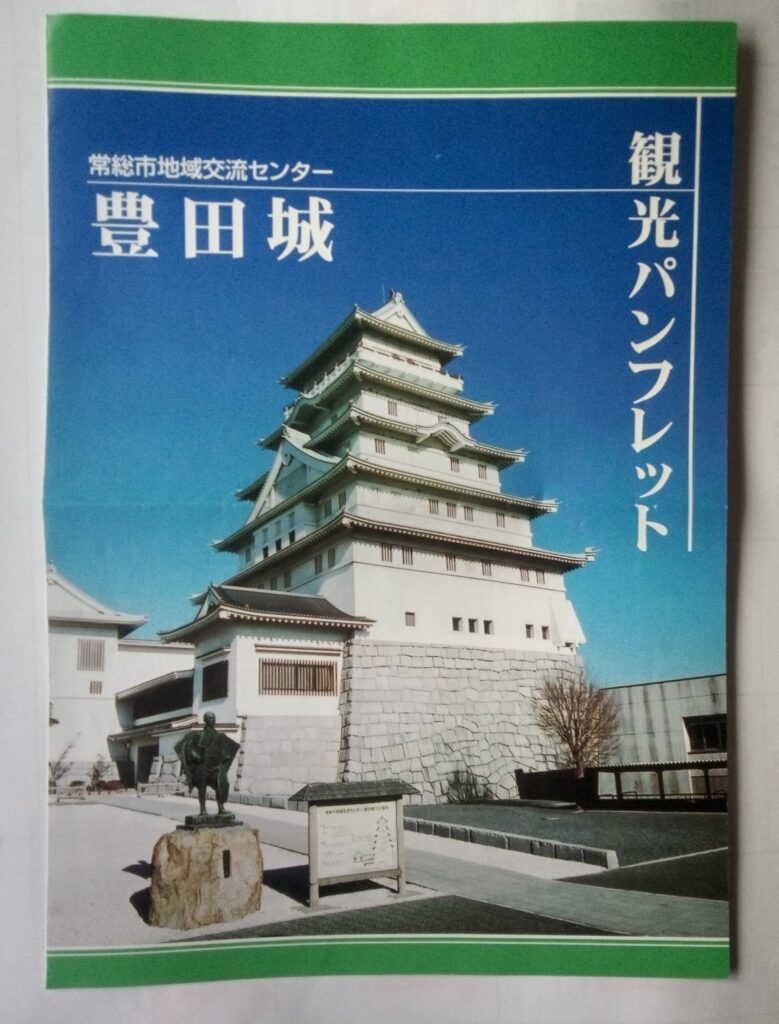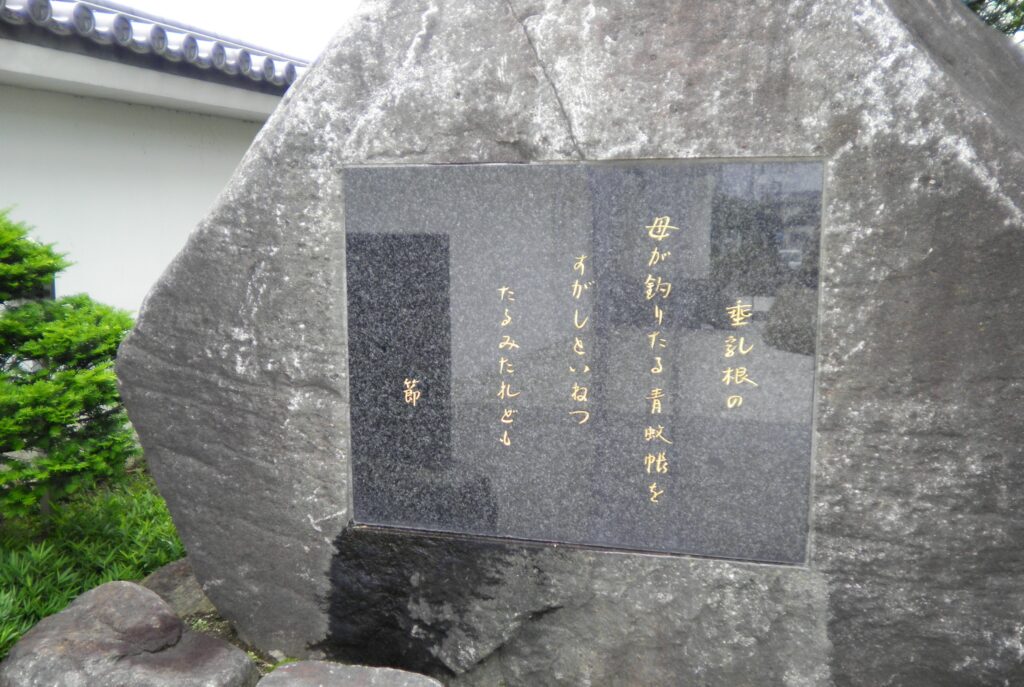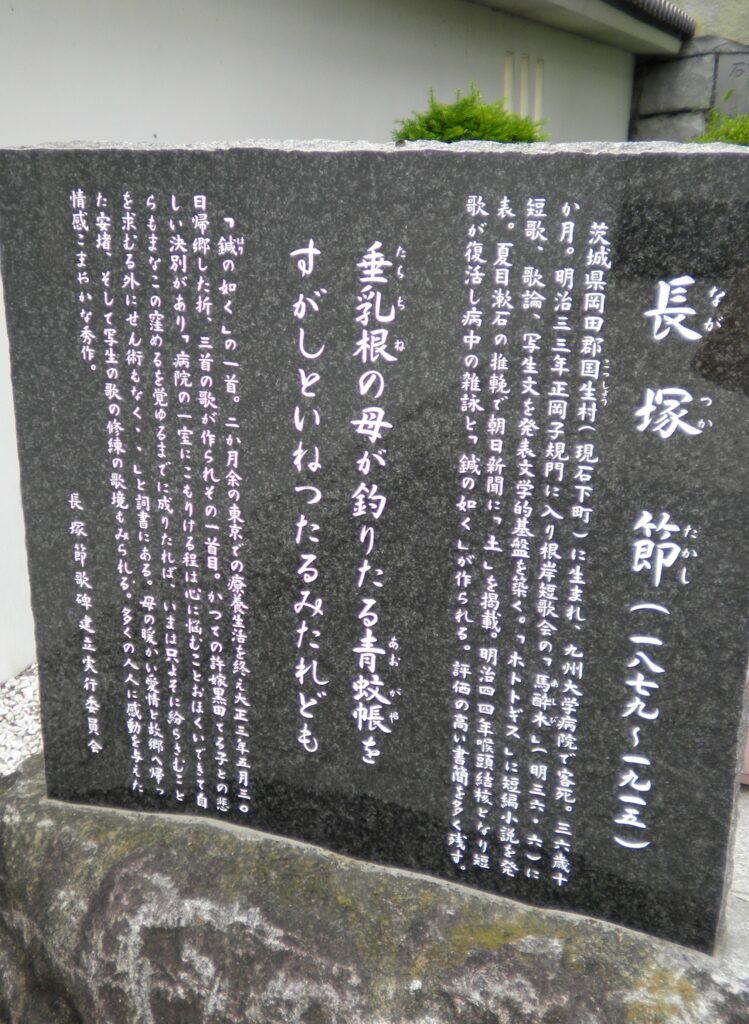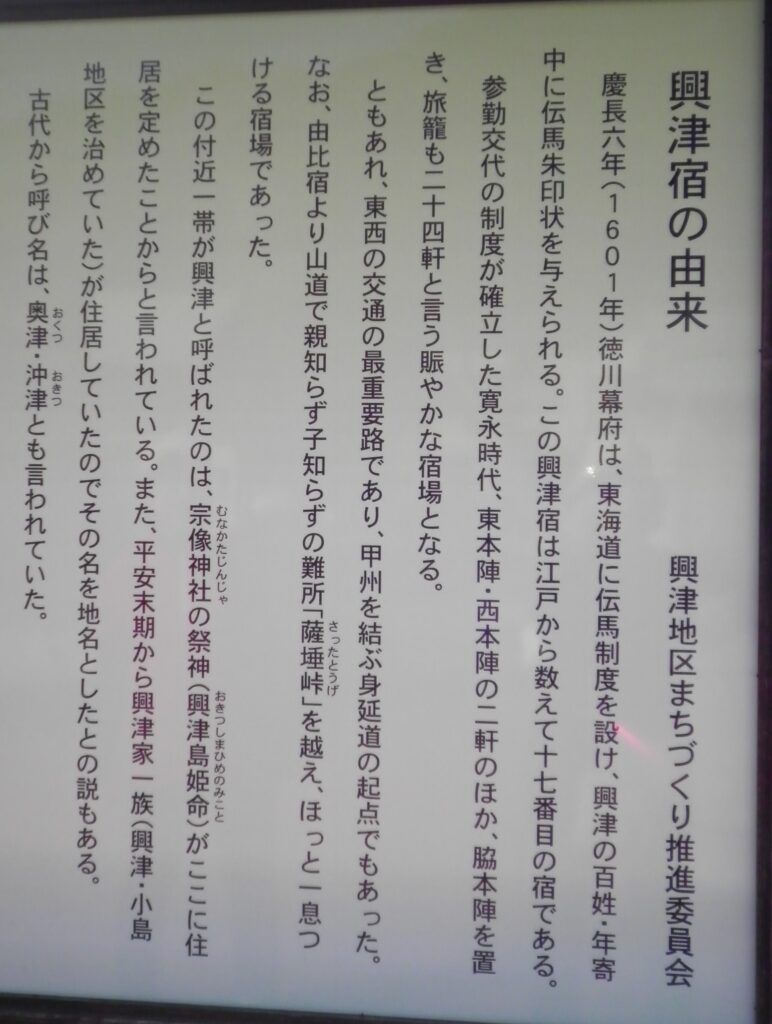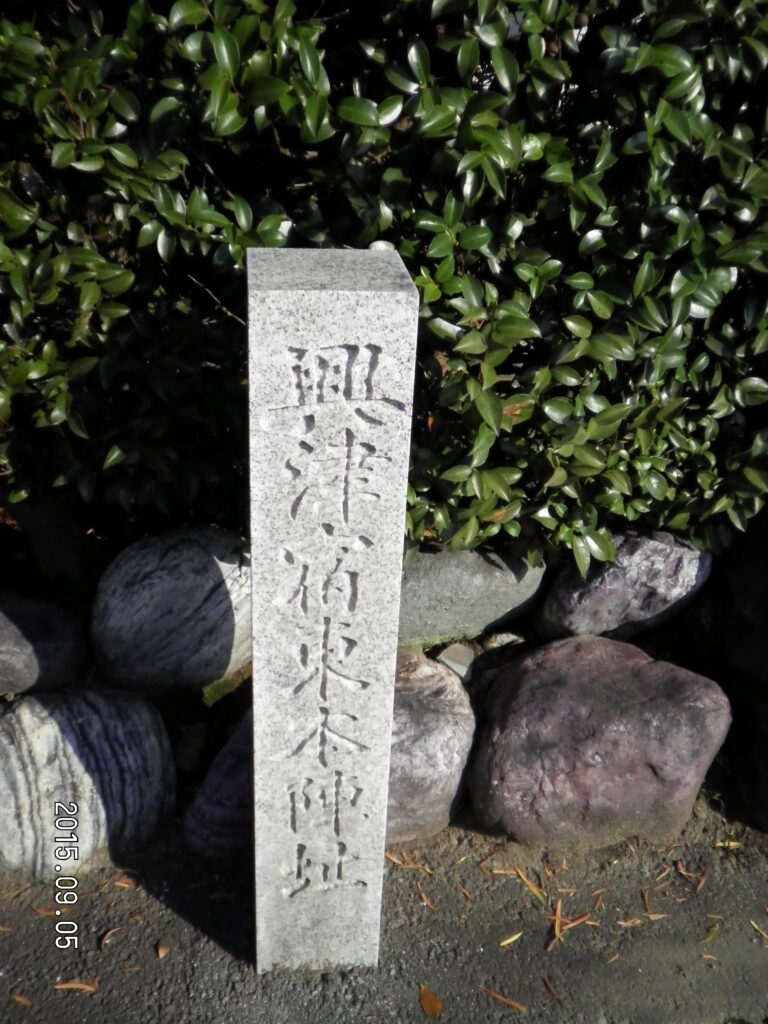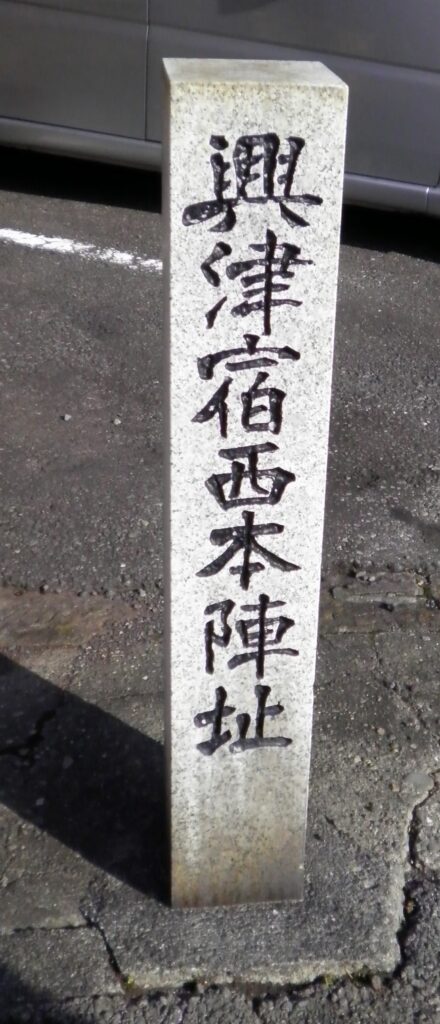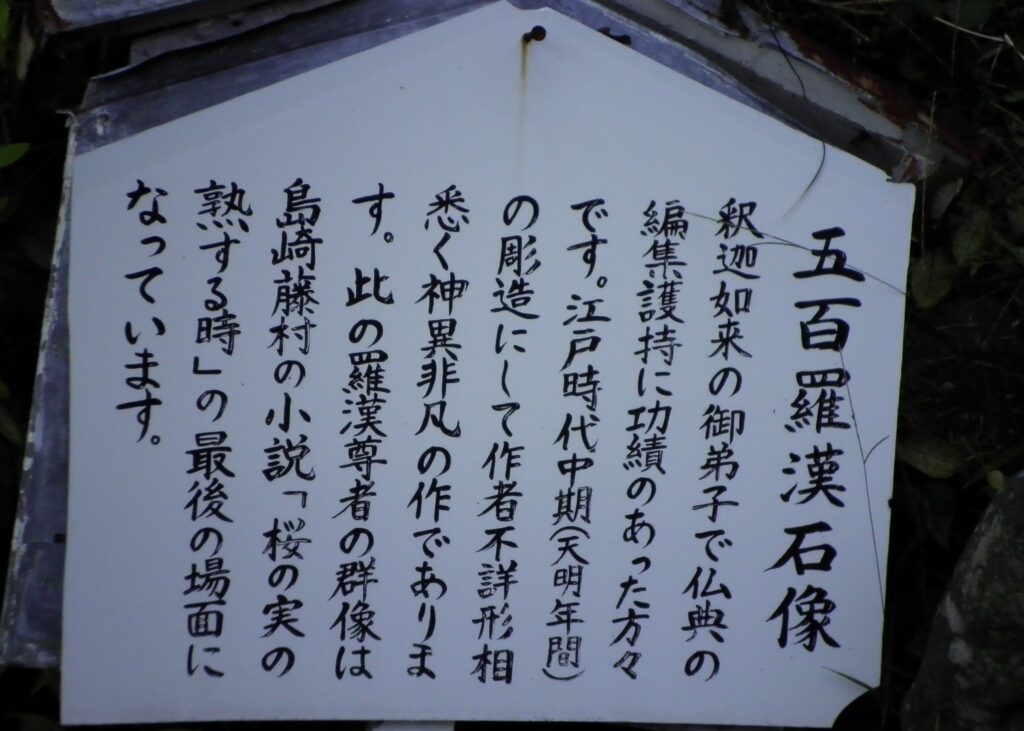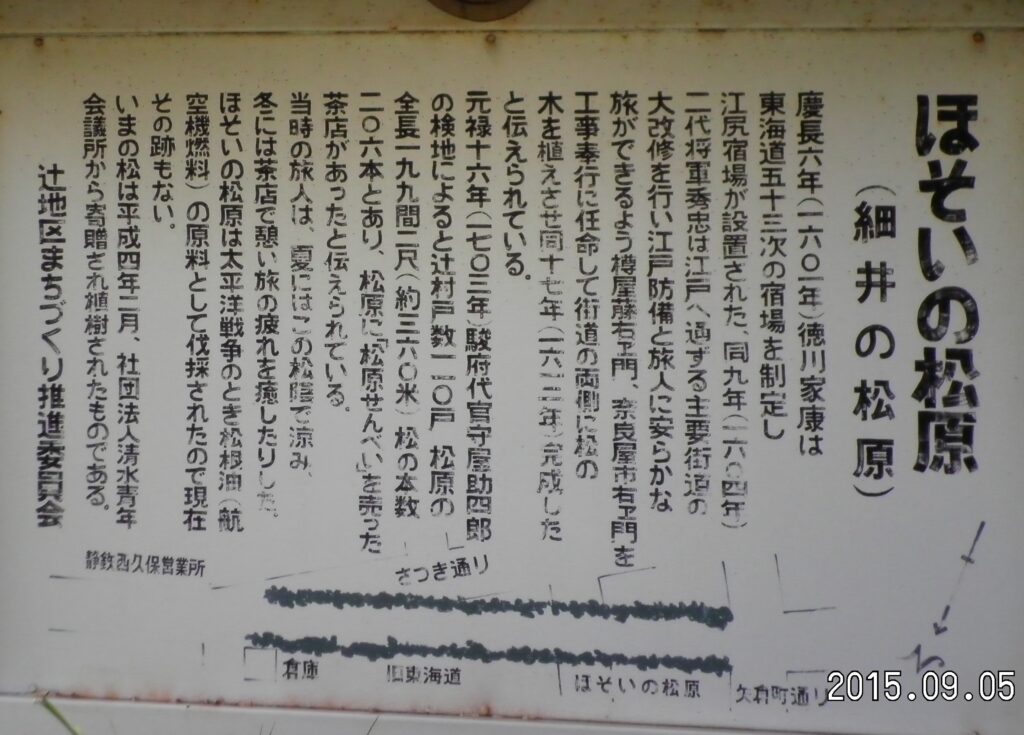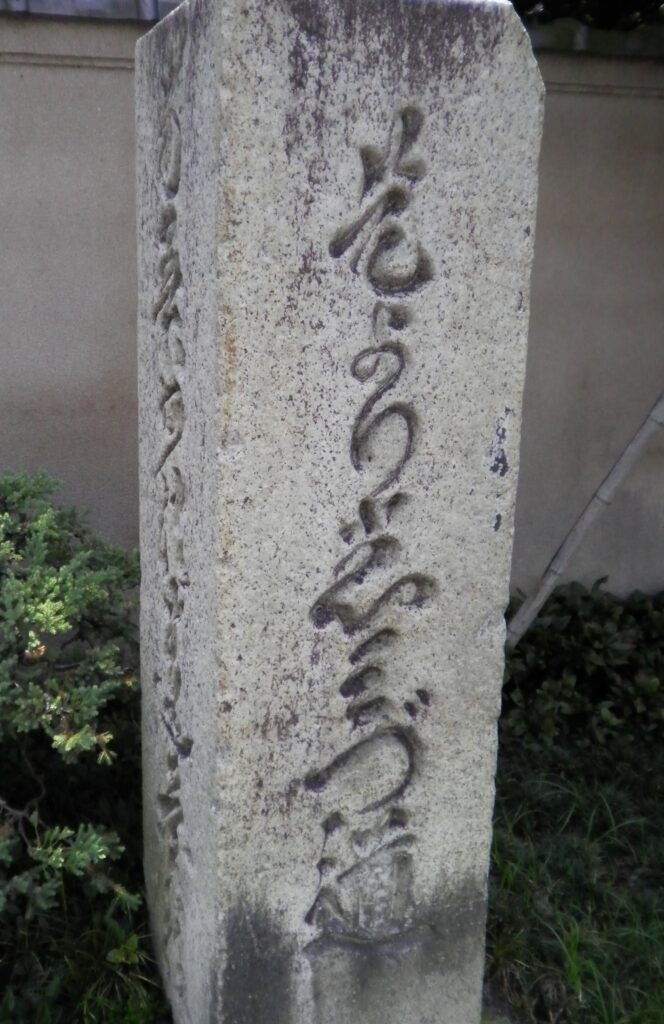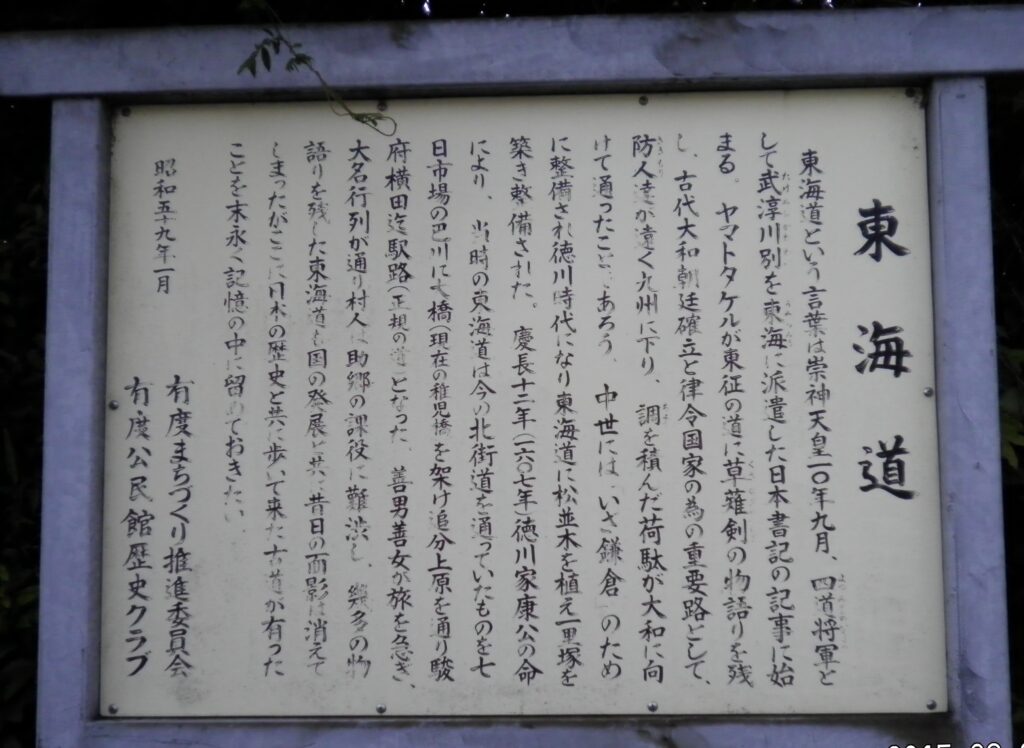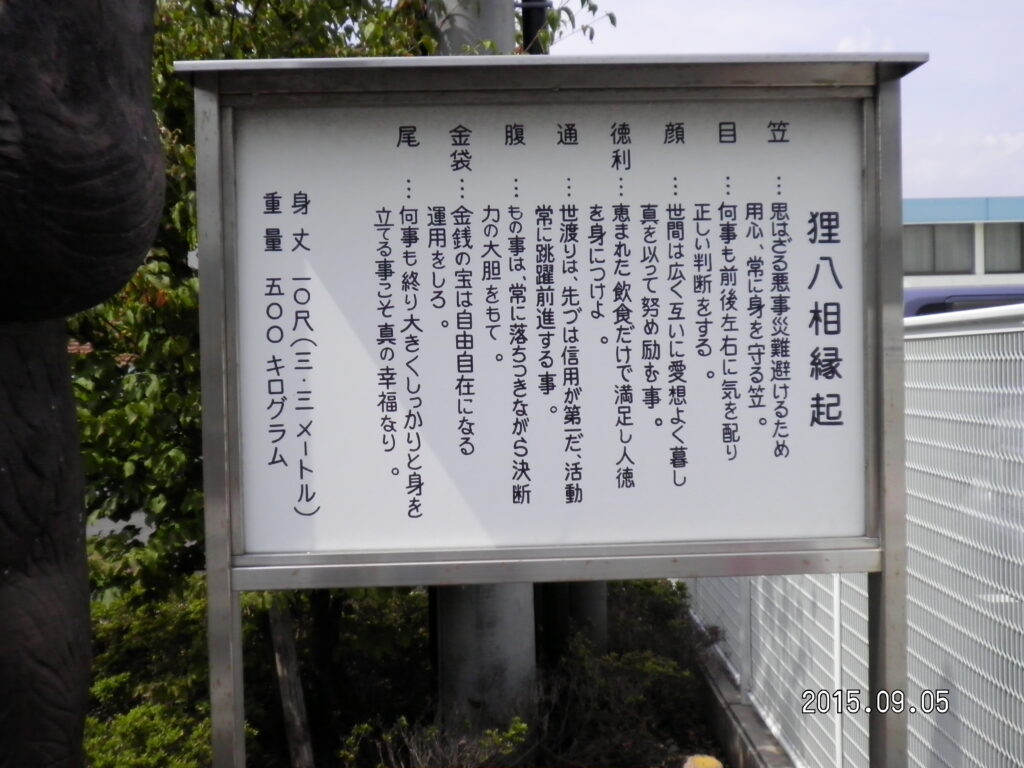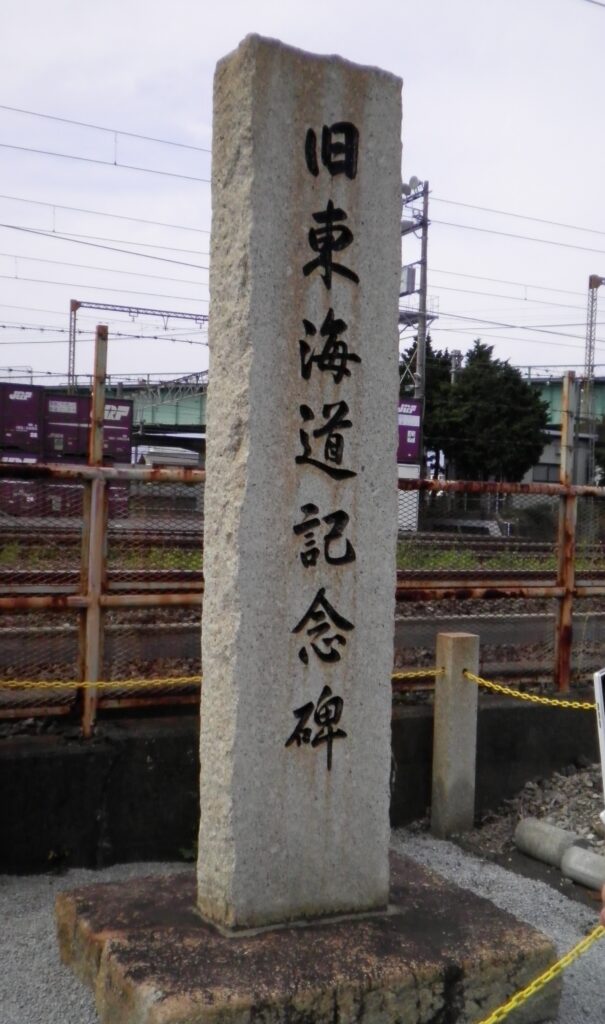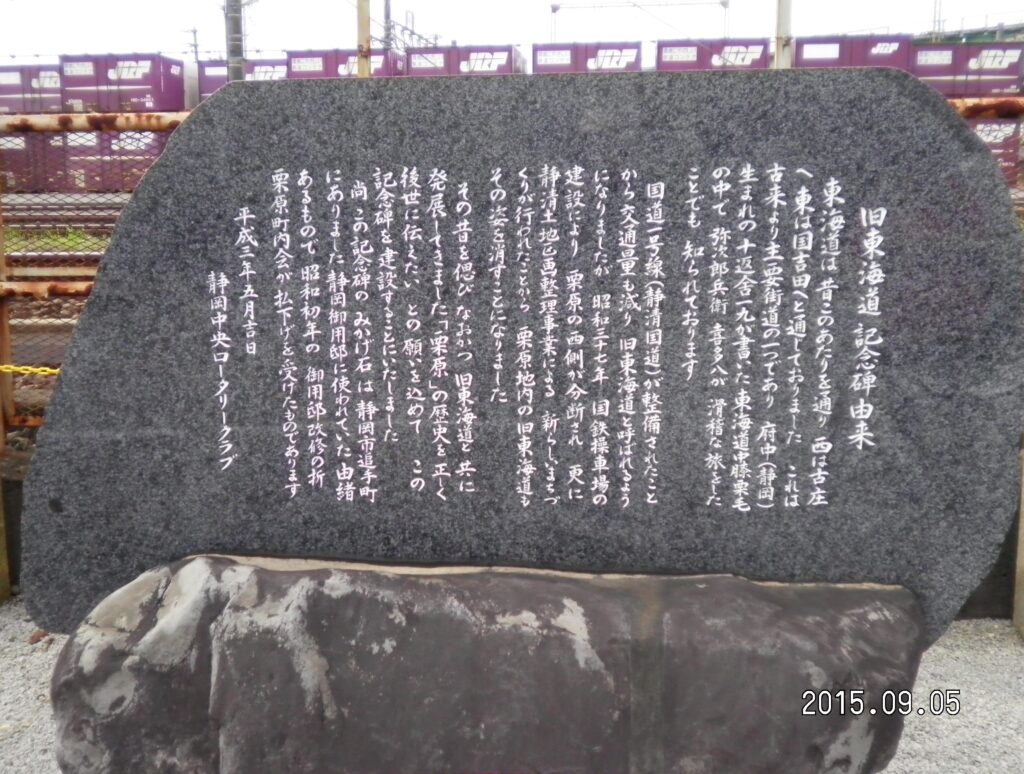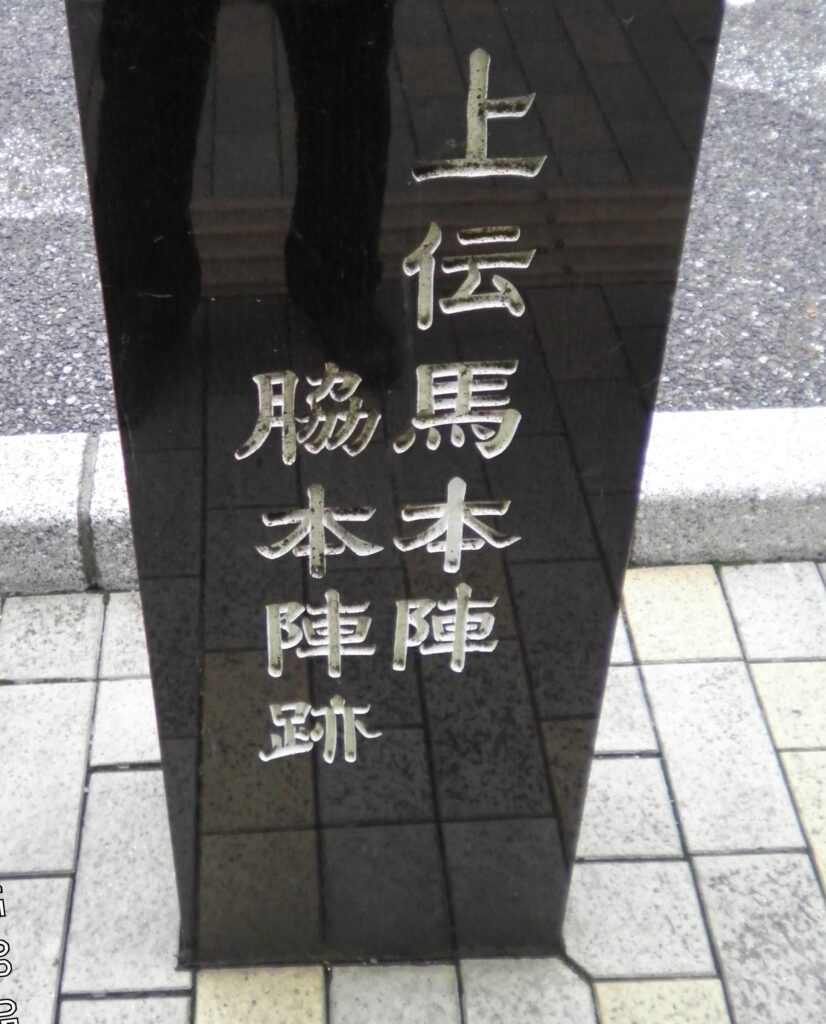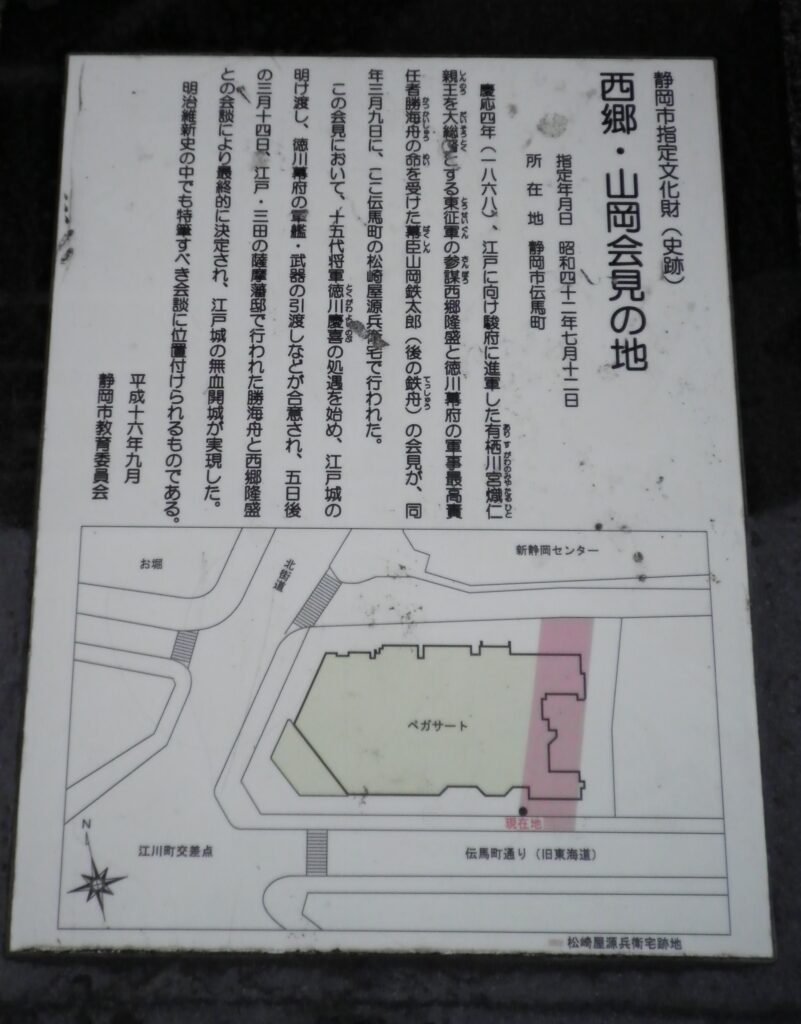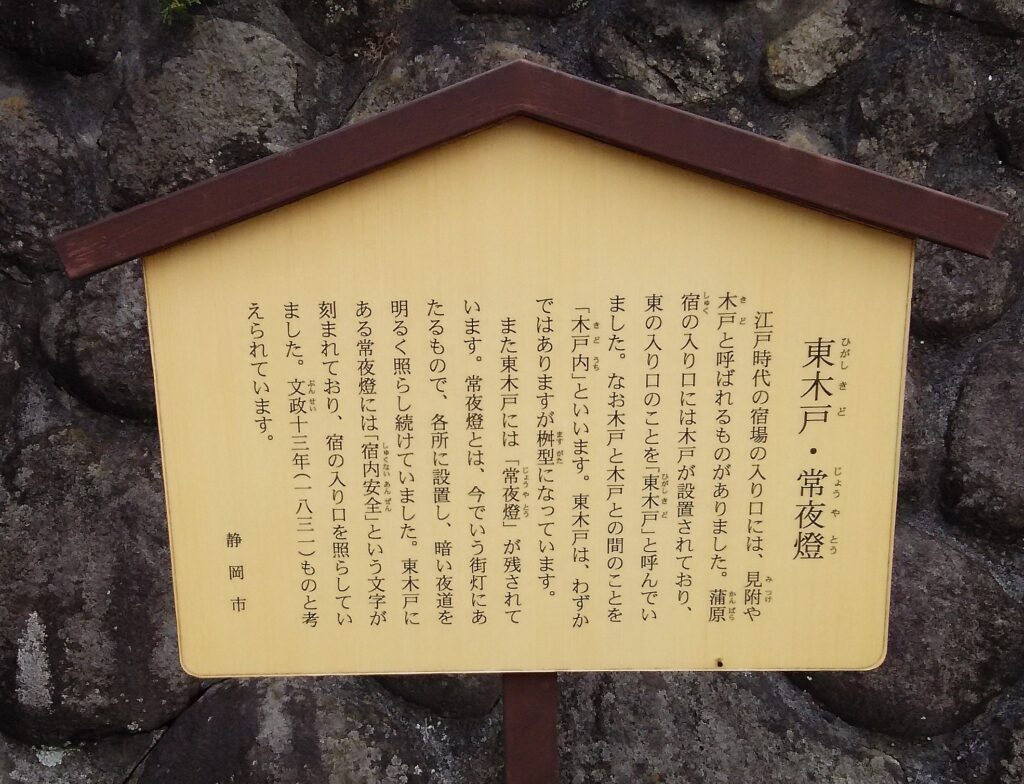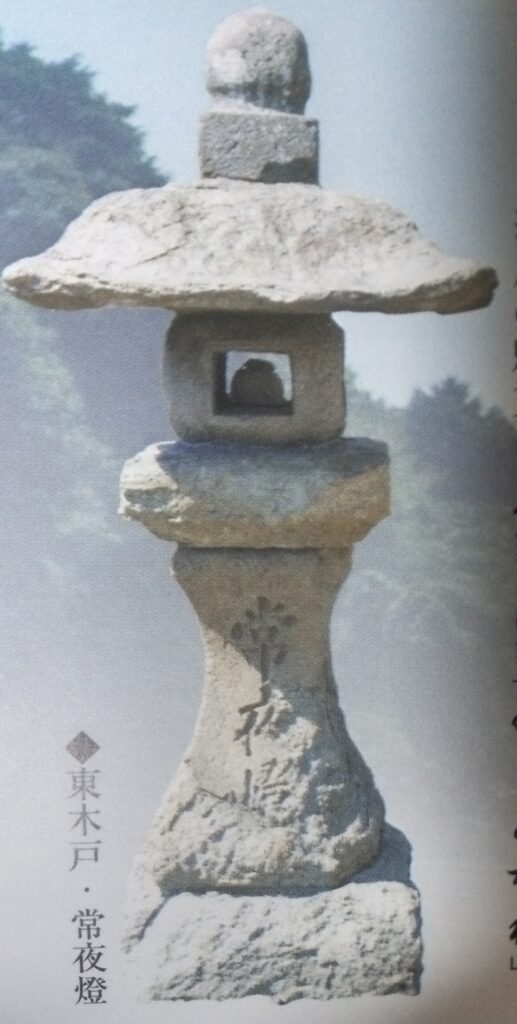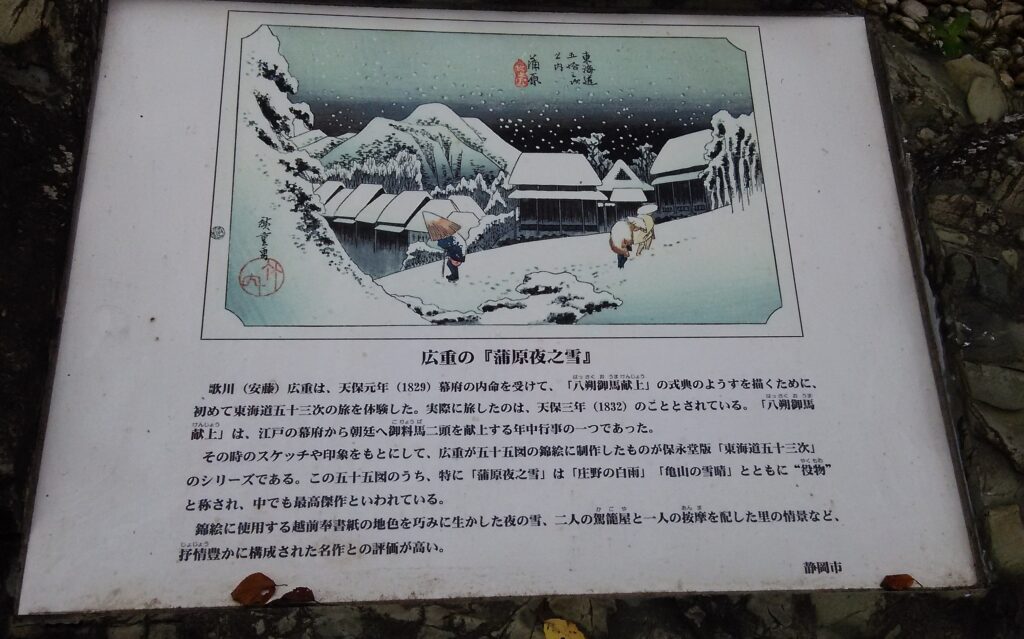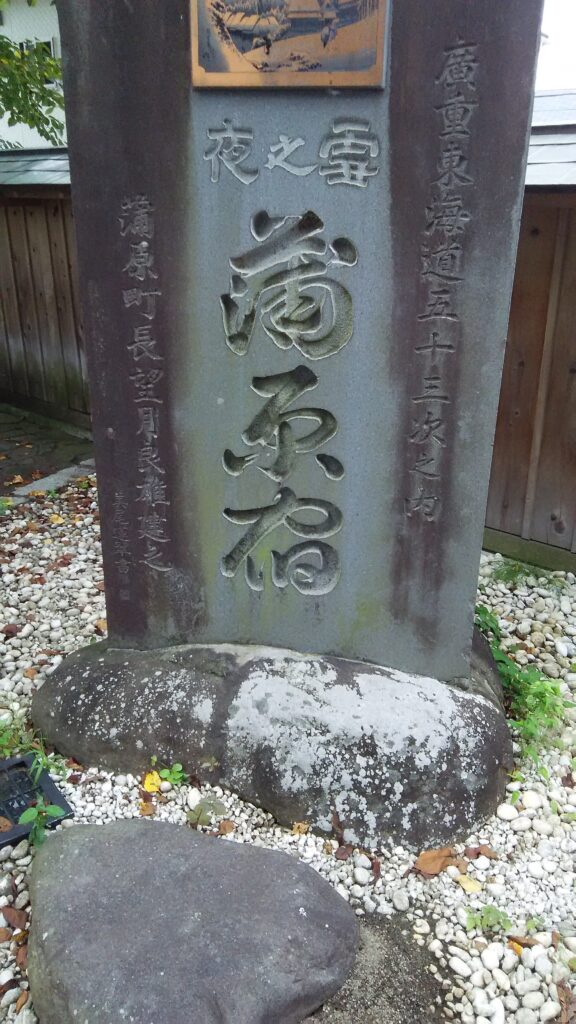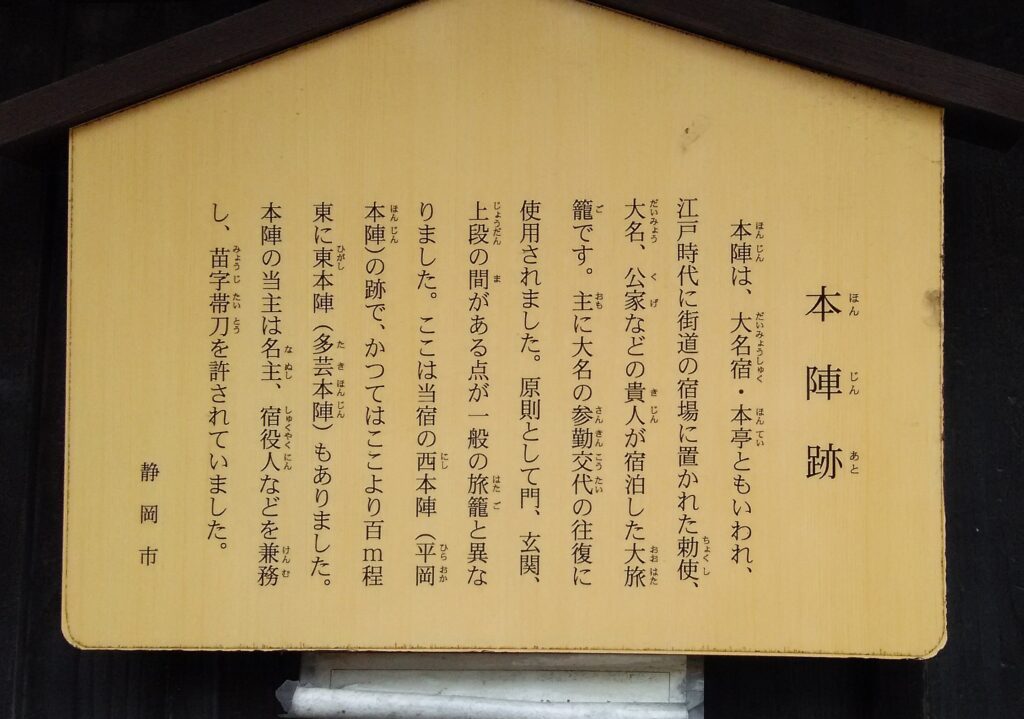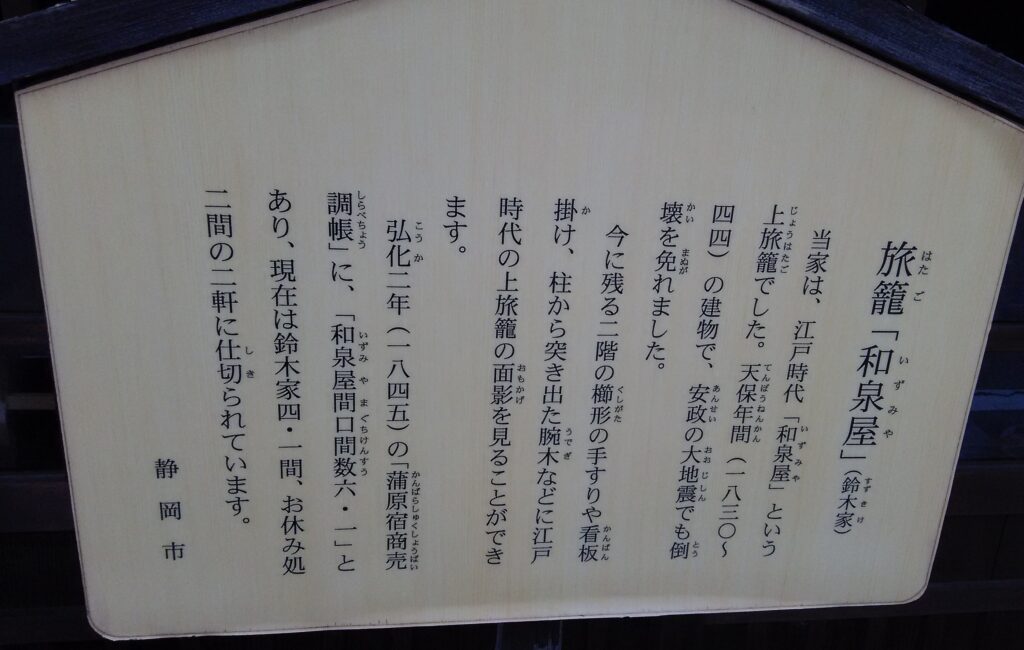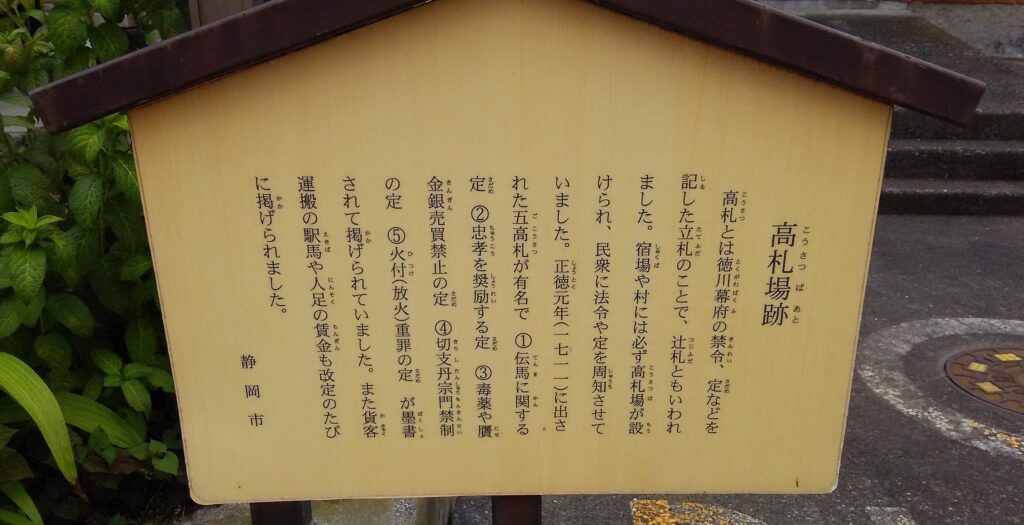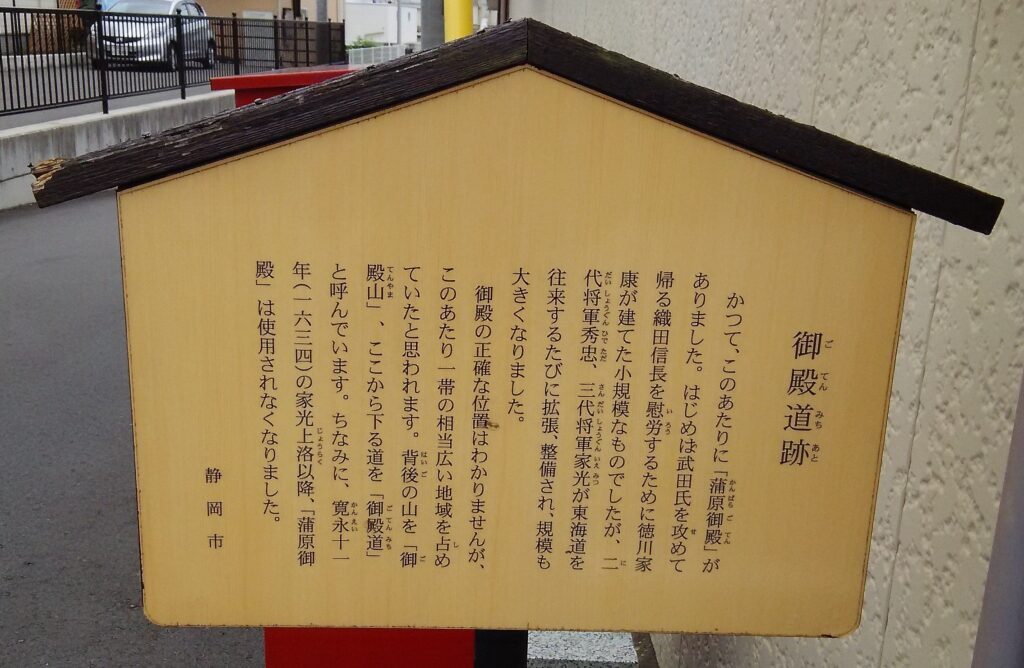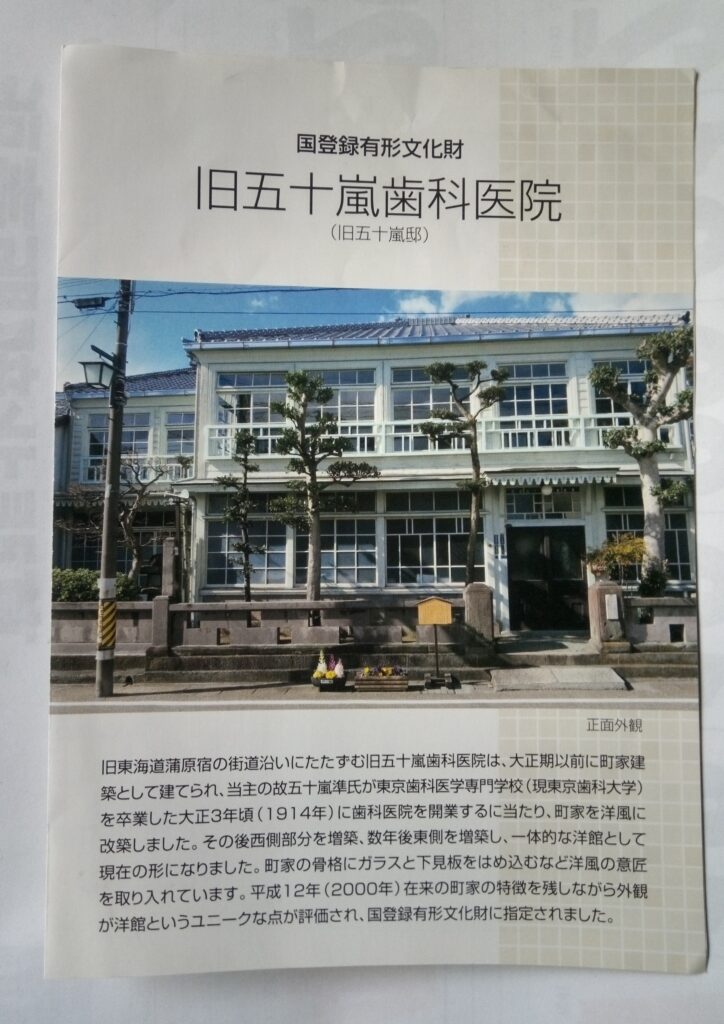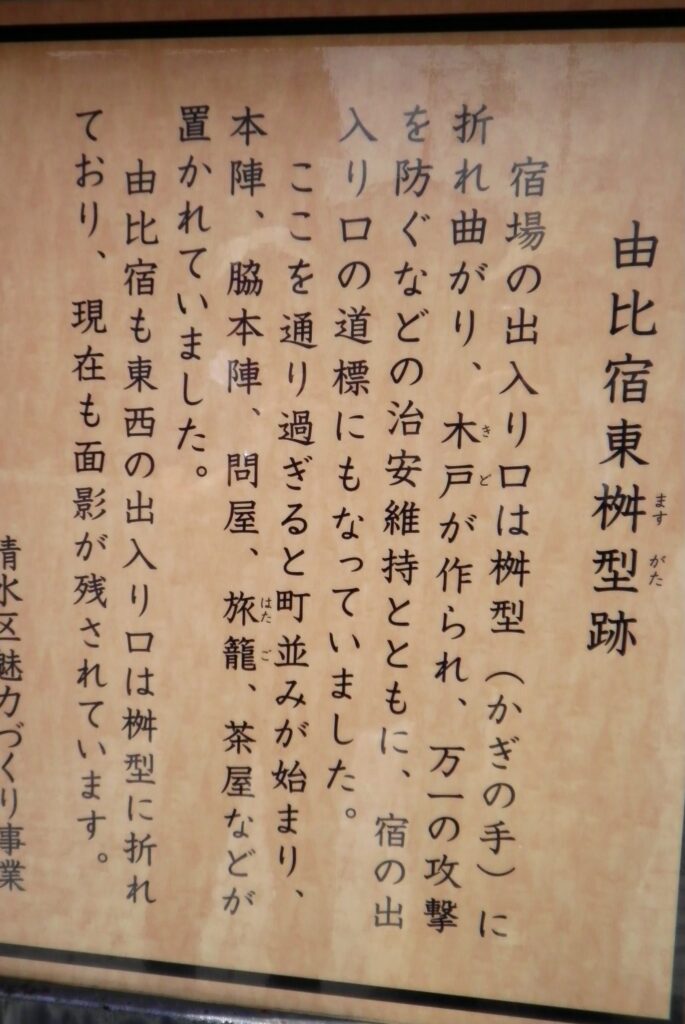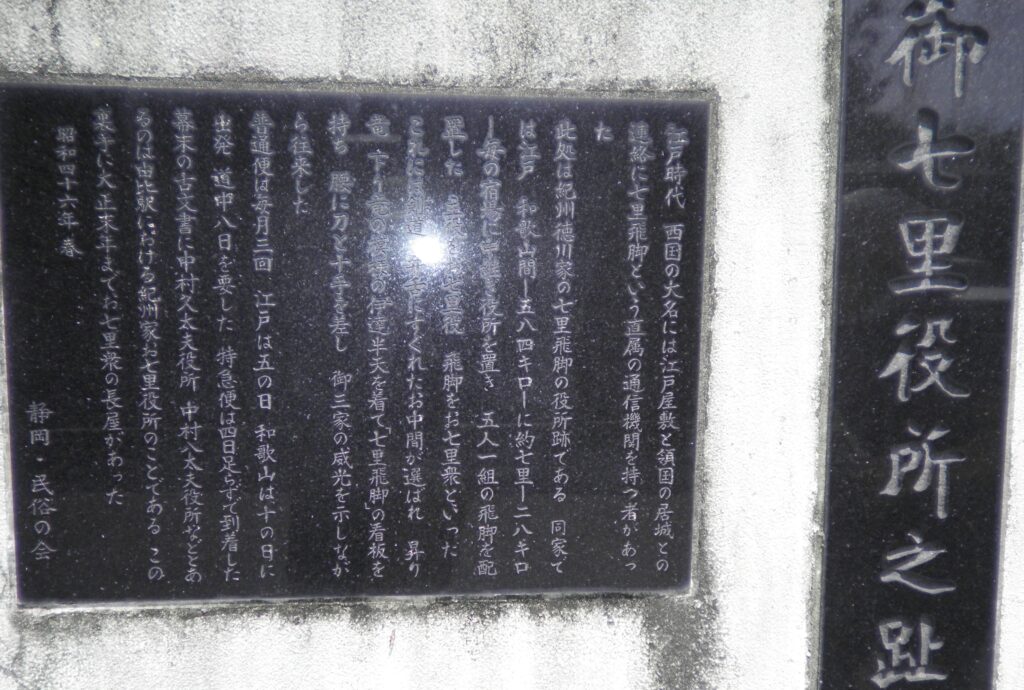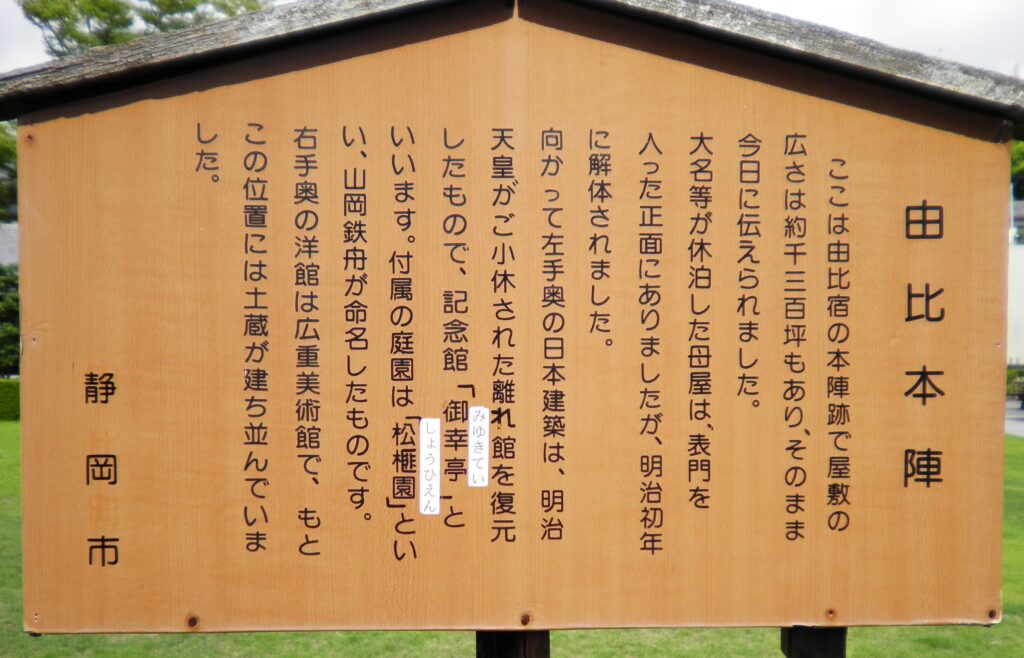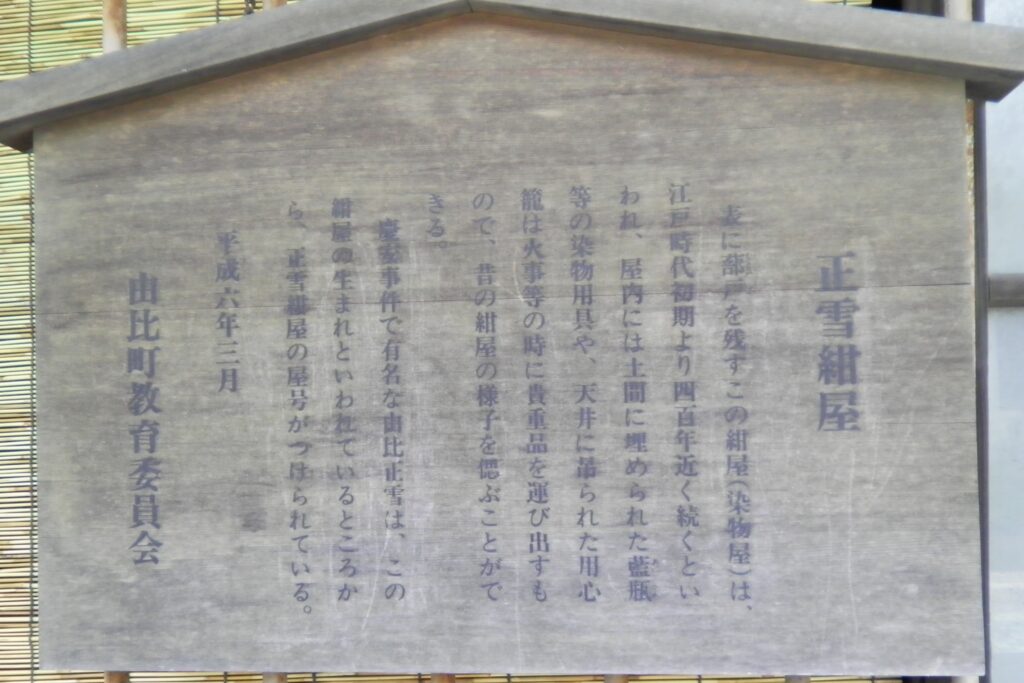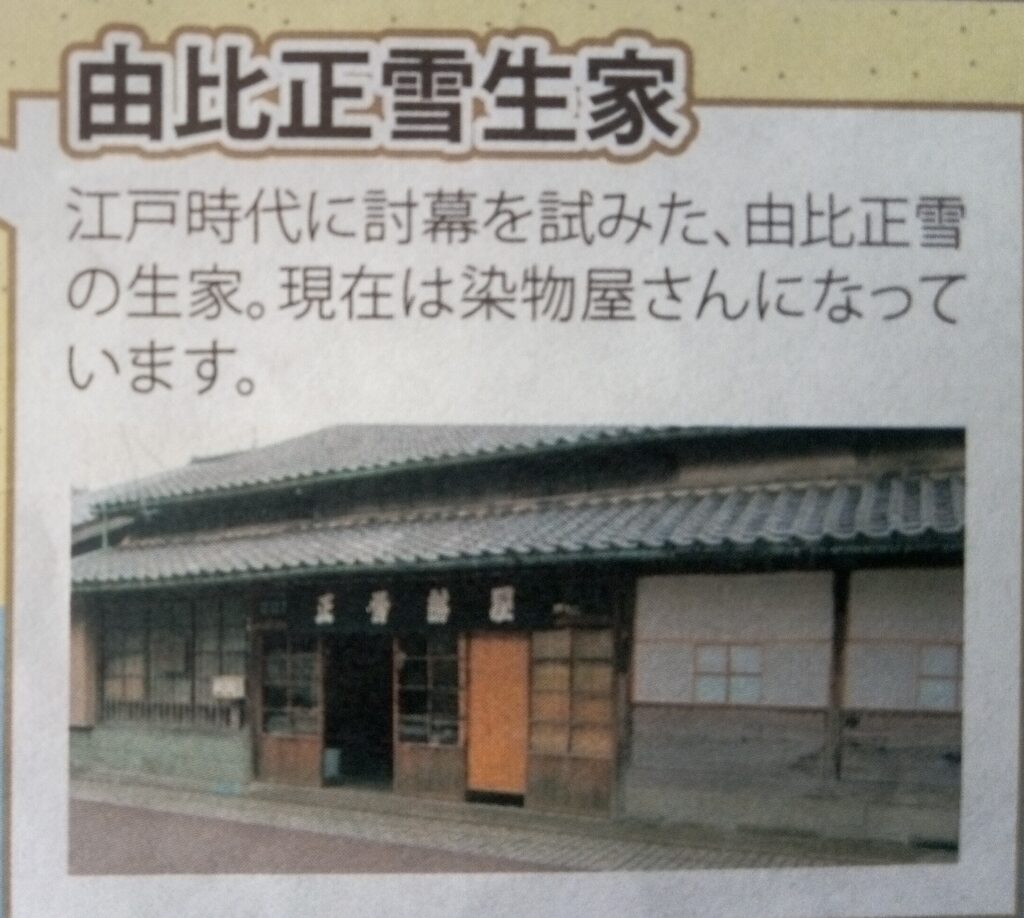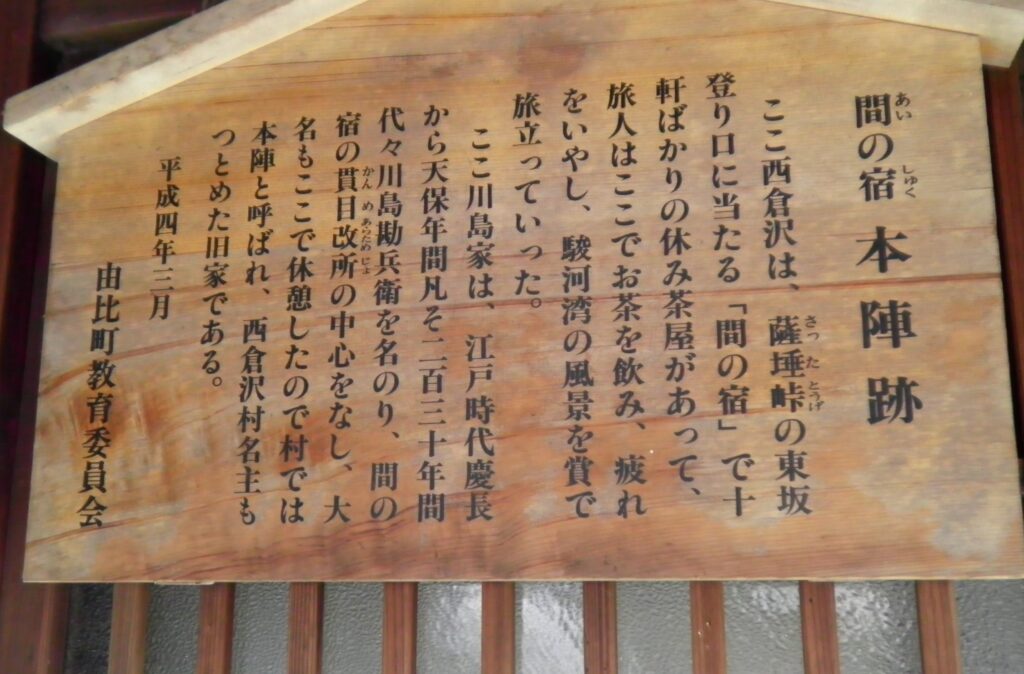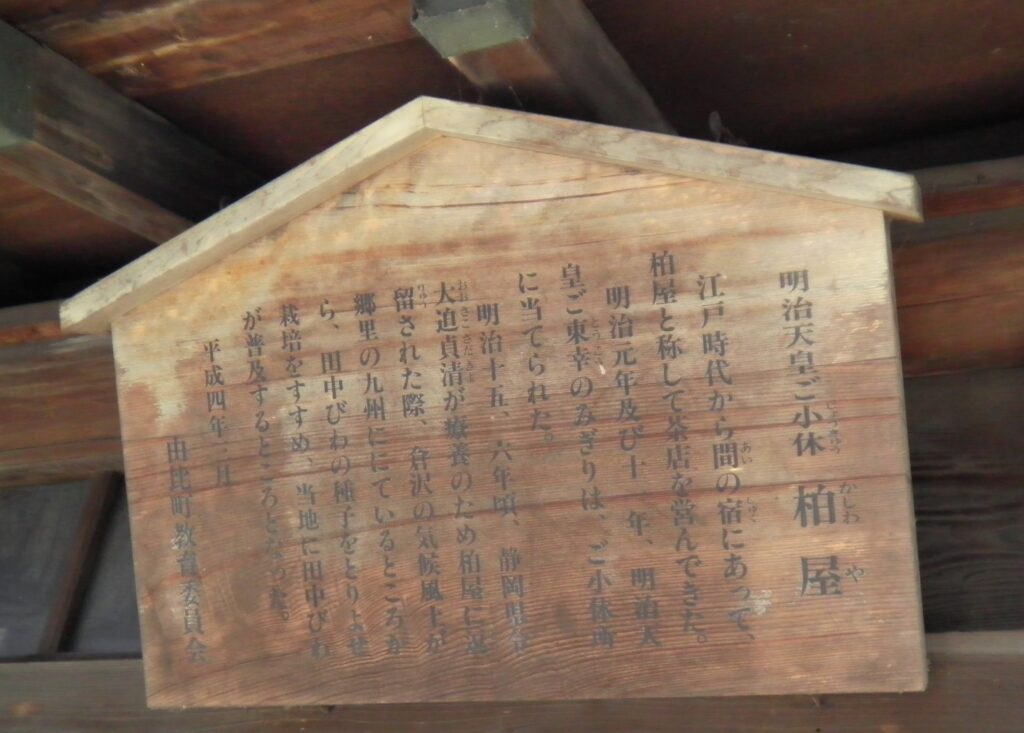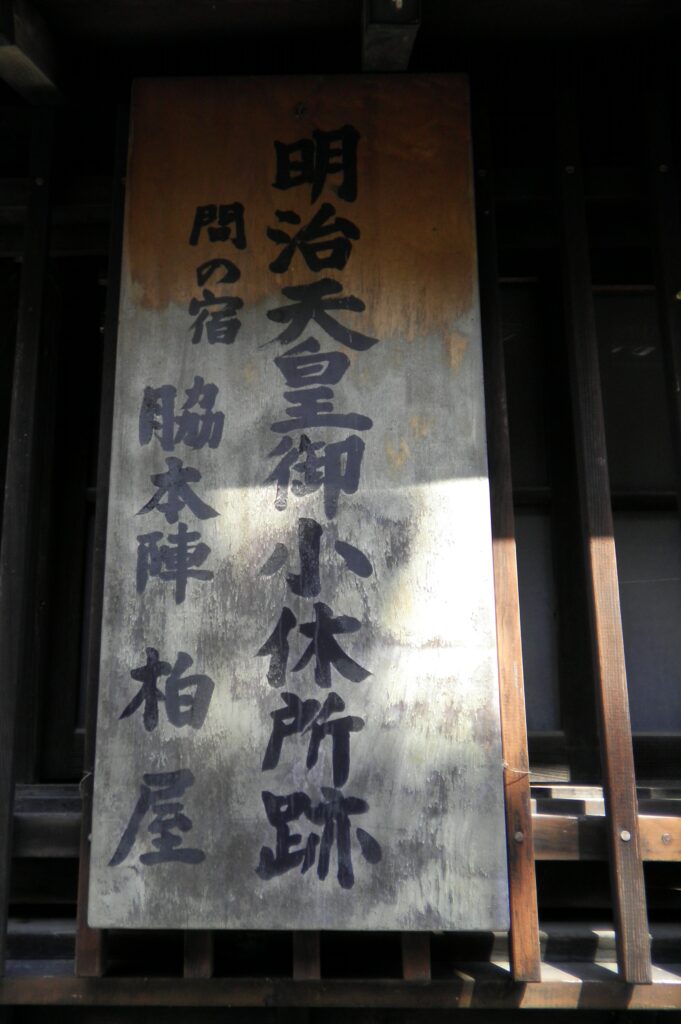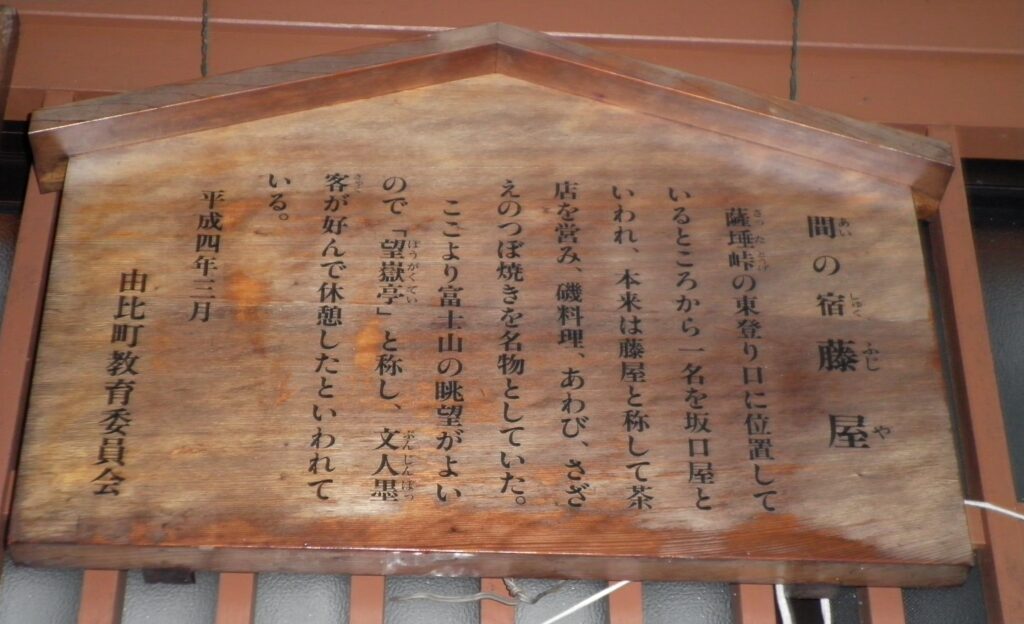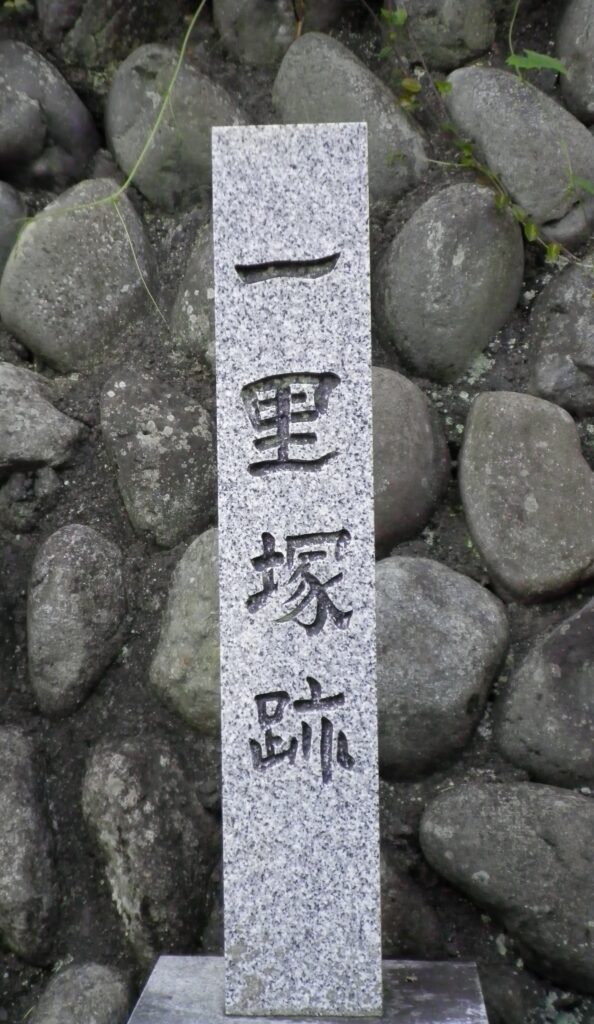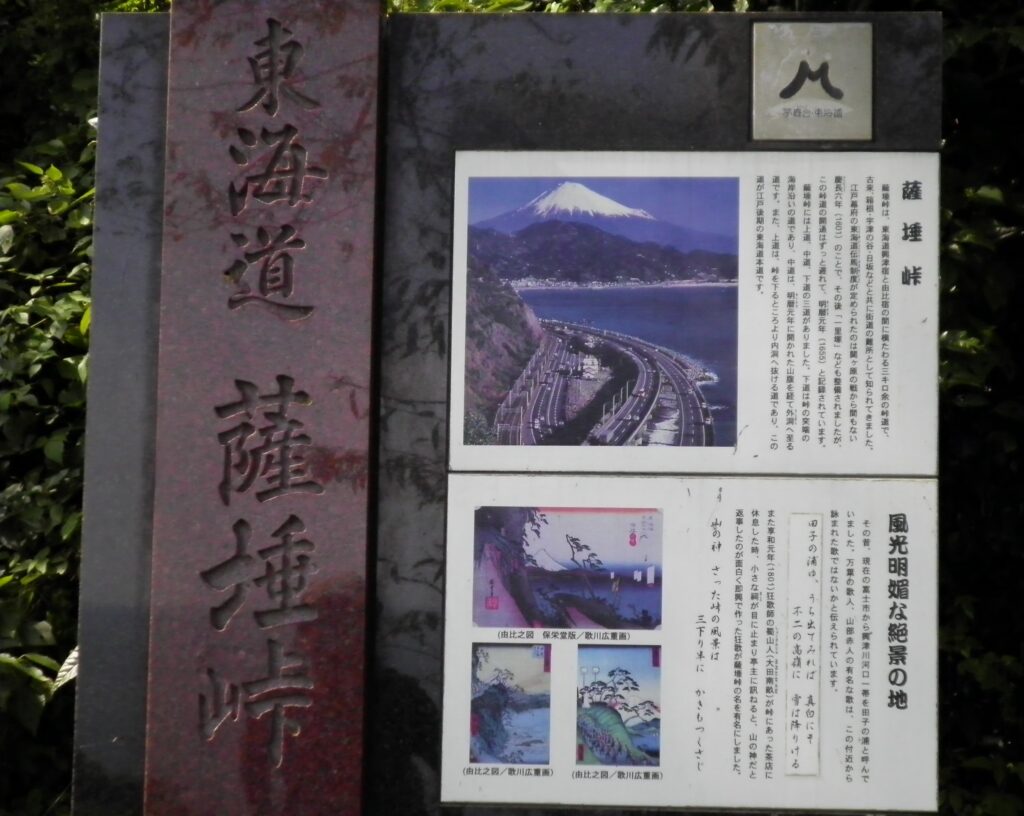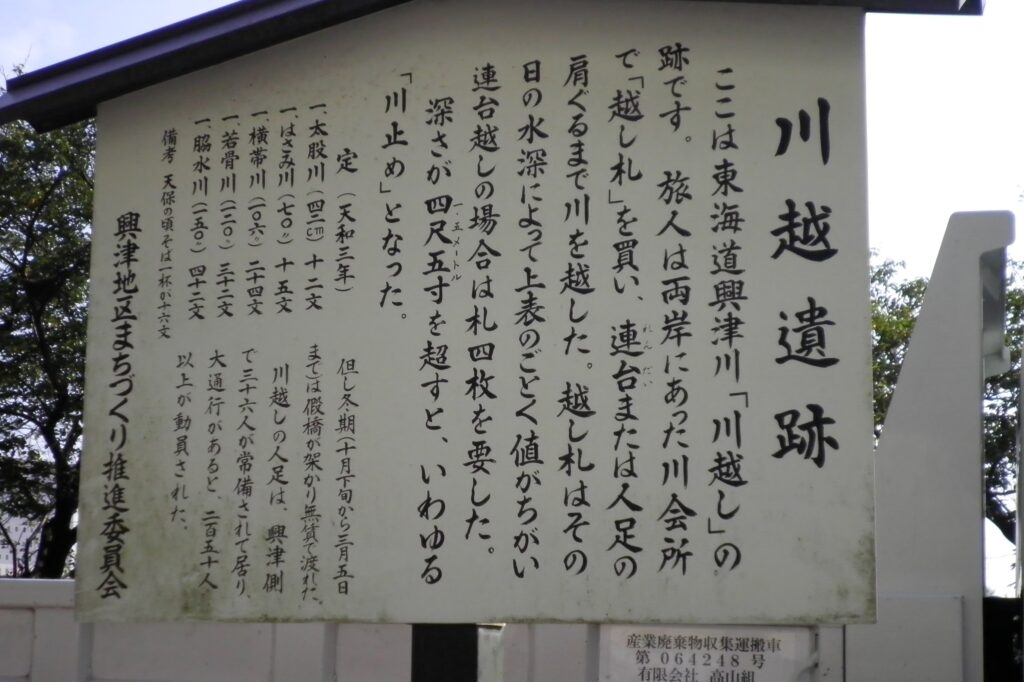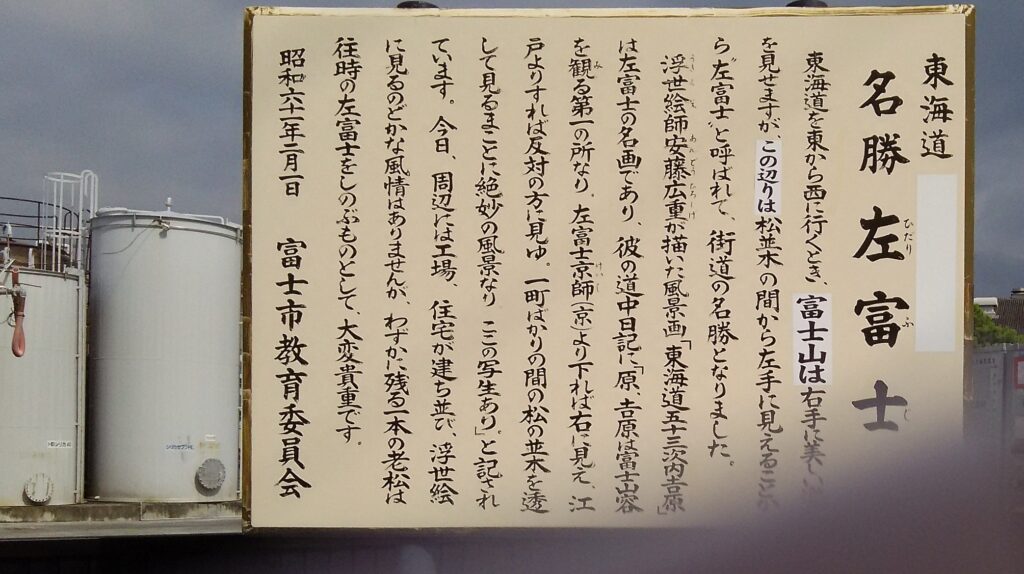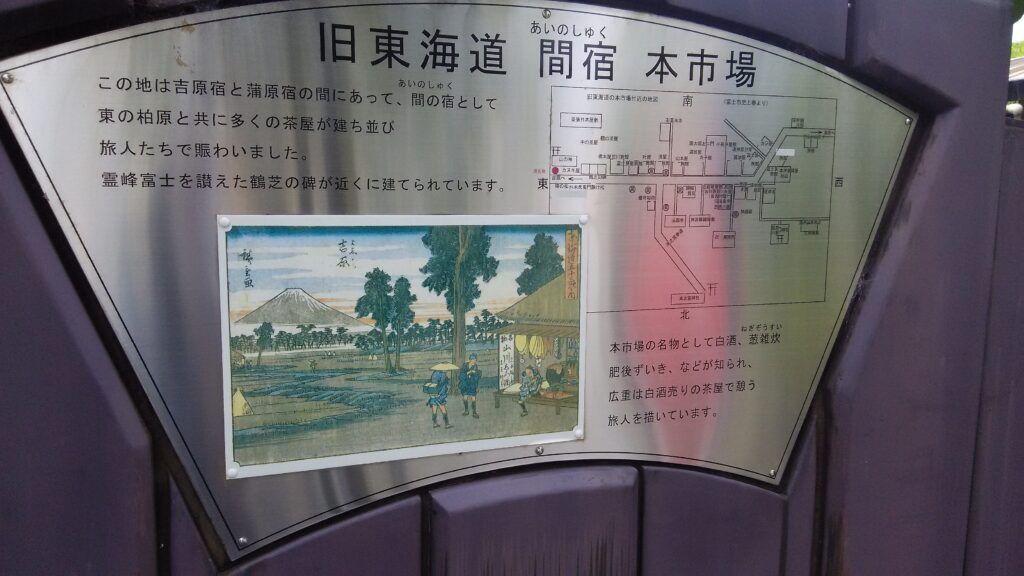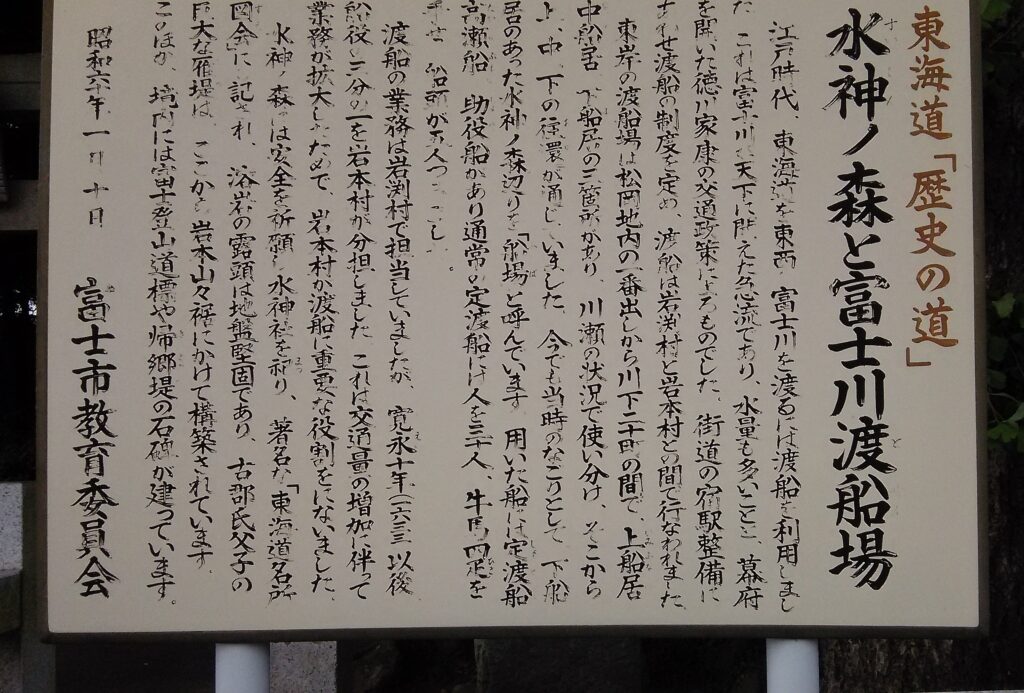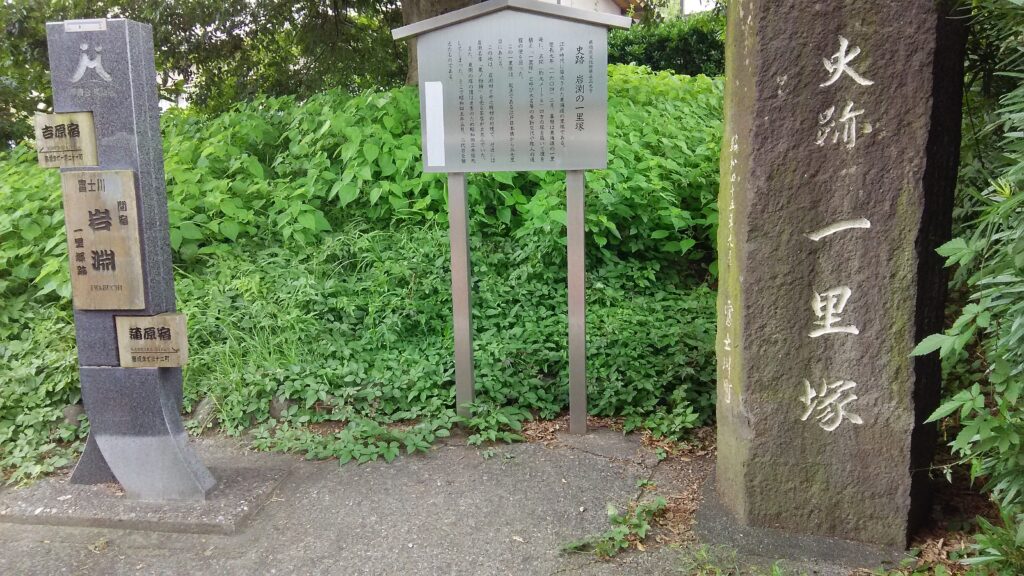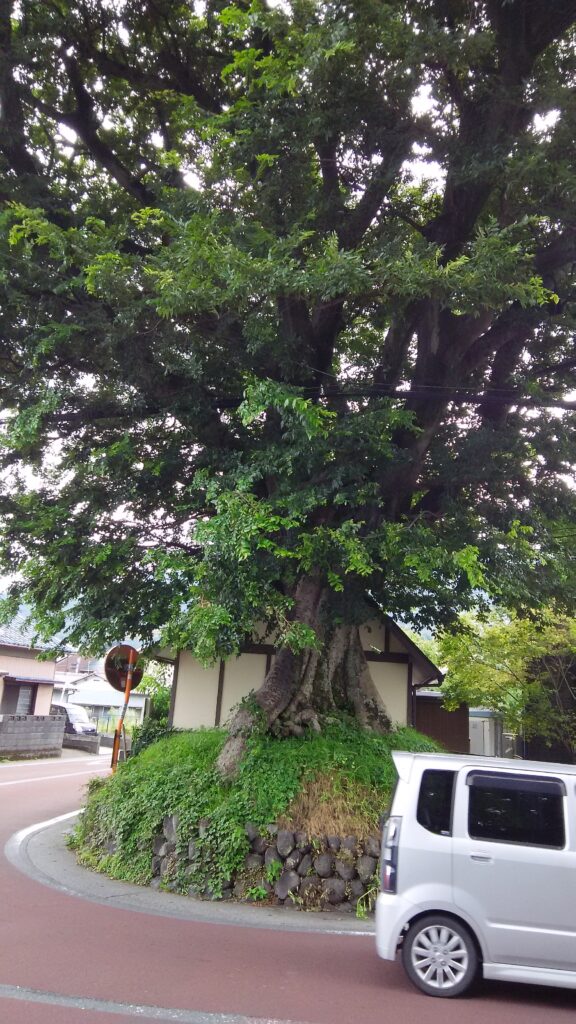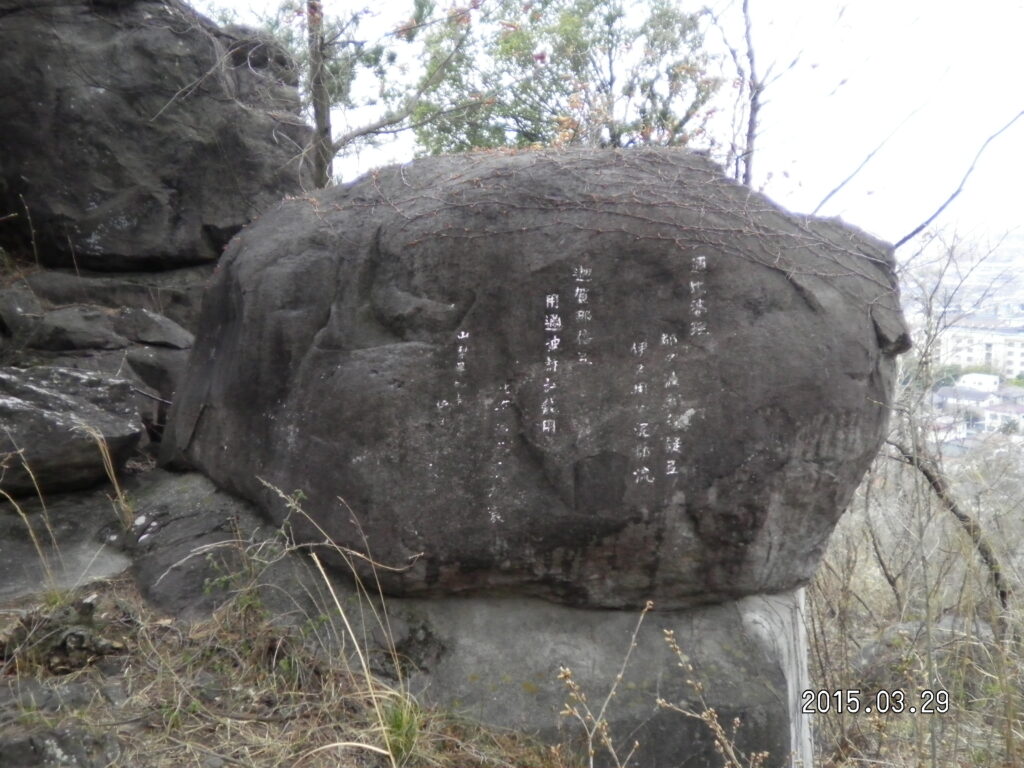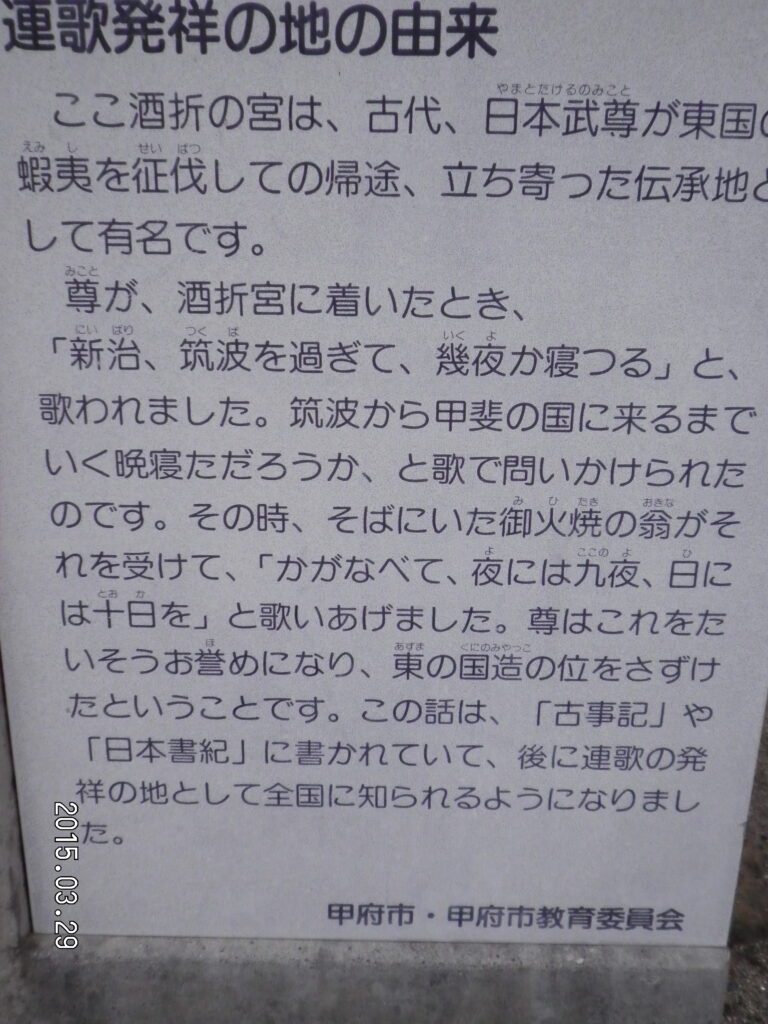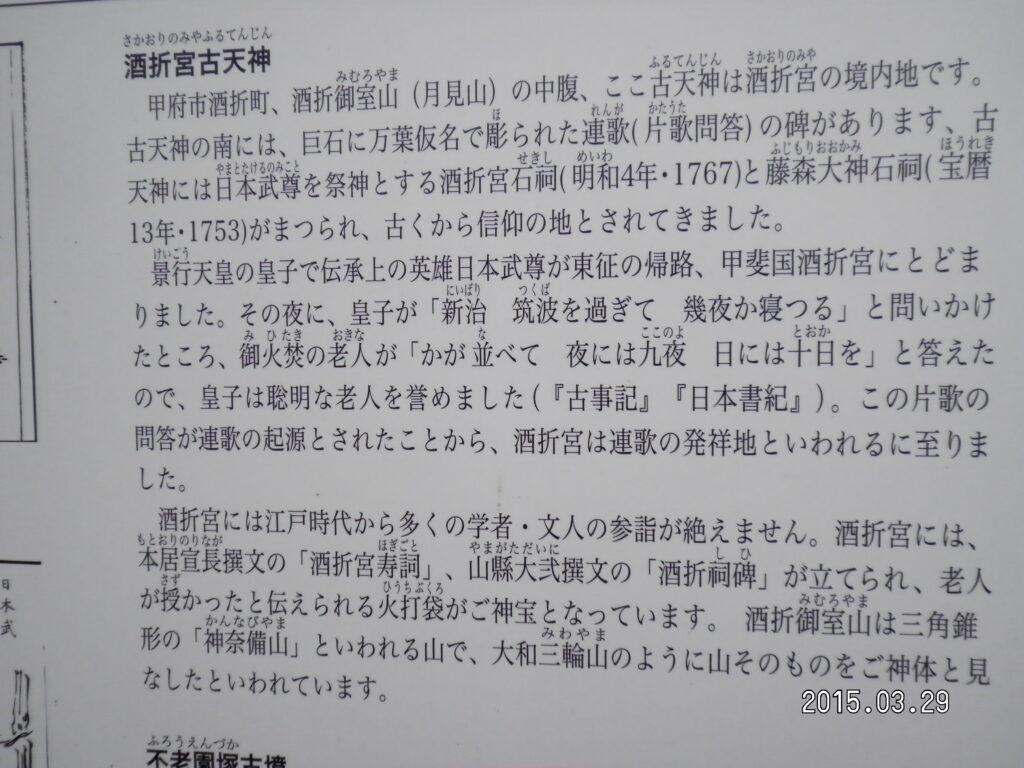<政治の日常化>を生活時間の中に組み込むことを心がけようと意識したら、これが怪物で時間がどんどんとられ、新聞を読むにしても時間が多くなる。というわけで、日常の習慣化につとめ時間配分の工夫に努めるしかない。もう一つ、生活の中での思考が観た芝居などの想いに影響されるようで、歌舞伎のような古典芸能も現代に生きる感情が左右され過ぎる傾向にあるように思い、冷静になってからとも考えた。しかし、古典であろうと現代に演じられ、現代の人が観るのであるからそれはそれと考えることにする。
『伽羅先代萩』。玉三郎さんの政岡の<人としての政岡>が胸に一撃を受ける。<飯(まま)炊き>の場は、じっくりと鑑賞させてもらったが、上手くできた場面である。主君・鶴千代を孤立無援で守る乳人・政岡、鶴千代を守るために我が子千松を身代わりとして教育する母親としての政岡。その二面性が、茶道具で飯を炊く美しい自然な所作と相まって展開される。お腹を空かす二人の子供は、低い屏風からそーっと覗きにくる。そこには主従の関係のない頑是ない子供である。
千松に対しては、母として叱り、次に来た鶴千代には千松がまた来たと思って叱ろうとして、鶴千代と知ってへりくだるあたりも二人の子供を挟んでの政岡の立場がわかる。この場での政岡のあらゆる行動によって、鶴千代と千松のそれぞれ立場を教え込む政岡の心のうちが伝わる。母として甘えたい千松。鶴千代にとっても母と同じであるが、その二人の甘えを拒否して、屏風をくるっと廻し自分を隠して涙を流す政岡の後ろ姿。こういう道具の使い方の先人の考えには唸ってしまう。ここでの三人の交流があってこその千松は母に教えられた行動へとつながるのである。ある意味で、政岡は意識的にか意識外なのかは判然としないが、千松をコントロールするのである。
千松は鶴千代の毒見役である。幼い当主を殺そうと企む執権仁木弾正(吉右衛門)一派から守るためである。そのため管領(将軍の補佐職)の妻・栄御前(吉弥)のお見舞いのお菓子を千松は走り出て口にするのである。毒のため苦しむ千松をみて弾正の妹・八汐(歌六)が手にかけ殺害してしまう。鶴千代をかばい懐刀の紐を解く政岡。鶴千代に害が及ばないと判断するや、静かにその紐を巻き整える。眼は逸らさず大きく見開き我が子の最期を見つめる。
栄御前が殺されたのは入れ替えた鶴千代と誤解し連判状を預けて去り、全てを身に受け、政岡は千松の遺骸の前で初めて母政岡となる。こともあろうに八汐のような者に殺された悲しみ。今回一番耳に残ったのは懐剣を持つ手を千松の首の上から反対側に渡し、懐剣を畳に立てた形で 「死ぬるを忠義と云う事はいつの世からの習わしぞ」 である。胸にぐっときた。母政岡の悲痛な叫びである。主人に仕えるキャリアの政岡が子供までも捧げる立場の嘆き。
ここまで至る憎っくき八汐も、沖の井(菊之助)と毒薬を調合した医師の妻・小槙(児太郎)の助力もあり政岡の怒りの一刺しとなる。ところが、連判状を鼠に持ち去られる。その鼠を捕らえようとするのが、荒獅子男之助(松緑)である。忠儀者で床下で鶴千代を守っていたのである。この設定も面白い。ところが、鼠は妖術を使う仁木弾正だったのである。花道に現れ太々しさを残し消える。
さらに面白いのは、妖術を使う仁木弾正も忠臣の渡辺外記左衛門(歌六)らの訴えにより幕府の問注所での裁きとなる。栄御前の夫・管領山名宗全(友右衛門)が弾正に有利な判決をだすが、管領細川勝元(染五郎)が現れ外記等の逆転勝訴とする。弾正は外記に襲いかかるが、忠臣たちに助けられ痛手を受けた外記は弾正に止めを刺す。
目出度く鶴千代の家督相続が許可される。
では、鶴千代の父上とは。それが最初にある<花水橋>に登場する、足利頼兼(梅玉)である。闇夜での出来事、だんまりの情景であるが、見えても見えなくても頼兼はゆったりと品格をみせ、闇から伽羅の匂いを醸し出さなくてはならない。こういう役は梅玉さん。いつも足の歩幅や動きの流れに目がいく。この感じを会得するには時間を要す。この殿様の放蕩からお家騒動となるわけである。
役者さんの置き所が的確で、それぞれの見せ場をたくさん作り芝居の空間を絞め、お家騒動ならではの苦慮が浮き彫りになった。
刺客に襲われる頼兼を助ける絹川の又五郎さんも力士の愛嬌と力がある。忠臣の沖の井の菊之助さんも八汐にしっかり対抗し政岡の忍に答える。児太郎さんも落ち着いて役どころの転換を見せる。男之助は出は少ないが弾正の正体を知らしめ、女たちの世界から男たちの世界へ転換する大事な場面であることを押し出してくれた松緑さん。八汐の歌六さんは憎々しく今までの八汐を演じた役者さんたちと肩を並べる。ガラッと変わった外記はお手の物。
大きな色悪の仁木弾正の吉右衛門さん。<対決>で自筆を書くだんで心の中で迷っている様子が吉右衛門さんならではの思索の人の一面が。その弾正の悪を暴く勝元の染五郎さん。高い音質が細くなるので心配したが、高低自在に変化をセリフに乗せ聞かせる工夫がみられ、急に高い声を張らせて語るあたりこれからのさらなる楽しみが増える。
今回の芝居でも、空白のある年代があることを思わせられるが、そのことを乗り越えて心している役者の意気が頼もしい。