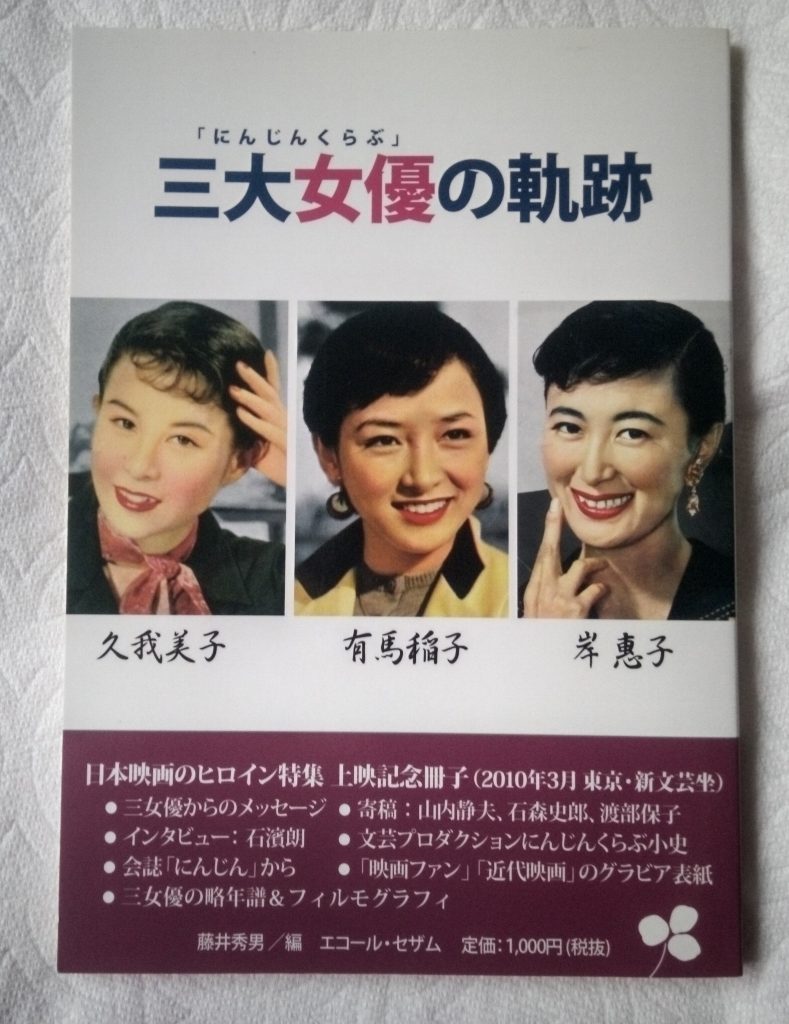東北六県であるが、福島は通過で降車しなかったので、宮城、山形、秋田、青森、岩手と東北五県を巡る。
山形の慈恩寺に憧れを抱き、いつかは行くぞと思っていたら、今年は今世紀初の秘仏御開帳である。宮城県仙台からバスツアーが出ている。山形県<慈恩寺>から<羽黒山>へ行き秋田県の鶴岡に抜けるのである。そうなると、五能線で青森に出れる。青森の<県立美術館>と<三内丸山遺跡>に寄り、岩手県の一関から、<平泉世界遺産めぐり>のバスツアーがある。平泉が世界遺産となり初めて知ったのであるが、それまでは形として残っている中尊寺の金色堂と毛越寺(もうつうじ)だけが頭にあったが違うのである。奥州藤原氏三代の築き上げ理想とした、万人平等の平和な浄土の世界、それが100年続いたという事が評価の対象である。その拠りどころとなった建物で当時のまま残っているのが金色堂だけなのである。残されたわずかなものと、今も発掘が続けられている遺跡の地を訪ねて想像の翼を広げないと、捉えきれないのである。青森の<三内丸山遺跡>も今年の発掘調査が開始されたばかりであった。
これが、今回の旅の柱であったが、旅には、予定外のサプライズの出会いがつきもので、最初の宿泊地秋田で、出会いがあった。
友人が先に、東北から新潟への旅に出ていて、時々報告がメールで入る。彼女は、レンタカーを使い、石川雲蝶を追いかけている。石川雲蝶は<越後のミケランジェロ>といわれている彫り物師である。その一報に、「秋田県立美術館所蔵、藤田嗣治の『秋田の行事』が最高。他の油絵、素描も感激。」とある。こちらは仙台から秋田に抜けて、秋田に泊ったのであるが時間が無いと思いきや、朝起きて気が付く。美術館がホテルから5、6分。美術館は秋田駅から10分である。美術館の開館前に行くと、20分は時間をとれる。
『秋田の行事』見れた。一人一人の表情、筋肉の動き、人の動きによって踏まれた雪、今にも雪が降り出しそうな鈍よりとした空模様、右手の祭りの造り舞台では、秋田音頭が踊られていて、見物人は浴衣で、夏祭りであろうか。大平山三吉神社の大祭であろうか、鳥居を潜ろうとする神輿を担いだ男たち。その前面に漁師であろうか、厚い刺し子の長い防寒衣を着た大きな男。秋田竿燈(かんとう)もある。立てかけられた木材には秋田産の焼印。箱そり。秋田犬。継張りされた、夜店の囲い布の色が優しい。油絵、素描と凝縮された時間である。油絵の町芸人、力士などは、フェリー二監督の登場人物を思わせる。
『回想 寺山修司』の中で、『毛皮のマリー』パリ公演の最終日、ホモセクシュアル文化のメッカでもあり、その手の客を招待した時の様子を次のように表現している。「フェデリコ・フェリー二の映画からぬけだしてきたような着飾った連中が、まるで悪夢のようにどっと押し寄せたものだから、公演どころではなく奇妙なパーティー騒ぎになってしまったのである。」すぐ想像がつく光景描写である。やはり、旅の途中もどこかで寺山さんを引きずっているようだ。
感動を知らせてくれた友に感謝である。藤田嗣治さんの絵は、資産家・平野政吉さんが収集したもので、『秋田の行事』も平野家の米蔵の中で描いている。平野政吉コレクションとあるので、秋田県立美術館が所蔵しているのではないかもしれない。この壁画は、1937年(昭和12年)に新しい美術館に飾られる予定であったが、戦争のため美術館の建設が中止となり、一般公開されるのが、30年後の1967年(昭和42年)である。その間、平野家の米蔵で保管されていた。今は、秋田県立美術館に行けば藤田嗣治の『秋田の行事』を見る事ができるのである。時間の無い者には嬉しいことに、310円の観覧料であった。
もっと驚いたのは、青森の<三内丸山遺跡>は、展示室も含め無料である。あの広い縄文時代の<ムラ>の草刈りなど、ボランティアの方達がされているのだそうである。東北の地に根ざした力は凄いです。平泉にしろ、頼朝は恐れを感じていたことがわかる。東北独自の考え方を持つ現世の浄土感の土地だったのであるから。
東北の旅・仙台~天童~慈恩寺(2) | 悠草庵の手習 (suocean.com)