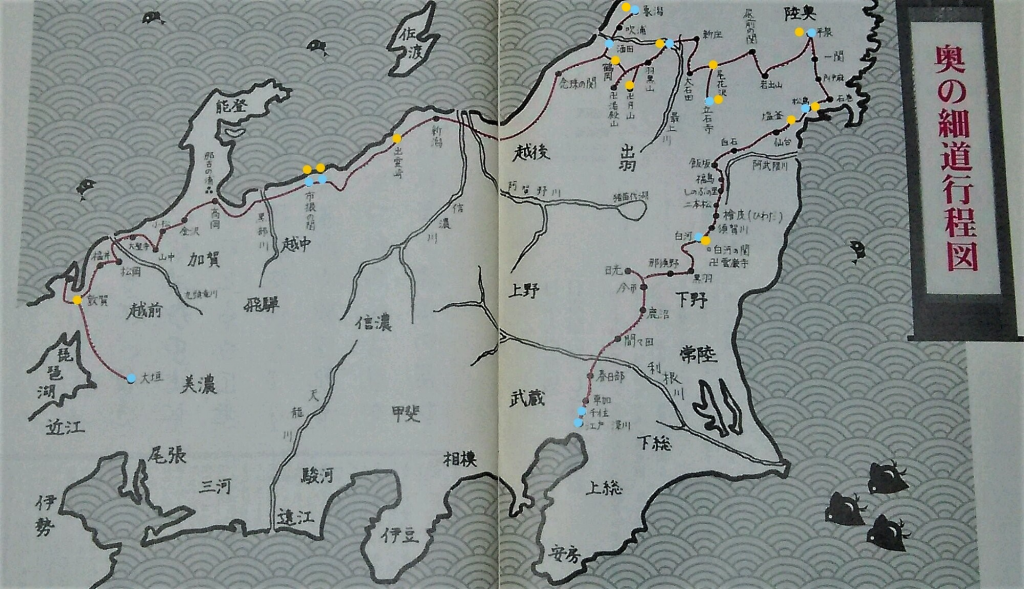芭蕉は松島から平泉へ向かいますが途中で道に迷って石巻という港に着いたとしています。<つひに道踏みたがへて石の巻といふ港に出づ> 江戸時代の石巻港は東北でも有数の港で迷うということはないはずで、これは創作的表現で道に迷って着いたところがにぎやかな港であったとの驚きを加味したのだろうとのことです。
そして平泉。
⑤夏草や 兵(つわもの)どもが夢の跡 / 五月雨(さみだれ)の 降り残してや光堂
『趣味悠々 おくのほそ道を歩こう』では義経終焉(しゅうえん)の地とされる高館にある義経堂(ぎけいどう)を訪ね、その後で中尊寺にむかいます。芭蕉と同じ道です。

義経堂は高館の山頂にあり途中古戦場跡と北上川がみえます。
義経は、藤原秀衡によって鞍馬寺からこの平泉に招かれます。それは秀衡がこの地で戦い抜いたとき助けてくれたのが陸奥守であった源義家だったのです。その子孫が義経です。兄頼朝が旗揚げしたとき秀衡は臣下の佐藤継信、忠信兄弟を義経に随行させました。そして平家を倒してのち、兄に追われる身となった義経をうけいれました。
義経が到着して8か月後秀衡は亡くなります。次の泰衡の代となり頼朝の圧力に負けて義経を邪魔ものとして奇襲するのです。そしてこの地で義経31歳で終えるわけです。しかし頼朝は奥州が欲しかったので奥州藤原は滅びてしまいます。
< 「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、笠うち敷きて、時の移るままで涙を落としはべりぬ。 夏草や兵どもが夢の跡 >


義経堂は芭蕉が来訪した6年前に建立され義経像もその時にまつられたものだそうです。何もかもなくなっている地にこの堂と像を拝観した芭蕉は涙ししばし立ち去れなかったのでしょう。
奥州藤原三代の仏教を中心とする文化圏は世界遺産として登録されましたので跡地に復元がなされたりして芭蕉の見た風景と今とは随分と違っているとおもいます。私も二回目訪れの時は歴史的奥州の姿をバスガイドさんやボランティアのガイドさんによって多くを知らされました。
芭蕉の訪れた頃は中尊寺一帯も1126年の火災で様変わりし変わらないで残っていたのが金色堂でした。金色堂は芭蕉さんの時には荒廃をおそれて木造の堂で覆われ、その中に美しい姿をたもってくれていました。< 千載の記念とはなれり。 五月雨を降り残してや光堂 > 雨が避けてくれて残ったような光輝く堂だったのです。
今はコンクリートの覆堂で旧覆堂ものこされています。須弥壇には初代藤原清衡、2代基衡、3代秀衡の遺体が納められています。4代泰衡は御首級(みしるし)が納められているようです。

この金色堂も1962年(昭和37年)から7年間解体修理されます。その様子を映像で観ることが出来ます。努力を惜しまない根気と素晴らしい技術の結集です。
この映像で高館から中尊寺まで雨の中歩かれた黛まどかさんと榎木孝明さんの道筋がわかりました。高館には行っていないので歩きたかったです。
よみがえる金色堂(フルHD)|配信映画|科学映像館 (kagakueizo.org)
平泉の文化はかつて京の都から匠たちが集結して作り上げられました。そこから残った金色堂は再び未来をめざして再現されたのです。この時の中尊寺貫主は今東光さんでした。
西行はこの地で桜を見て吉野の桜に並び称されると歌っています。 <きゝもせず 速稲山(たばしねやま)のさくら花 よし野のほかに かゝるべしとは>
芭蕉も当然ここで桜を見ることを望んでいたでしょうが桜に関しては何も書いていません。それはもっと先で思いがけない場所での桜との出会いがあるのでそれを強調するために見ていても記さなかったのかもしれません。
秀衡は子供たちに義経を大将にして奥州を守り通すようにと遺言を残します。その遺言を守ったのが三男の忠衡でした。彼は遺言通り義経を守りますが、23歳で力尽き亡くなっています。その忠衡が寄進した鉄の宝燈「文治灯籠」が塩釜神社の社殿の前にあります。当時のものではありません。芭蕉は忠衡の戦死を知っていたので、「文治灯籠」の前で言葉を尽くして彼を讃えています。
芭蕉の中では義経の周囲の人々のことも構図としてとらえられていたのでしょう。
追記:
一面満開の桜もいいですが

こんな桜も愛おしい