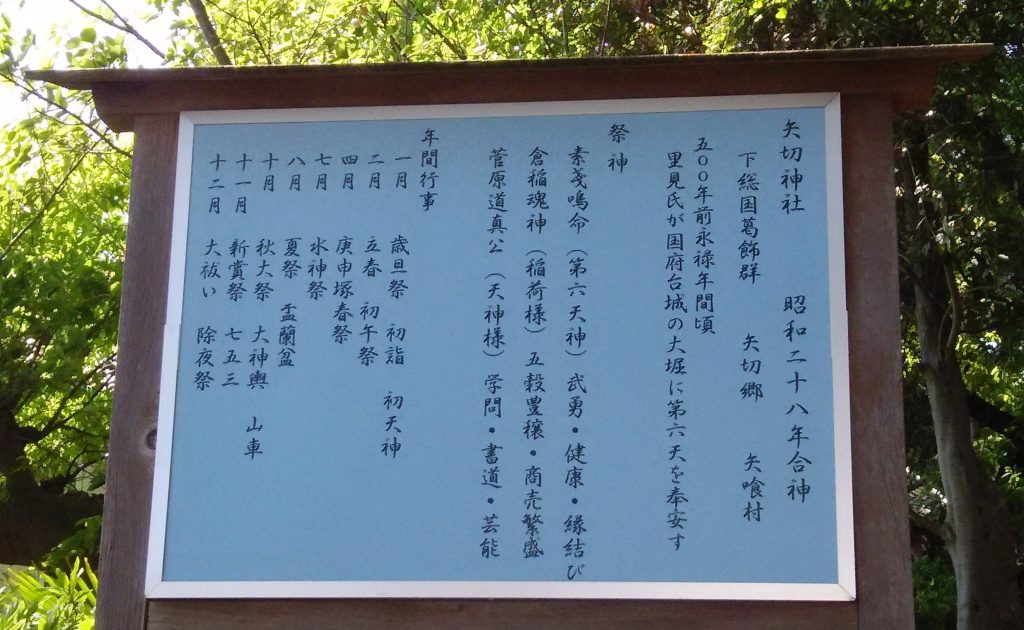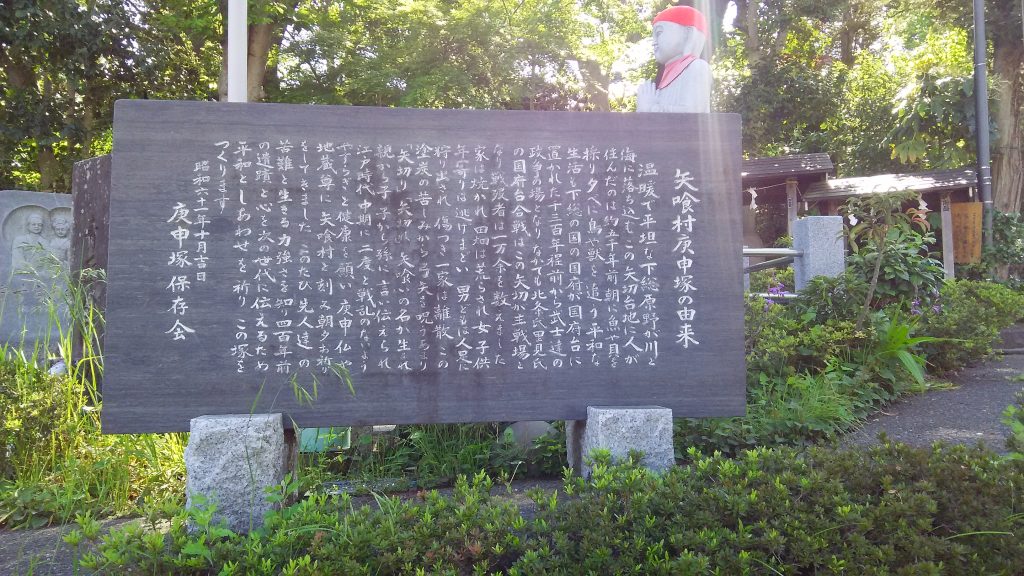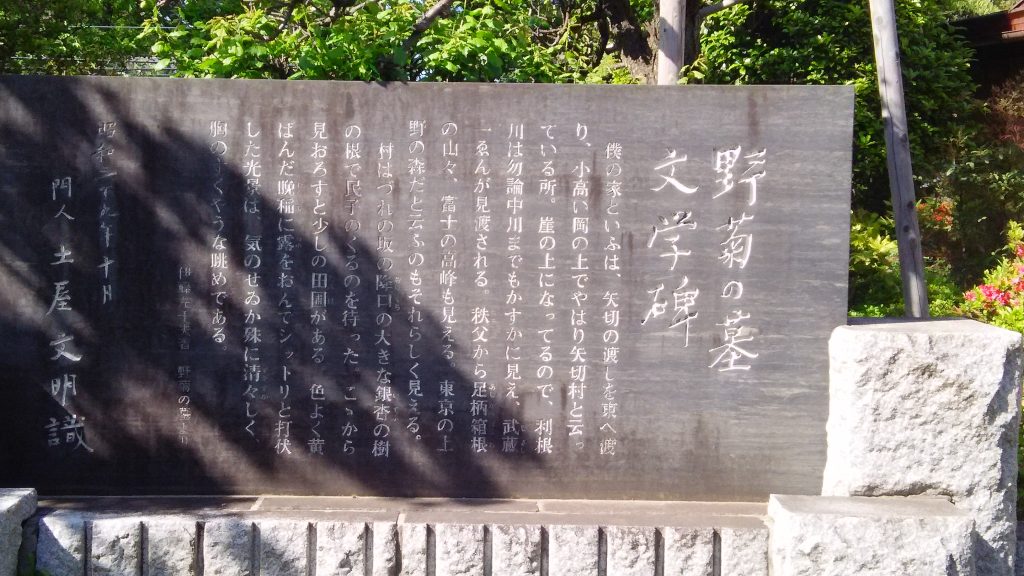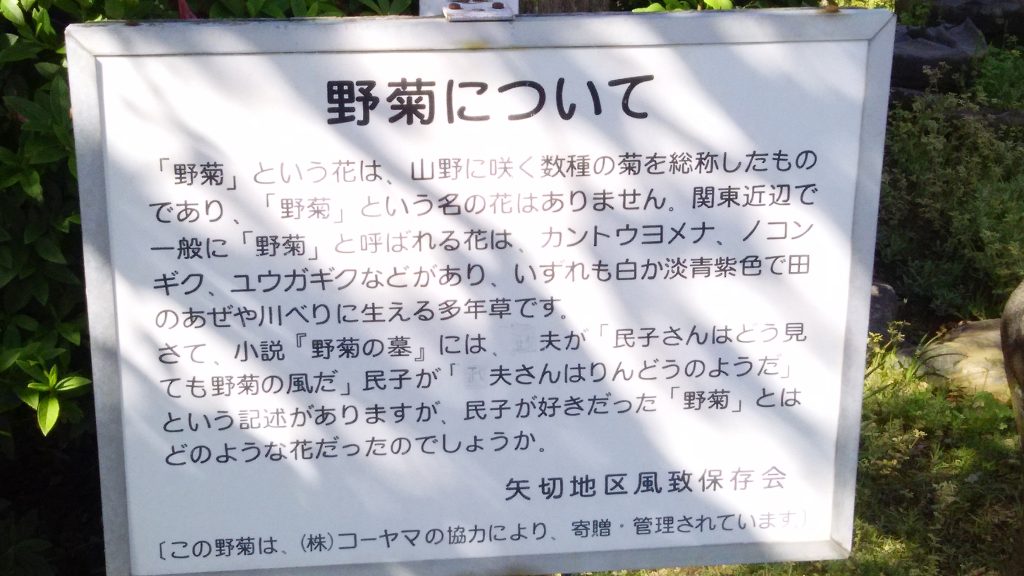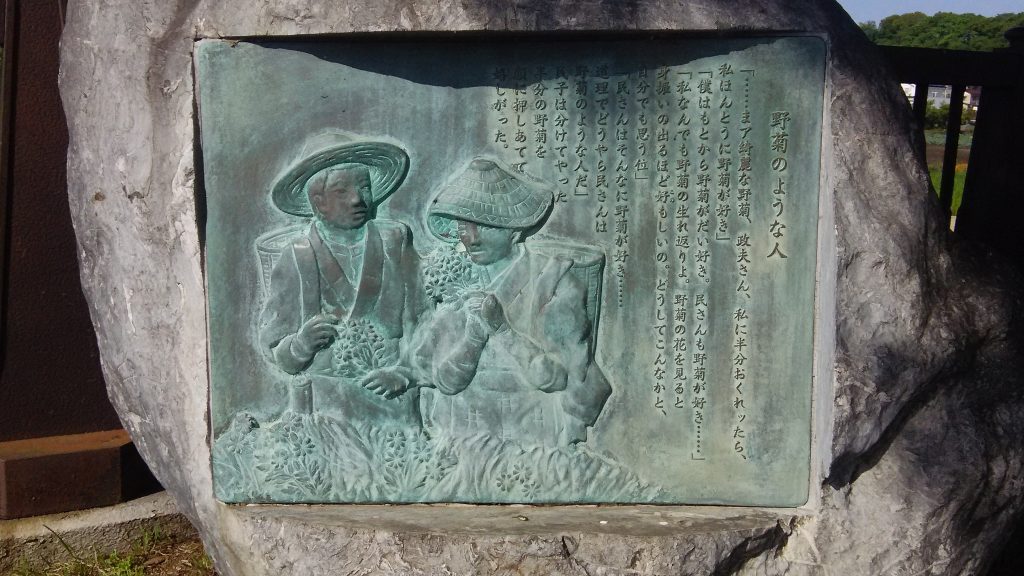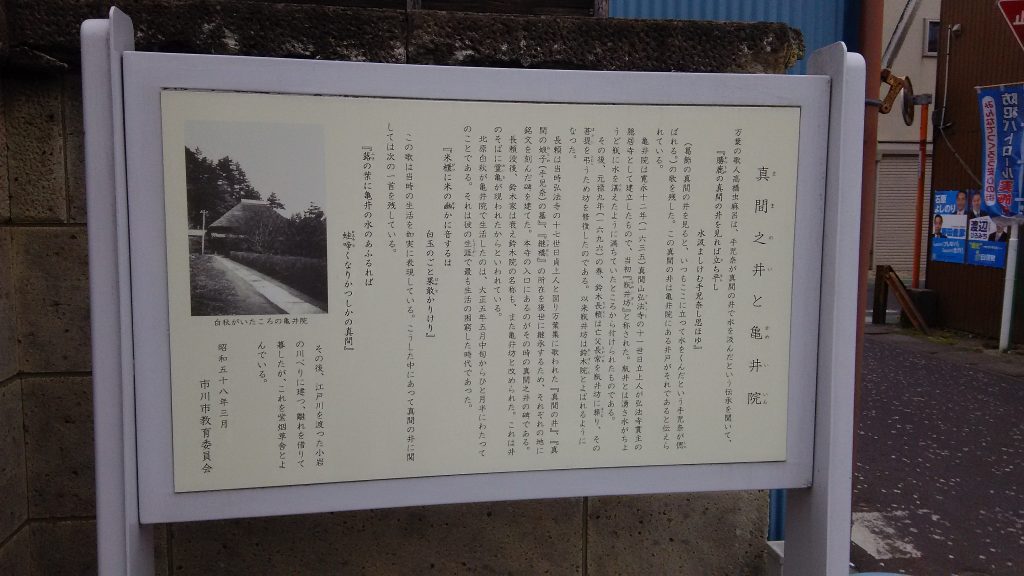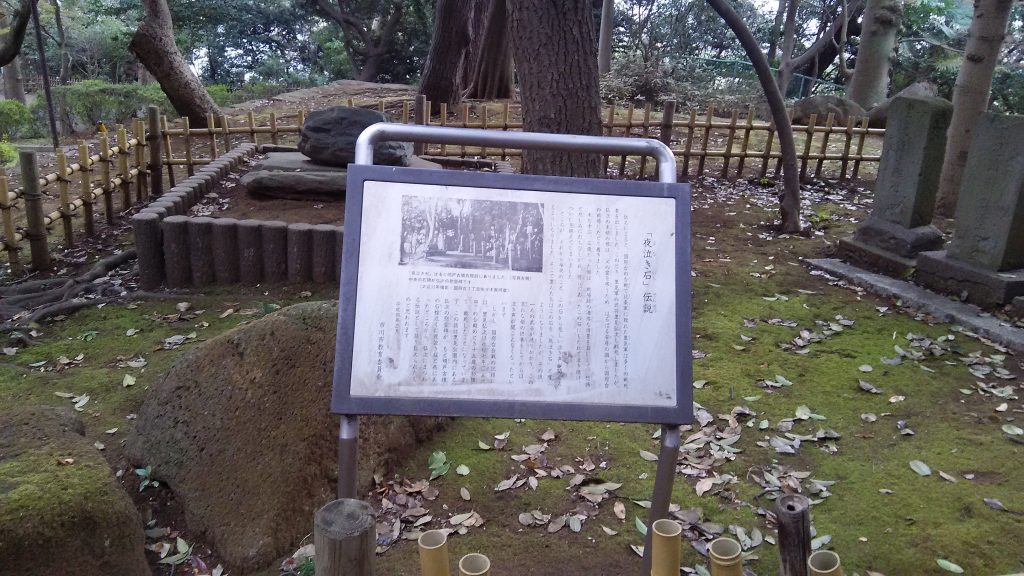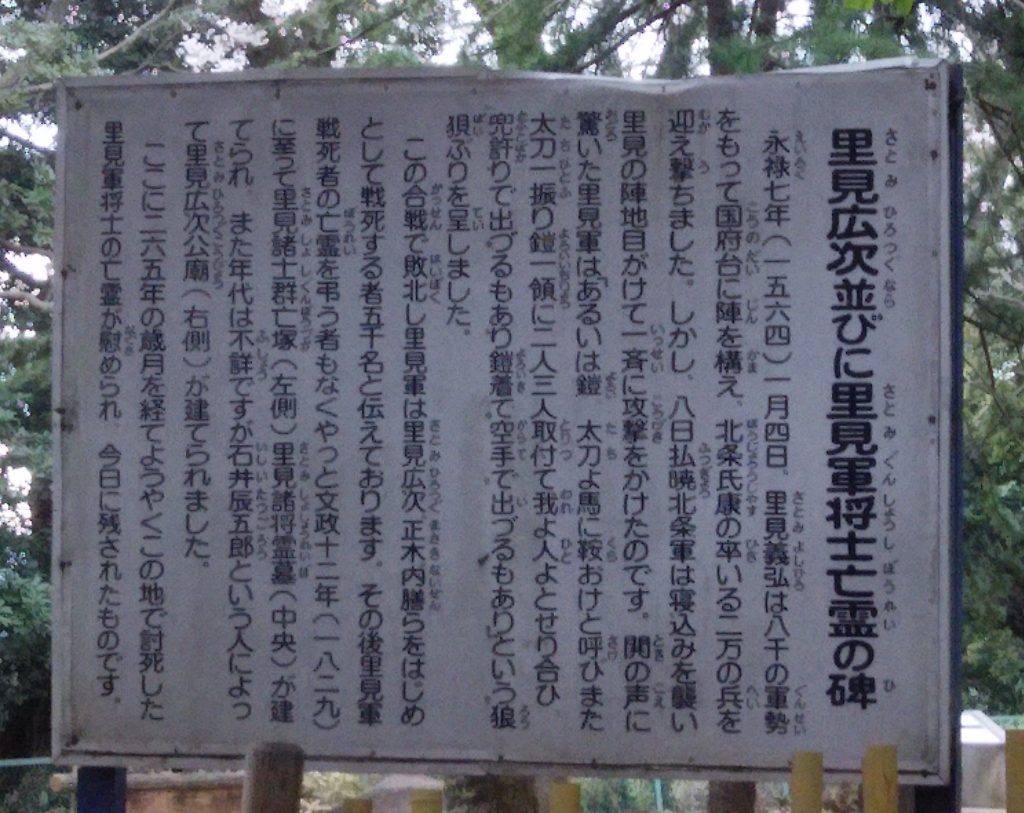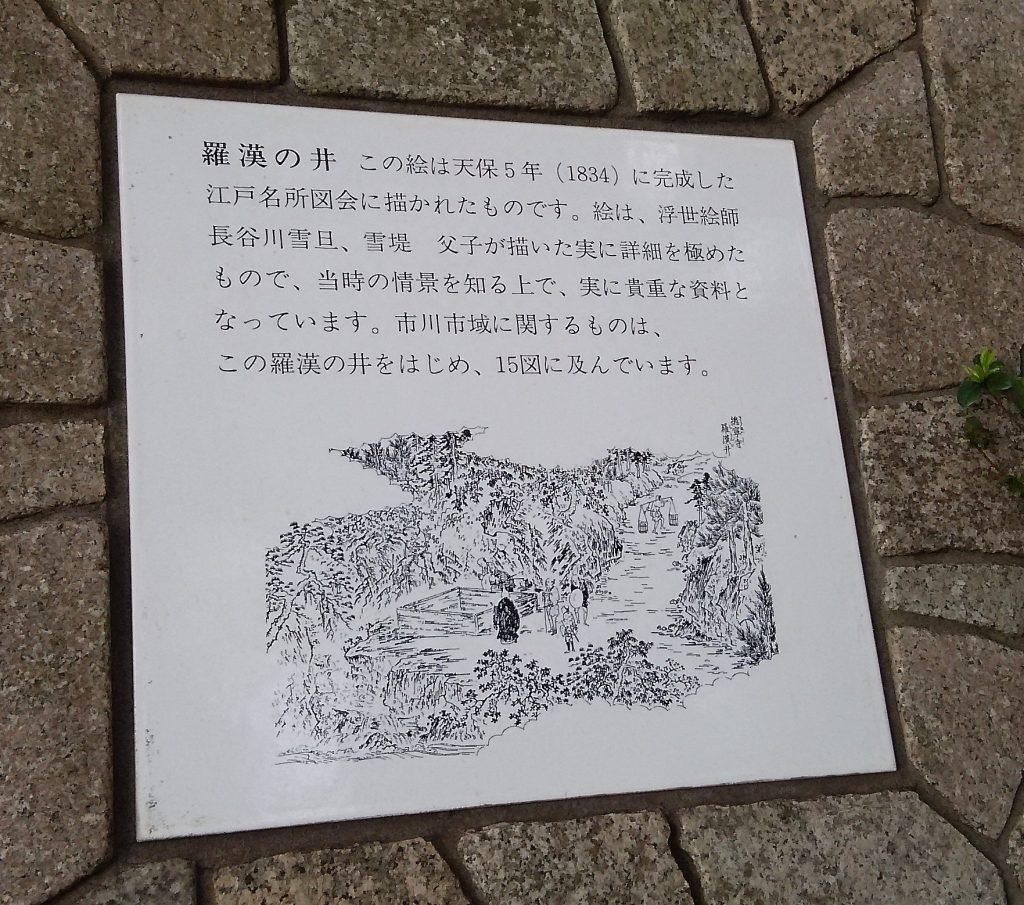映画『人生タクシー』からは、イラン映画を観て、イラン関係の本を読み、国立博物館へ行き、さらにトルコ映画を観ることになった。流れは次のようになる。
イラン映画→『正倉院の世界 皇室がまもり伝えた美』(シルクロード)→迎賓館赤坂離宮→東京ジャーミィ(モスク)→トルコ映画
映画『人生タクシー』のジャファル・パナヒ監督の他の作品では『オフサイド・ガールズ』と『チャドルと生きる』を観る。『オフサイド・ガールズ』は、女性はスポーツ観戦が法律で禁止されているのであるが、サッカー大好きな少女たちが、男装して何んとか観戦しようとするが見つかってしまい兵士の監視下におかれる。イラン映画はイラン国の事情がわからないからドキドキしながら見てしまう。少女たちは黙ってはいないし、それに真面目に答える兵士との会話にユーモアさえ感じる。
すったもんだがあり、観る方は、もっと厳しいことになるのではと心配になるが、一件落着してほっとさせられたりもする。ラストは、予想外のことが生じる。初めは少女たちに同情して観ていたのにもかかわらず、兵士に、あなたたちの今までの苦労は何なのよ、それでいいの、と声をかけたくなる場面で終わるのである。田舎出身の兵士が、都会の少女に翻弄されているようでもあり、兵士も普通の若者であったという可笑しさにさそわれる。少女たちのサッカーに対する熱さは今後も続くであろう。サッカー大好き少年の映画としては『トラベラー』(アッパス・キアロスタ監督)というのもある。
『チャドルと生きる』は、なかなか事情が呑み込めないような展開である。黒いチャドルをまとう女性の行動が謎めいている。チャドルは原音に近いのはチャードルなのだそうで、半円形に仕立てられた一枚のヴェールである。イラン国内の女性は、人前では髪の毛と身体を覆う衣服の着用が義務づけられている。スカーフに丈の長いコートという着方をしている女性も多い。これらすべての総称が「へジャーブ」と呼ばれている。黒のチャドルの雰囲気はどこか謎めいていていて女性の行動も一層謎めく。
チャドルという歴史の古い衣服が、古い因習の重さをも表しているようで、それにに押しつぶされそうな女性が、一人でその殻を破るために右往左往しながらも前に進んで行く。女性の旅の規制など、女性たちが行動していく過程で予想のつかない現実があり、女性たちは何んとかそこを突破しようとしていて強い。
子供たちも自分の力で問題を解決しようと進む。そのひとつが『友だちのうちはどこ?』である。アッバス・キアロスタミ監督・脚本・によるジグザグ道三部作の一作目で、ジグザグ道は、映像の中に出てくる。このジグザグ道を主人公の少年は一生懸命走るのである。なぜ走るのか。教室で隣に座った同級生のノートを間違って持って帰って来てしまったのである。その子は、宿題をノートではなく他の紙に書いて先生に注意され、三回目は退学だと言われている生徒である。このノートがないと三回目になってしまうのである。
ノートを届けるため少年は走る、走る。そして友だちの家を探すのである。イラン映画はフェイントをかけられるところがあり、えっ、どうしてという箇所がある。それが次の展開ではホッとさせられるという状況になったりもするのであるが、この映画も、ハラハラ、ドキドキさせられながら、主人公の考えた行動に納得させられるのである。
『柳と風』(脚本・アッバス・キアロスタミ/モハマッド=アリ・タレビ監督)、『運動靴と赤い金魚』(マジット・マジディ監督)も同じように子どもの一生懸命さに観る側の背筋が伸びる。もっと厳しい環境の中で生きている子供たちの映画もある。
映画からはどんな環境にあっても子供たちに勉学に励んでもらいたいという大人(映画人)の願いを感じる。字の読み書きができない大人も多かったのである。踊るようなペルシャ文字は魅力的である。
若者の映画では、音楽の世界に生きるドキュメンタリー風の映画『ペルシャ猫を誰も知らない』(バフマン・ゴバディ監督)がある。イランではコンサートなども許可制で、音楽も規制され、若者たちは逮捕されつつも自分たちの音楽を目指す。この映画ではイランで生み出される様々な音楽が味わえる。イラン人は詩を大切にし身近なものとしているらしく詩の世界に入りきれない映画もあるし、ミステリー映画もある。映画の事ばかりになり先に進まないので、観た映画名のみ記しておく。
『そして人生は続く』(ジグザク道三部作・二作目)・『オリーブの林を抜けて』(ジグザク道三部作・三作目)・『クローズアップ』・『ホームワーク』・『桜桃の味』・『バダック:砂漠の少年』・『風がふくまま』・『ダンス・オブ・ダスト』・『トゥルー・ストリート』・『スプリングー春へー』・『カンダハール』(イラン・フランス合作)・『私が女になった日』・『少年と砂漠のカフェ』・『1票のラブレター』・『少女の髪どめ』・『風の絨毯』(日本・イラン合作)・『ストレイドッグス~家なき子たち~』(イラン・フランス合作)『ハーフェズ・ペルシャの詩』(日本・イラン合作)・『彼女が消えた浜辺』・『別離』・『ある過去の行方』・『セールスマン』(イラン・フランス合作)
その他、イランの映画監督が外国で撮った映画で観た映画。『セックスと哲学』・『トスカーナの贋作』・『ライク・サムワン・イン・ラブ』(日本)・『独裁者と小さな孫』・『誰もがそれを知っている』・『明日へのチケット』
この続きは来年となってしまう。紅白はたけしさんの『浅草キッド』だけ聴きたかった。シンプルでよかった。ひばりさんは古い映像で工夫してほしかった。人工的で悲しくなった。あとは音を消して映像をチラチラ眺めていた。歌を聴くよりもそちらのほうが面白かった。