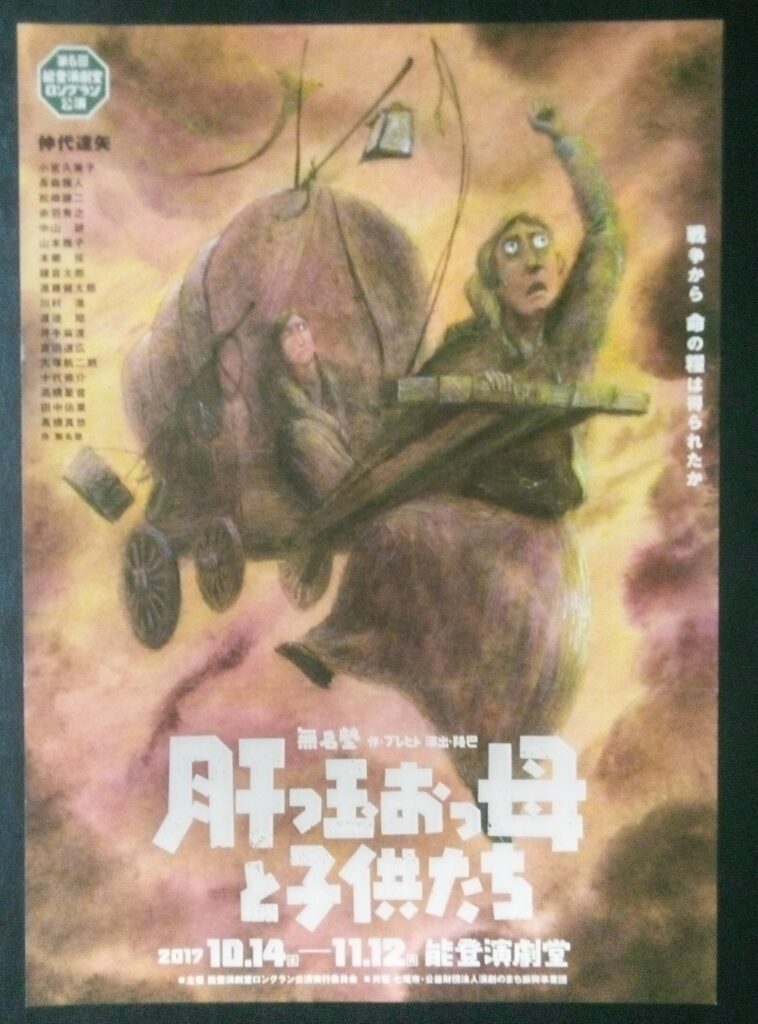- 猿之助さんが亀治郎時代に井上ひさしさんの芝居『雨』に出演していた。実際には観ていないがテレビの録画があった。一度挑戦したが10分ほどでやめてしまった。猿之助さんは今月は法界坊という汚いなりの役であるが、こうした役は『雨』以来だという。そうなのである。汚いなりで亀治郎さんは聞き役であまりしゃべらないのでそれで止めてしまったのである。ここから膨大なセリフとなる。江戸から<金物拾いの徳>は、山形に行く。その土地の方言を寝る時間を割いて練習し、違う人物の特性を知り身に着けるために必死となる。その努力は死への道であった。
- 予定外に早く予想しなかった死がやってくるのであるが、或る面では人の生きるということもそういうことであるようにもみえる。ただ怖いのは徳だけ知らないで周りは皆、徳の死のために動いていたのである。自分たちが生きるために。集団の同調する怖さでもあり、そしてそうしてしか生きていけない悲しさでもある。観客はラストになるまでそのことはわからない。その隠蔽さは観客にも見抜けないのである。それがまた怖い。言ってみれば観客もその一員になっているということである。
- <金物拾いの徳>は、自分は生まれながらの金物拾いでこれからもずーっと金物拾いであると思っている。両国橋下で徳は紅花問屋の主人・喜左衛門と人違いされる。徳は相手にしないが、その男は信じて疑わない。あなた(喜左衛門)が急に居なくなって、美しい女房のおたかさんもあなたの帰りを待っているという。<美しい女房>。これに徳はまず魅かれる。ちょっと行ってみようかとでかける。途中徳を悩ませるのは方言である。行く土地、行く土地で違い、語尾になにかをくっつければよいのかなと思えばそんな単純なことではなかったりする。
- 羽前平畠藩に入り、やはり帰ろうとすると乳母が現れ喜左衛門さんだといって大喜びである。乳母が疑わないのならと徳は天狗にさらわれて言葉も頭のなかも奪われてしまったことにする。女房・おたかも喜び、周囲もやんやと騒いで寝屋へと送り出される。ここで人違いとばれるであろうと徳はひやひやするがなんとか通過することができる。最初徳はなり澄まして金目の物を持って逃げようとするが、いやいや待て、おたかのいるこの生活を続けたいとおもいはじめる。疑っているものは多い。そのための努力は惜しまない。このあたりは健気な徳である。
- しかし、正面から邪魔立てする人間があらわれる。徳はその人間を消していく。喜左衛門には深い仲の芸者がいて、徳が喜左衛門でないことを見抜くのである。そしておたかが違う人であると知っていながら自分をかばってくれたことを知る。そのおたかに徳はますます情愛を感じていく。ここも重要な罠の一つだったのである。徳と同じように観客にもその罠はわからない。(わたしだけで他の人はわかっていたかもしれない)紅花の造り方の極意も知り、徳を喜左衛門その人であるとおもう人がほとんどとなる。
- 徳に知らされていなかったことがあった。徳が喜左衛門と会ったとき「俺は殺されない」というようなことを言っていたので、あれ!と思った。徳は気がつかない。それは喜左衛門が切腹することを定められた人なのだという事である。すべてはそこに集約されていたのである。それを知った徳は、自分は喜左衛門ではなく徳だという。ところがそれを証明してくれる人は、徳が自分ですでに消していたのである。
- 喜左衛門(徳)が死んで、弟(喜左衛門)がおたかと結婚することになっていたのである。感想で猿之助(亀治郎)さんが、本物の喜左衛門が死んで徳が生きててもいいかもといわれたが、私もそう思った。徳は努力に努力をして言葉も喜左衛門の頭中も手にするのです。その一途さが愛すべき徳となっているのである。徳がなぜと思うようにこちらも、それはないでしょうとおもってしまった。すべておたかに対する徳の気持ちから端を発していて、おたかの情愛と信じていた徳である。ところがおたかはもっと広い人間関係である藩や農民を集約した代弁者であり実行者だったのである。
- <金物拾いの徳>は金物を見つけるとすかさず拾った。<喜左衛門の徳>は、<金物拾いの徳>の習性さえも捨ててしまっていた。拾わなかった五寸釘に刺されてしまう。たかは死んだ徳を抱きかかえ、あなたのことは一生忘れませんというのである。こちらは徳の気持ちになって、御冗談じゃない、死んでからまであなたに操られたくない思ってしまった。でも、徳はそれで満足するかもしれないなあ。自分では想像もしていなかった人間になれたのだから。能であれば、亡霊がでてきて語るのであるが。徳は<金物拾いの徳>が本物なのか<喜左衛門の徳>が本物なのか。ただ<喜左衛門の徳>は、周囲から上手く誘導されて作られた徳であることは確かである。
- 徳の亀治郎さんは、やはり歌舞伎役者の亀治郎さんであった。もう歌舞伎役者に作られた身体表現なのである。歌舞伎役者がやるものは全て歌舞伎であるというゆえんがわかる。この芝居は江戸時代の話しなので特にそれが顕著であった。しかしそれは良い方に生かされ、世話物の上手さが出ていた。次から次へとためされる場面が続くが飽きさせないだけの巾があった。おたかの永作博美さんは明るくてこんな人がだましたりはしないとたかをくくって騙されてしまった。井上作品の唄とそれに乗った動きも、このにぎやかさにも騙されたことを後で知る。
- 方言が一つの地域の約束ごとでそのことが結束を固めていることも改めて感じる。外から観るとそれは可笑しさも誘うが、中に入るものにとってはバイブルのようなものである。そういえば、徳が死ぬ場面の後ろの梁と柱は十字架のようにもみえた。よそ者を誘い出し中に入らせて犠牲としたのである。色にふけったばっかりには結構あちらこちらにあるわけである。この芝居が気になっていたので片づけられてよかった。徳の双面であった。井上ひさしさんはこの若き新しい舞台を観ておられないのである。残念。(2011年上演)
作・井上ひさし/演出・栗山民也/音楽・山田貴之/出演・市川亀治郎(現・猿之助)、永作博美、山本龍二、山西惇、たかお鷹、花王おさむ、梅沢昌代、etc