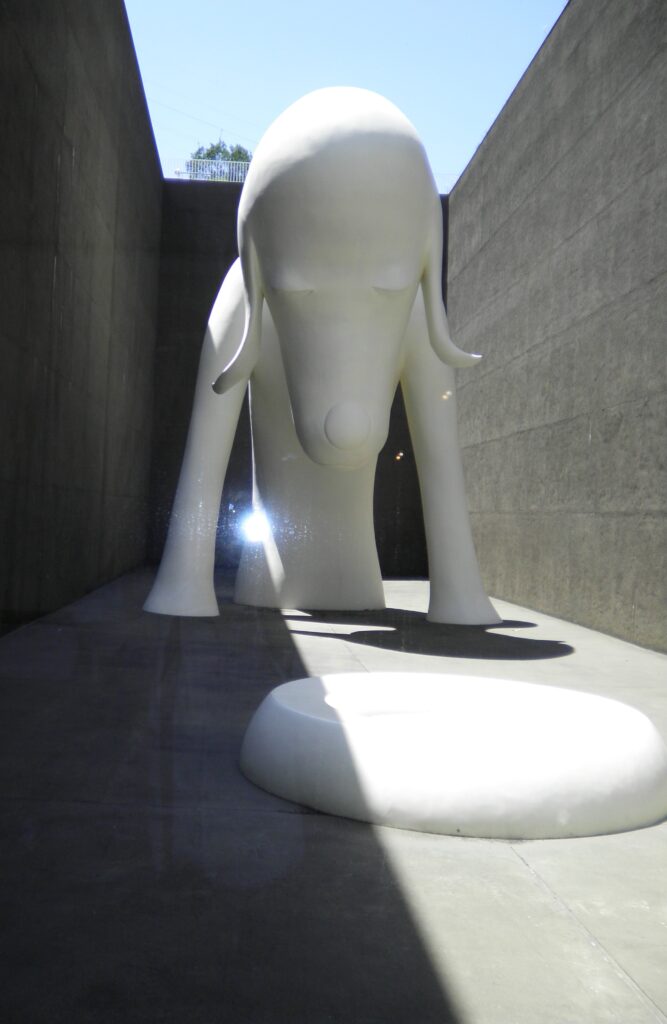鹿鳴館の設計者であるジョサイア・コンドルと絵の師である河鍋暁斎のジョイント展覧会である。開催されている<三菱一号館美術館>はコンドルの設計したときの建物の解体後に再建されたレプリカである。
展覧会には、鹿鳴館の階段の一部が切り取られた形で展示されており、暁斎の<河竹黙阿弥作「漂流奇譚西洋劇」パリ劇場表掛りの場>の行灯絵があり、明治の一部分も見せてくれる。
河鍋暁斎さんのこと、そして、ジョサイア・コンドルさんとの関係を知ったのは 河鍋暁斎とジョサイア・コンドル (1) からである。
そのあと、埼玉県蕨市にある『河鍋暁斎美術館』も訪ねた。今回の展覧会は、師弟二人の作品が観れるわけである。
コンドルさんは建築家でもあるので設計された図もあるが、こちらの興味は絵と、日本舞踊家であった奥さんと踊られた時の『京人形』の時の写真などである。京人形の扮装のくめさんの指に三つほど指輪をしているのが面白い。コンドルさんも彫り師の扮装である。『鯉の図』の鯉の目を見て、金目鯛の目を思い出す。これは、谷崎潤一郎さんの『春琴抄』のことに関係するのであるが、後日書くこととする。暁斎さんの<鯉>の絵は口を開けていてその口の強調と詳細さ、水を動かして泳ぐ律動感ある水面の描き方などに惹きつけられるが、コンドルさんは、穏やかな絵である。
暁斎さんと旅を共にし師の絵を描く姿を描かれているが、絵も描書き方もスケッチということもあるのか、絵の中の暁斎さんも力の抜かれたもので、狂画師の趣きはない。
暁斎さんのほうは、才能のほとばしりが感じられ、展覧会での解説でもかつては評価が難しかったとある。美人画なら、美しく描けばそれで評価の高い作品となる腕があるし、そうした作品もある。ところが、それだけでは暁斎さんはあきたらない。美人の眺める先には沢山のカエルが描かれていたり、美人のそばに飾りものではない動物の姿が加わっていたりする。美しい太夫も『閻魔と地太夫図』となる。
鳥花図や自然の中の動物も、生きて行くための狩りや弱肉強食の世界がある。花が美しく咲き、うさぎがそれを愛でていると思ったらその下には蛇が頭を持ち上げて待ち構えている。鷲がゆうゆうとその雄姿を誇っていると思うと、その下では、猿が頭を抱えて震えている。赤い柿を狙う鴉。蛙を口に咥える猫。戸隠神社の中社の帰りに出会ったという生首を加えた狼の絵。
そうかと思うと、楽しい鳥獣戯画的作品がある。『風流蛙大合戦之図』『猪に乘る蛙』など。
さらに、『鷹匠と富士図』は、鷹を手に、富士を眺めている穏やかな鷹匠の後姿。子供が盥に入れた金魚と遊びその後ろで木に縛られた亀が何んとかして逃れようとしている絵。あらゆる感情を喚起してくれる絵の数々である。
コンドルさんは、噺家の圓朝さんの落語を書き起こしていたが、暁斎さんの幽霊の絵は『牡丹灯籠』の新三郎にまとわりつく幽霊のお露さんを見たという伴蔵の話しから想像する幽霊を思い出す。美しいのとは反対のあばら骨の見える恐ろしい姿である。こちらも『牡丹灯籠』は読み終わったのだが、新三郎の住んで居た根津の清水谷はどの辺りかと思っていたところ根津神社のすぐそばらしい。本に地図があったので、森鴎外さんの作品散歩の時、二つ合体で楽しむこととする。
鴎外さんが大正6年に総長となった帝室博物館の東京帝室博物館はコンドルさんの設計で、この時はまだ現存している。関東大震災で崩壊してしまう。この大正6年に竣工したのがコンドルさん設計の、古河虎之助邸で、現在の旧古河庭園にある洋館である。
暁斎さんもコンドルさんも多くの現物が失われているが、残されているもので今も、まだまだ楽しませてくれている。暁斎さんは観るたびに、どうしてこの作品からこの作品に飛ぶのかと、その腕と想像と創造力に呆れさせてもらっている。分類、分析などを超えたところに暁斎さんの楽しみ方があるように思う。