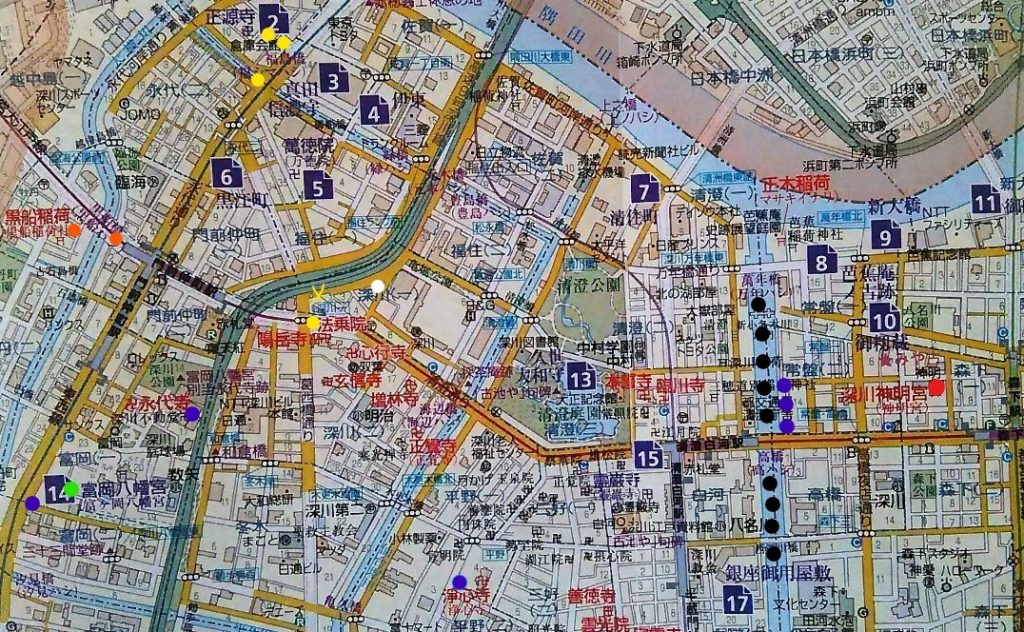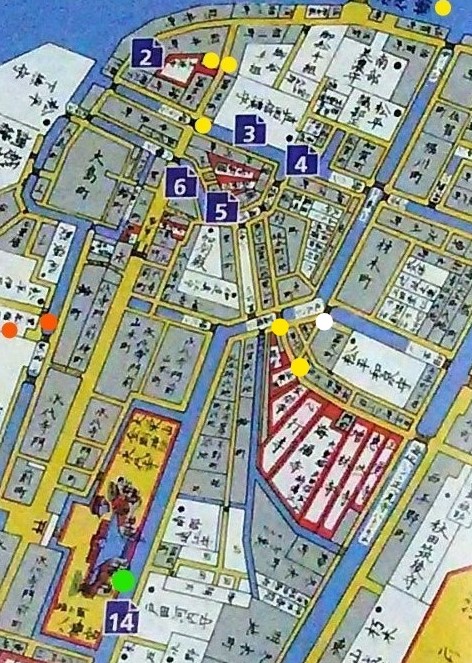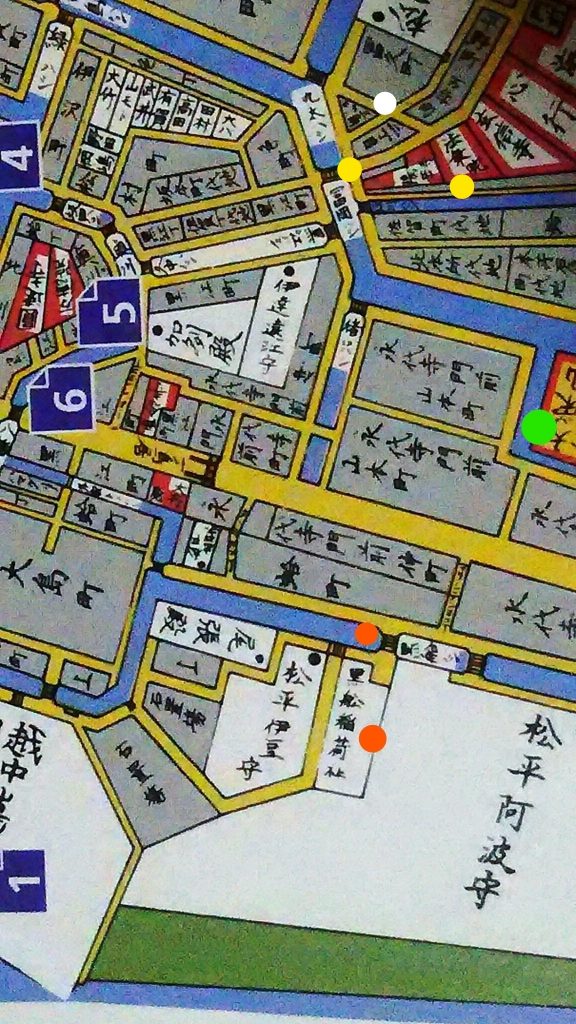さてもさても南北さんの深川から木挽町の歌舞伎座へと飛びます。歌舞伎座では6月から南北作品が続いています。人気者はお忙しいです。今回の作品は、この時期ならではの上演形態によりすくいあげられた作品といえます。
三代目猿之助さんの選ばれた四十ハ撰の家の芸の中に『天竺徳兵衛新噺(てんじくとうくべえいまようばなし)』があります。これは南北さんの『天竺徳兵衛韓噺(てんじくとくべえいこくばなし)』と『彩入御伽草(いろえいりおとぎぞうし)』を合体させて新たな作品としたようです。
今回は『彩入御伽草』よりとあり、小平次が殺されて化けて出るという怪談話の部分をとりだして「小平次外伝」となっているわけです。言ってみれば南北さんお得意の怪談物のケレンということになります。
小平次(猿之助)は巡礼の旅にでていたのですが、気にかかる夢をみて途中で帰ってきます。帰ってみれば、突然、馬士・多九郎(巳之助)と医者・天南(猿三郎)に毒を飲まされるところでした。多九郎は小平次の女房・おとわ(猿之助)といい仲になっているため小平次が邪魔なわけです。そこで、医者・天南に毒薬を頼んでいたのです。
ところが毒薬と小平次にバレてしまったので、こんどはこん棒で殴って沼に落とすのです。苦しみながらも小平次は浮かび上がります。何回も。しつこいくらい何回も。
しつこいと言えば小平次の妹・おまき(米吉)が尾形十郎(松也)に惚れてこれまたあきらめることなくしつこいのですが、これには笑えました。そして、妹の口から出た言葉で、小平次は幽霊となってあらわれるのです。ここは上手くつながっていました。納得です。ここから小平次の怨念がはじまります。
『東海道四谷怪談』で伊右衛門が悪人なのに色悪といわれるように、おとわは悪婆といわれる役どころです。
南北さん指にご執心です。おとわは夫の小平次が杭につかまっている指を切り刻むのです。悪い人間はいるものです。一番ワルなのは小平次の女房・おとわです。これでは小平次、簡単に成仏などできません。当然化けて出てきます。
どちらにしろ小平次は復讐しないわけにはいきません。小平次の幽霊とおとわの早変わりは楽しかったです。蚊帳を使っての早変わりなのですが、そういえば、『東海道四谷怪談』でも蚊帳は重要な役目をしていました。怪談ものは夏ですからやはり道具立てもそうなりますかです。
猿翁さんの著書『猿之助の歌舞伎講座』によりますと、小平次がこん棒で殺される場面では、小平次は泥だらけになっています。おとわが指を切ると、血が噴き出るようにしていました。やはり今の状況では制限が多いのでしょう。
それでも小平次が何回も浮かび上がるところは、もう少し工夫が必要だと思いました。回数が増えるごとに笑いが増えるようにし、おとわの指切りでぞくっとさせられるといいですね。
ケレンは観客の期待もあるので大変です。
お家騒動は背景にあるのですが、怪談が主ですから役者さんにとってはセリフが、解説になってしまってはいけません。そこが場面を取り出しの芝居の難しさでもあるようです。どんな芝居もセリフの交流の面白さは必要です。
「小平次外伝」、これからも出番が増えるような気がしますし、さらなる工夫でまた観たいです。お家芸が四十ハ撰もあるのですから四代目猿之助さんも継承に奮闘中です。
奴・磯平(男寅)、小平次の父・正作(橘三郎)、庄屋・満寿兵衛(寿猿・役名にくふうがあります)
話が飛びますが、小平次はお遍路姿ですから白の衣装です。これをみて「白のたたりだ。」と思いました。前の夜、テレビドラマのDVD『謎解きはディナーの後で』をみていたのです。白い衣服のひとが次々ころされていくのです。それで白に反応してしまいました。やはり殺されました。ドラマはどこまでもおぼちゃまを守る女執事が面白かったです。
舞踊『俄獅子(にわかじし)』は、華やかで綺麗な舞台でした。吉原で芸者や太鼓持ちが仮装などをして踊り歩くという行事があったそうで、その雰囲気をあらわしています。最初は粋な鳶頭(松也)と傘をもった若者との動きで見せ、次に芸者(笑也、新悟)と鳶頭の踊りへと移っていき踊りおさめます。
松也さんはいづれ尾上松助を襲名するのでしょうが、初代松助さんが『天竺徳兵衛韓噺』の初演を演じて評判をとっていて、今回は縁のある作品出演ともいえます。今はしっかり身体で学ばれて積み上げていく大切な時期なのでしょう。踊りの芯を忘れないで欲しいです。
八月の『加賀見山再岩藤 岩藤怪異篇』の猿之助さんの配信を観ましたのでその話を少し。
舞台では巳之助さんの正室梅の方がちょっとと思いましたが、猿之助さんのは、多賀大領に疎まれているとのおもいと同時に、お家のことも心配する正室の立場がでていました。そのことによってお家騒動のふくらみが加味され、お家を守る側の人々も生きてきました。なるほどと思いました。
それにしても巳之助さんよく務められました。
八月の歌舞伎座での「骨寄せ岩藤」をみたとき、以前に観たときより骨が少ないのではと感じたのですが、『猿之助の歌舞伎講座』によると、計三人で糸を操っていたそうで、今回は人数減らしているのかもです。
とにかく少ない人数で、早くというのは今の時期の苦労なところです。ただおそらくこの経験が後に生きてくることでしょう。
巳之助さんへの要望ですが、鳥居又助と今回の多九郎で、三津五郎さんのセリフ術を学んで欲しいと切望しました。あの術は残してください。
何かが欠けても舞台は作れるのだの精神でケレン道の険しい道は続くことでしょう。
追記: 歌舞伎観劇の後、京橋の『国立映画アーカイブ』の『生誕120年 円谷英二展』へ。このフライヤーは東京芸大美術館でゲット、グットタイミング。イギリスで発掘された『かぐや姫』の一部映像もありました。円谷さんの生まれ故郷の福島県須賀川市に『円谷英二ミュージアム』ができていて、芭蕉さんが『奥の細道』で足を止めた場所がさらに光ってみえます。
円谷英二ミュージアム|tette テッテ 須賀川市民交流センター (s-tette.jp)
追記2: 『加賀見山再岩藤 岩藤怪異篇』での配信で数えましたが、猿之助さん、17回衣装替えしていました。それを支える係のかたたちも縁の下の力持ちですね。
追記3: 映画『怪異談 生きてゐる小平次』(1982年・中川信夫監督)、思いのほか早く観れました。南北さんの『彩入御伽草』には実在のモデルがあり、女房とその愛人に殺されたのは旅役者でした。鈴木泉三郎さんがそれらを新たに戯曲『生きてゐる小平次』とし、さらに脚色し映画にしたのが中川信夫監督です。登場人物は三人だけ。役者・小平次(藤間文彦)、狂言作者・太九郎(石橋正次)、太九郎の女房・おちか(宮下順子)。三人は幼なじみで、三人にねじれがはじまります。中川信夫監督ゆえに怪談物かなとおもうと題名通りちょっとちがうところがさらなるねじれです。
追記4: 中川信夫監督の『東海道四谷怪談』(1959年)をユーチューブで観れました。DVD購入しないとダメかなと思っていたので歓喜。これですっきりしました。やはり怖くて伊右衛門の心理も現代的。(伊右衛門・天地茂、お岩・岩杉嘉津子)
怪談物は、歌舞伎、講談、落語、映画、演劇ら、多方面のジャンルでそれぞれの力量の見せどころ、聴きどころで愉しませてくれます。能などは多くに亡霊が出現です。夏だけの風物でなくなってきています。