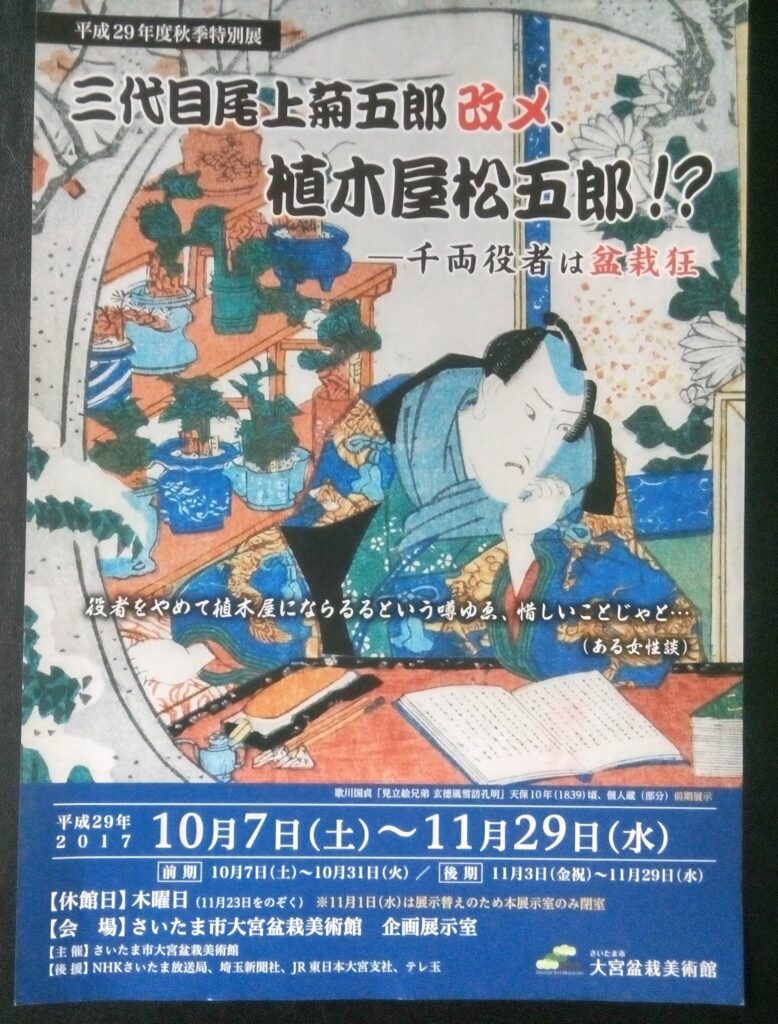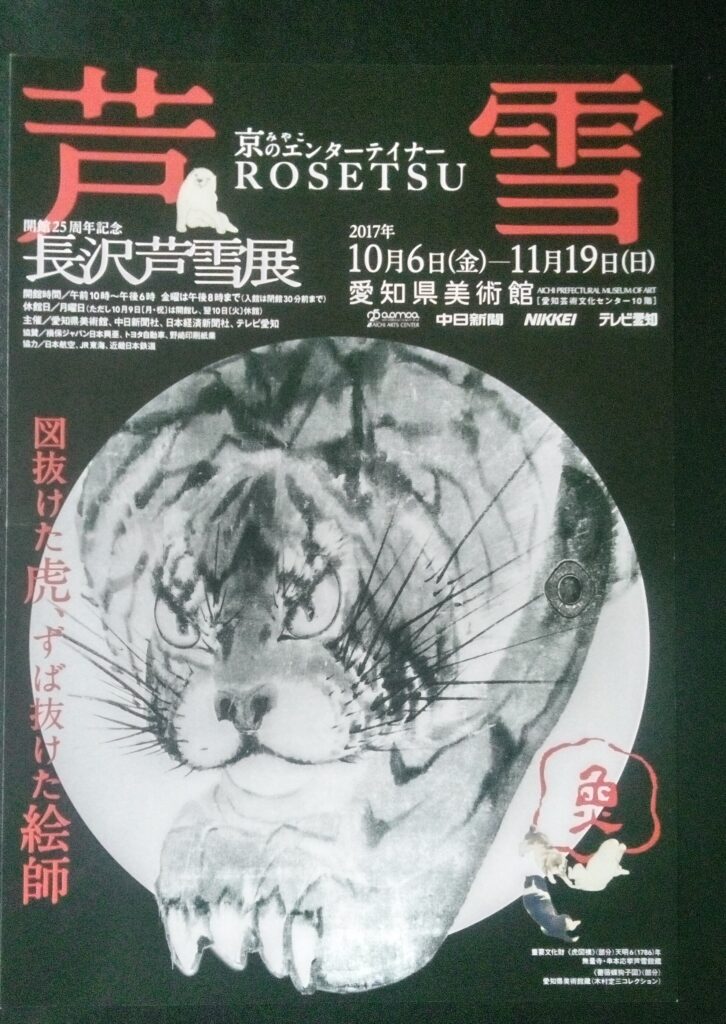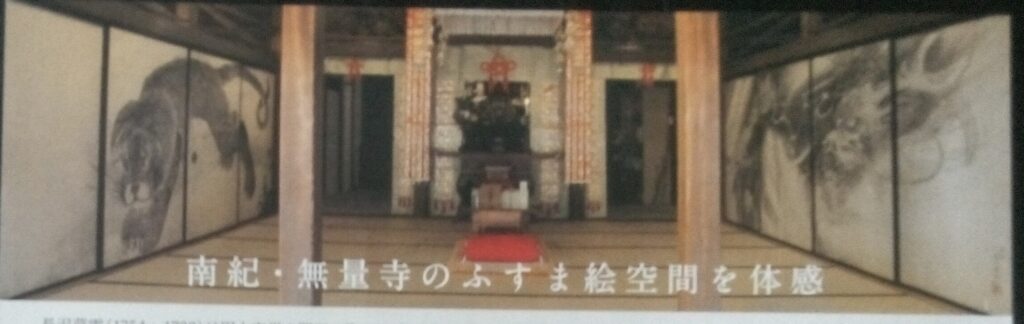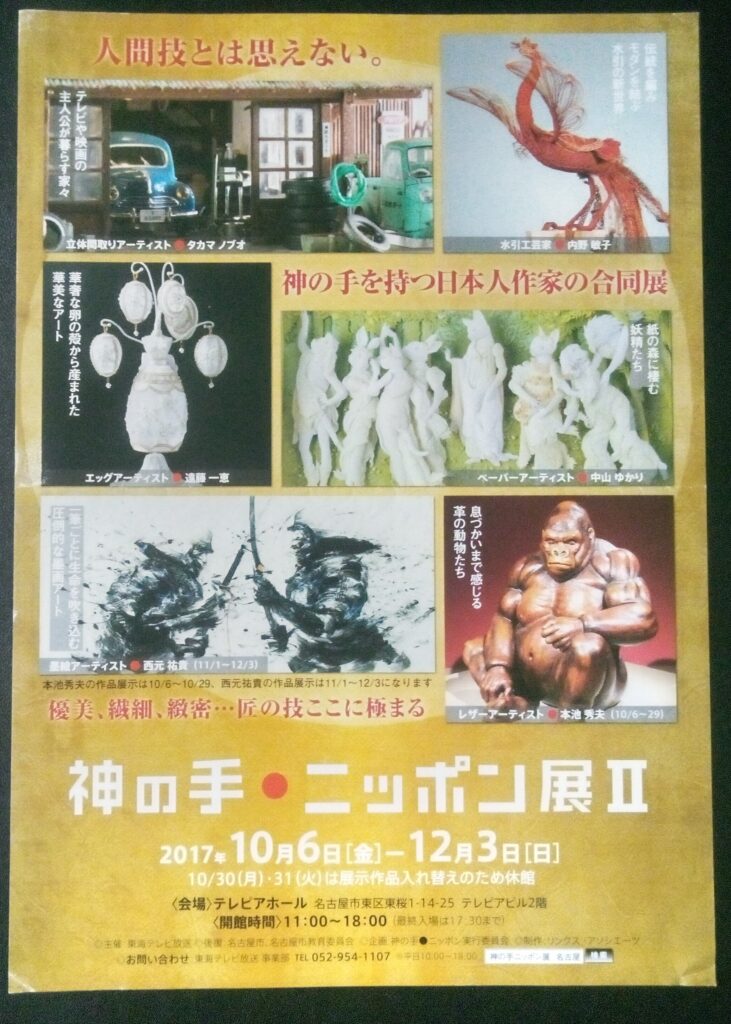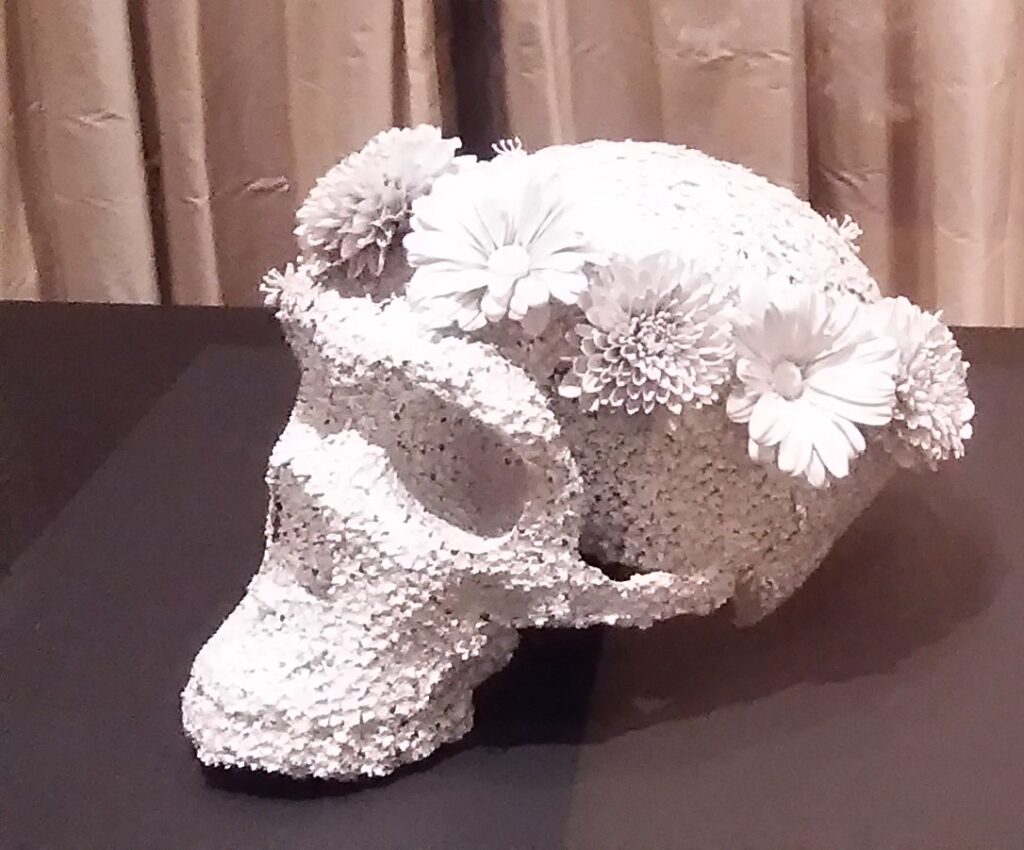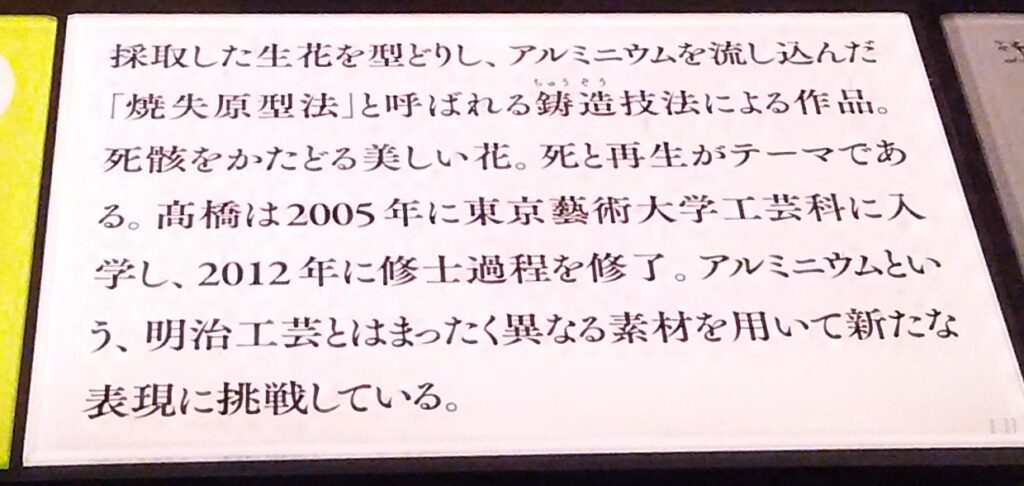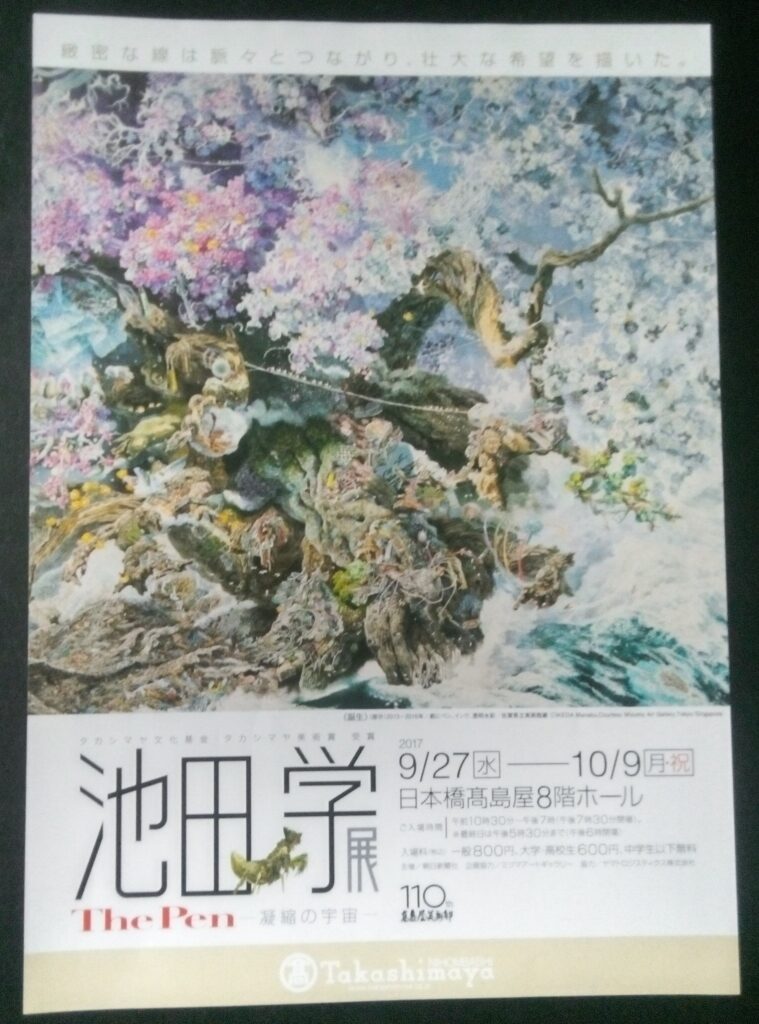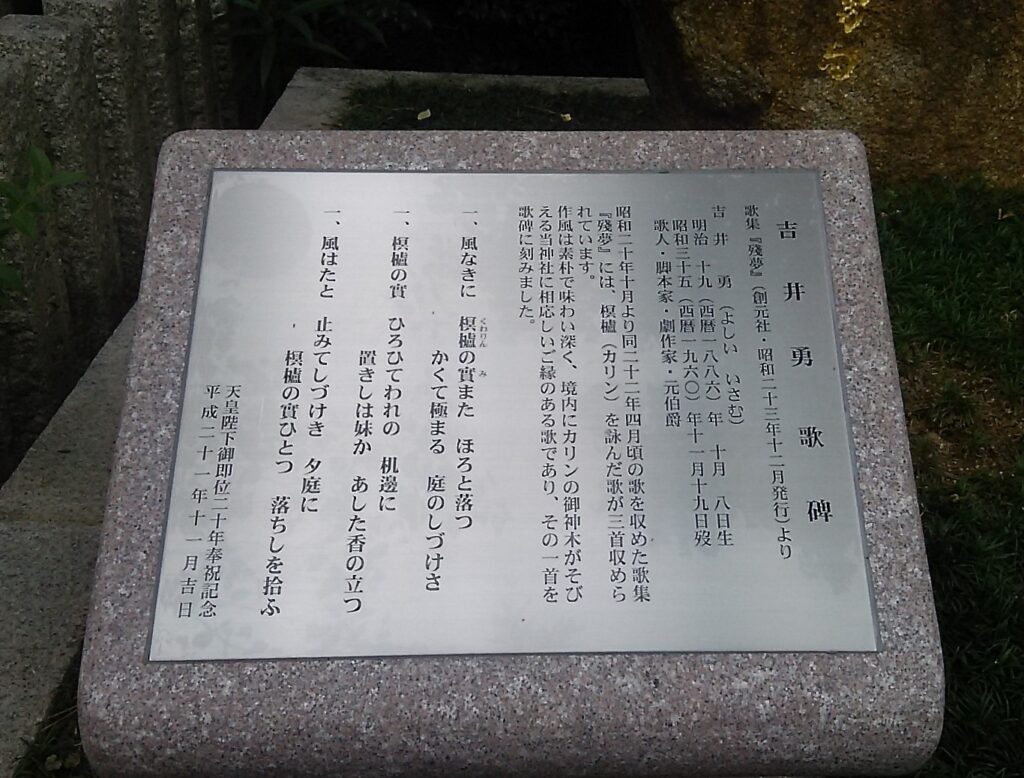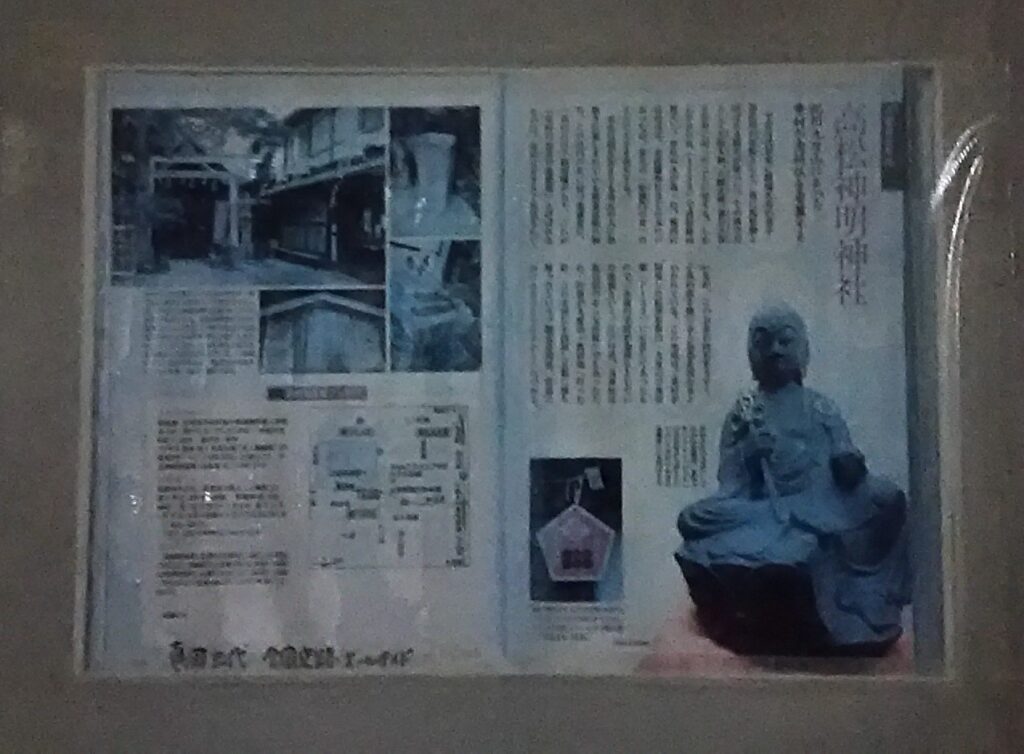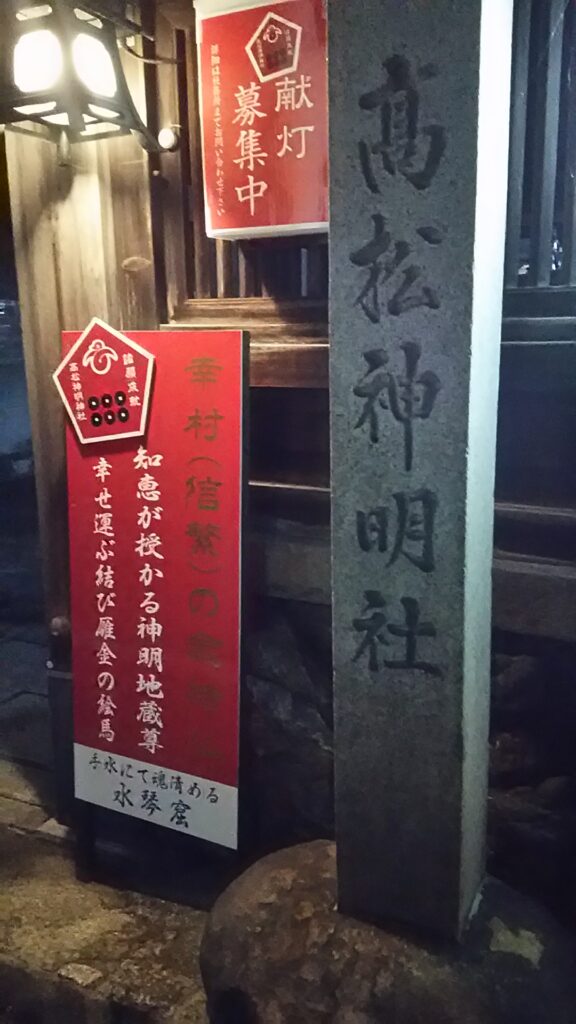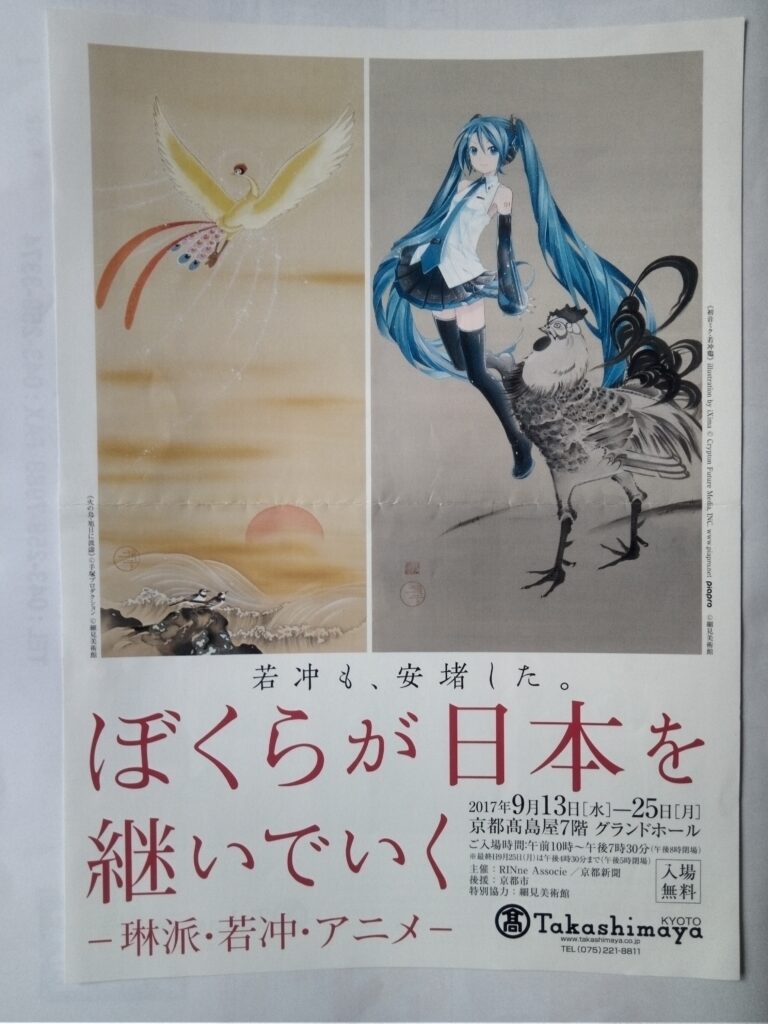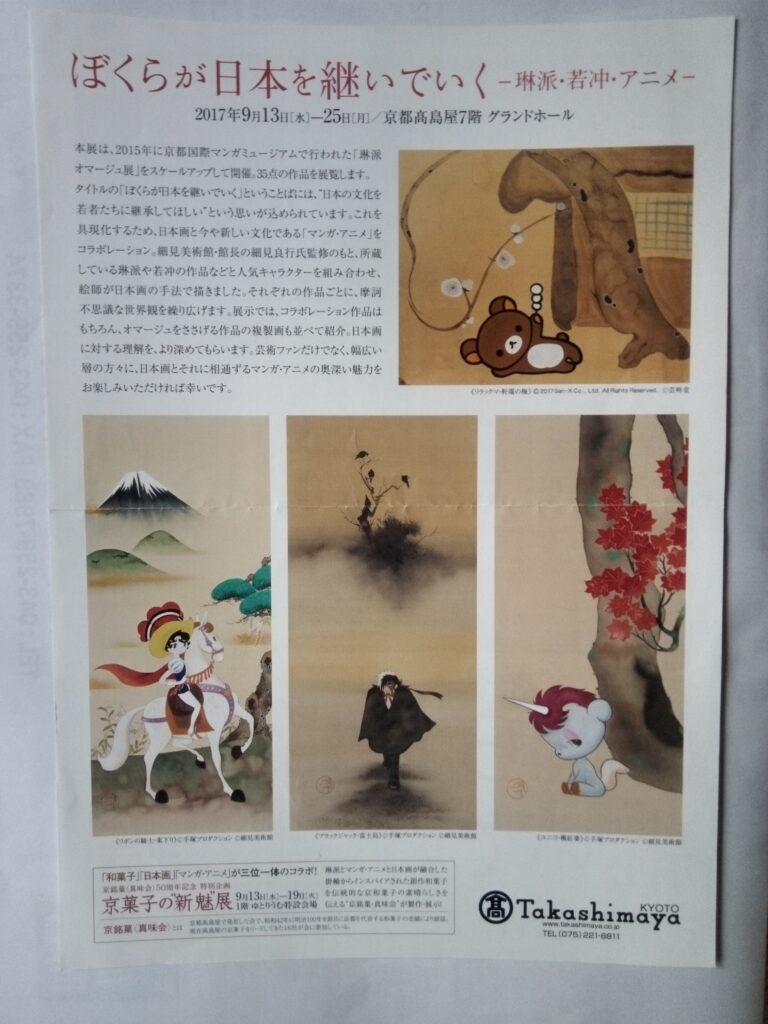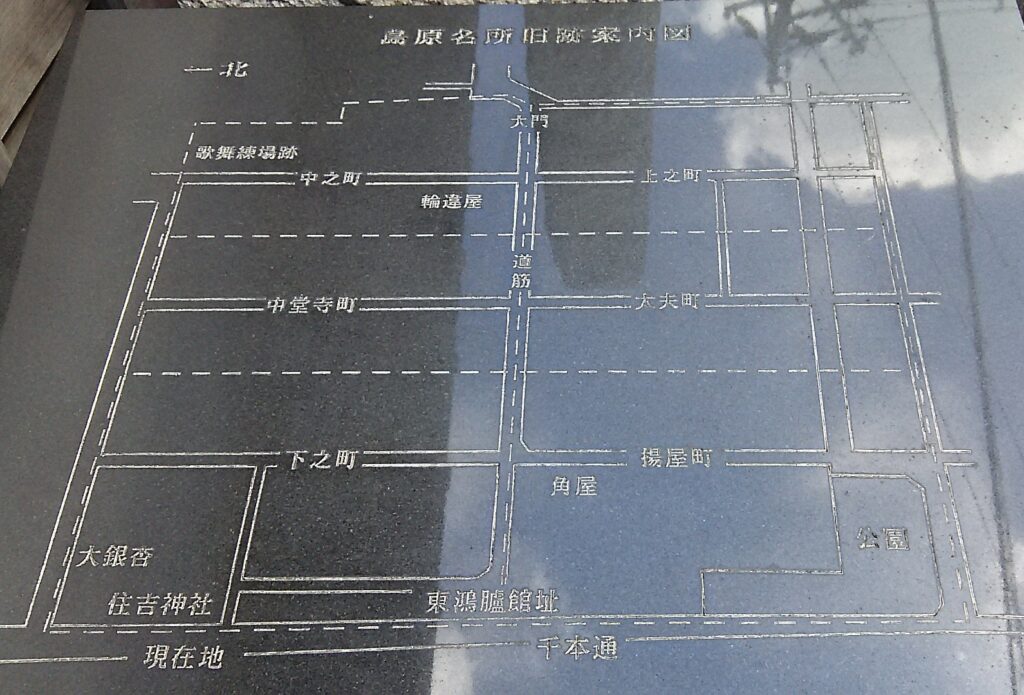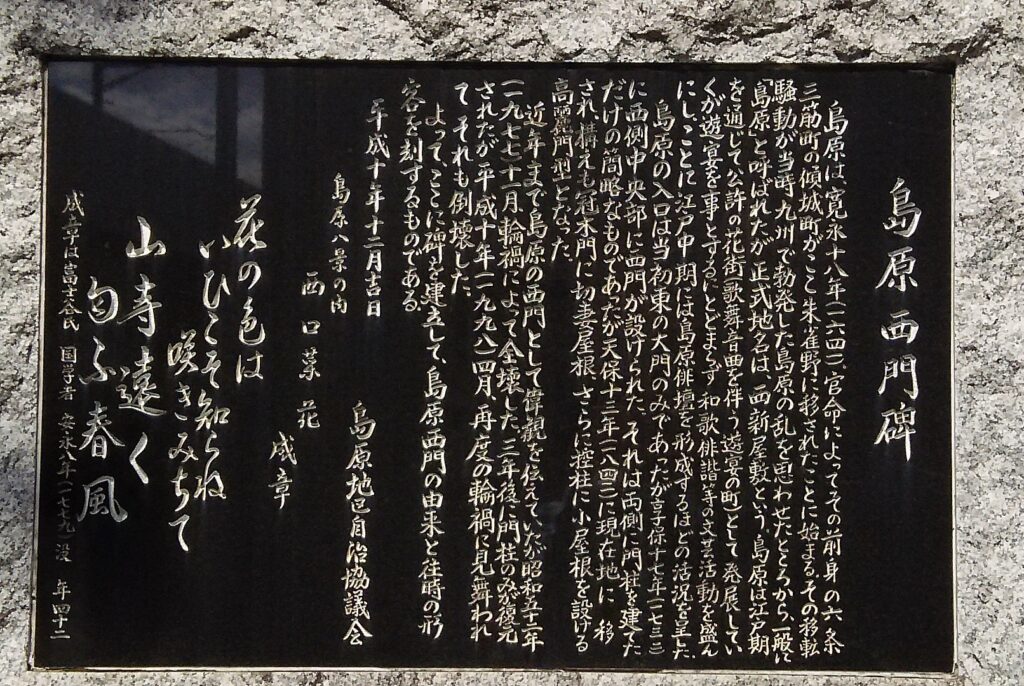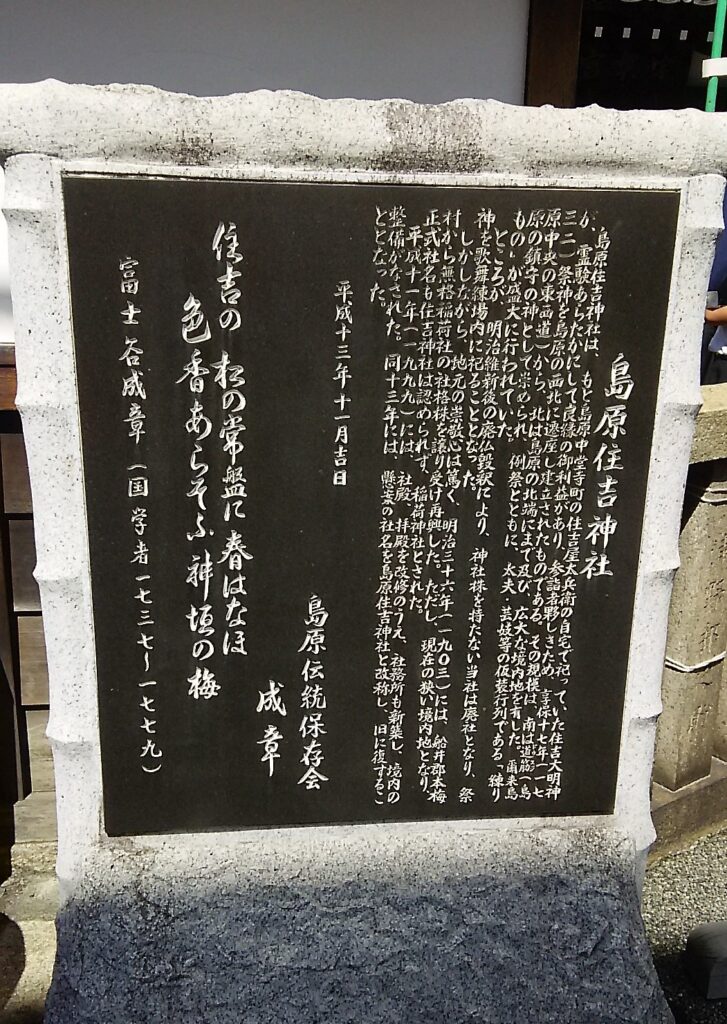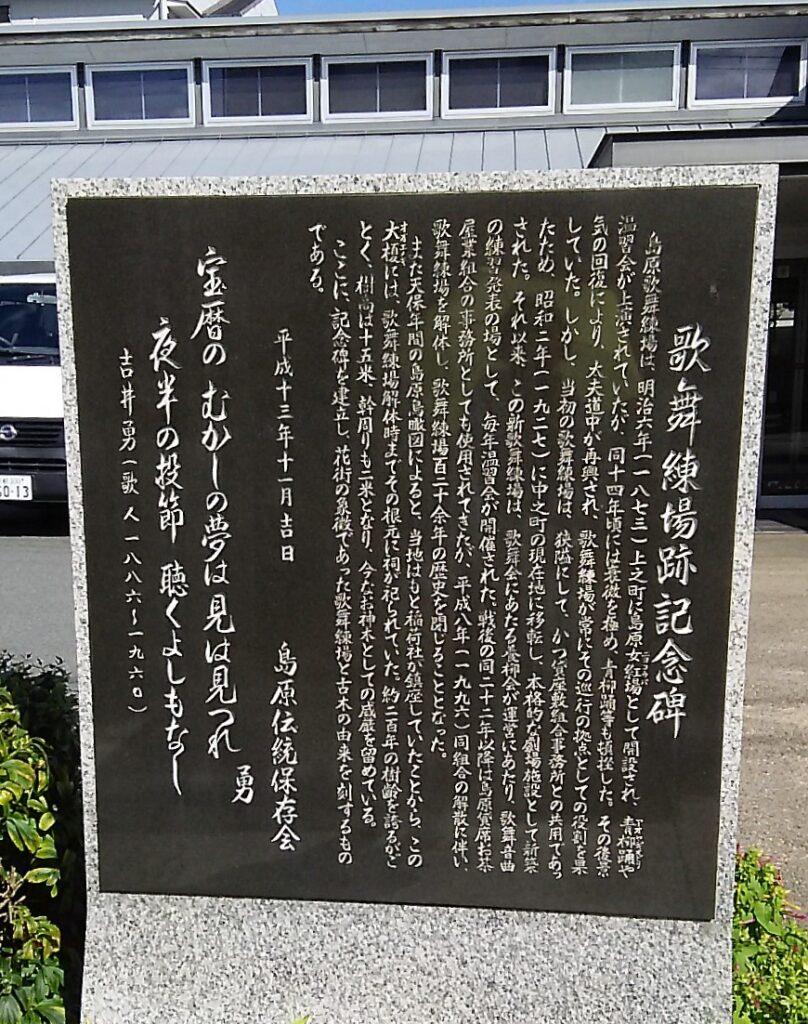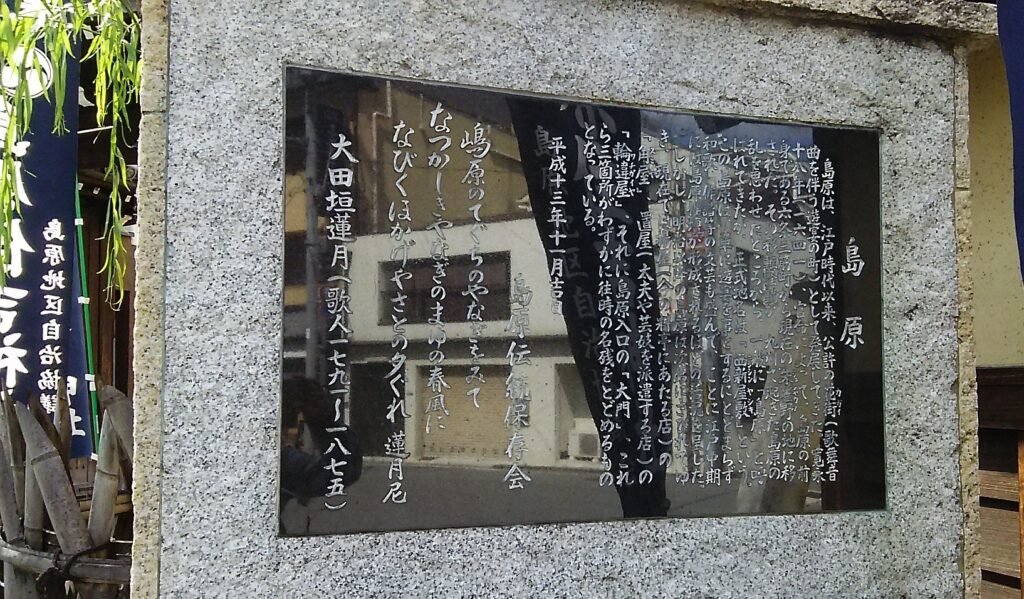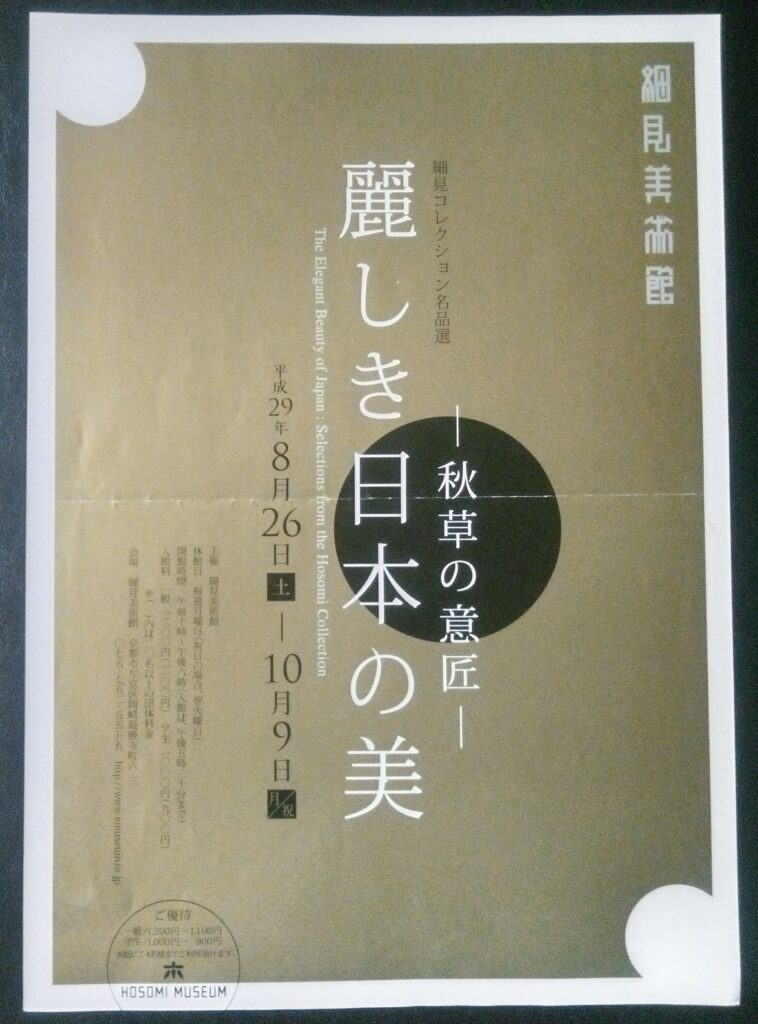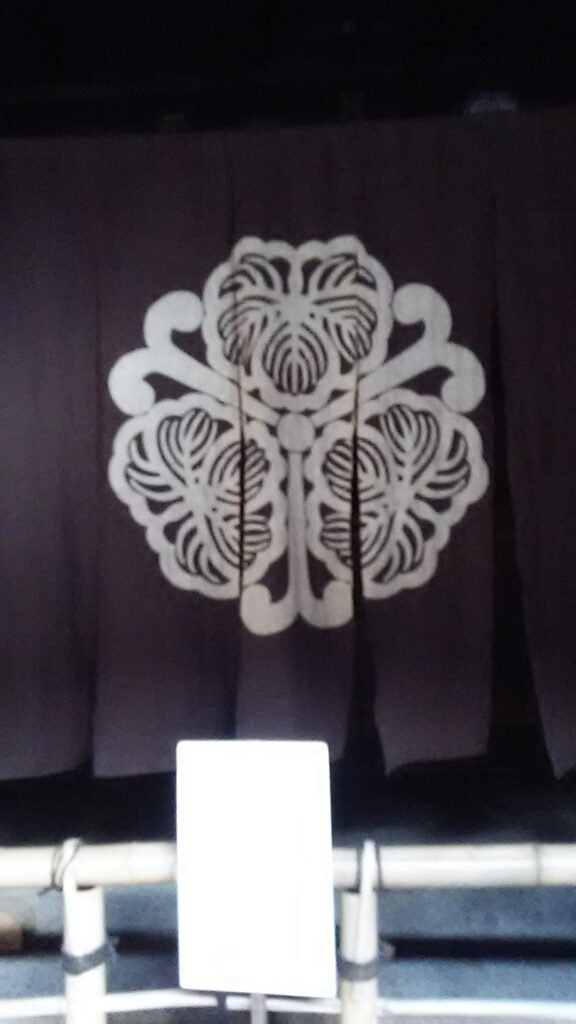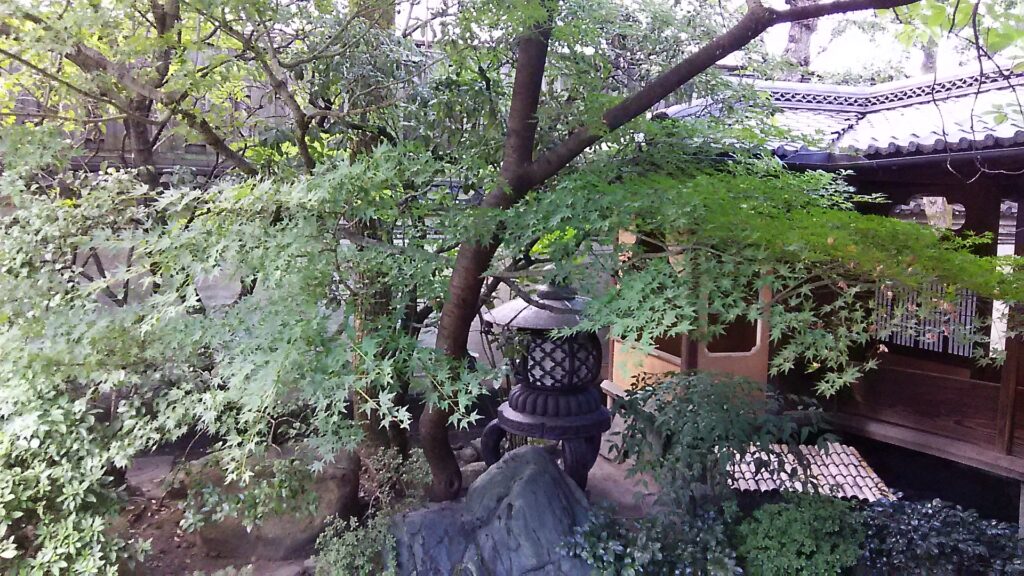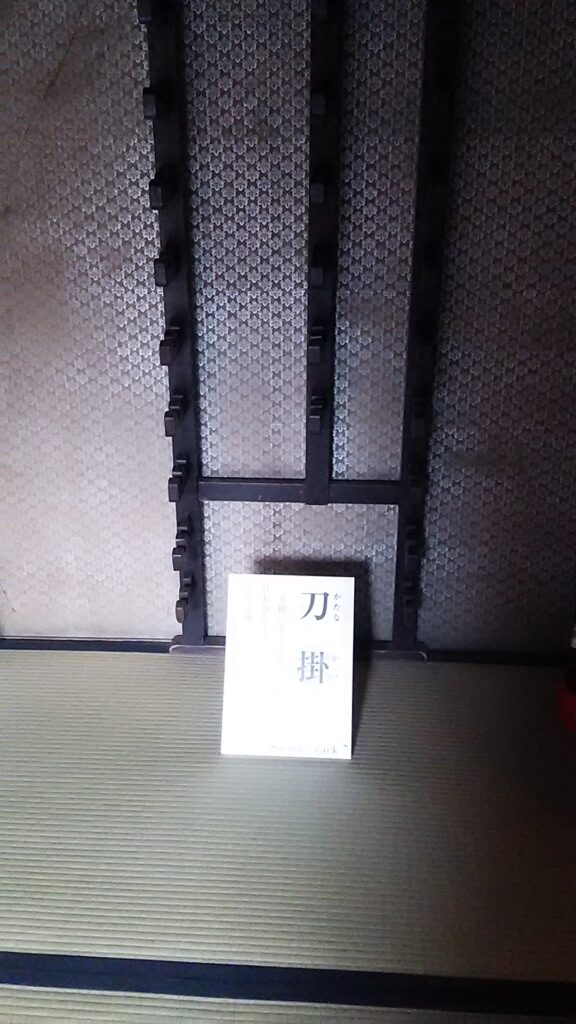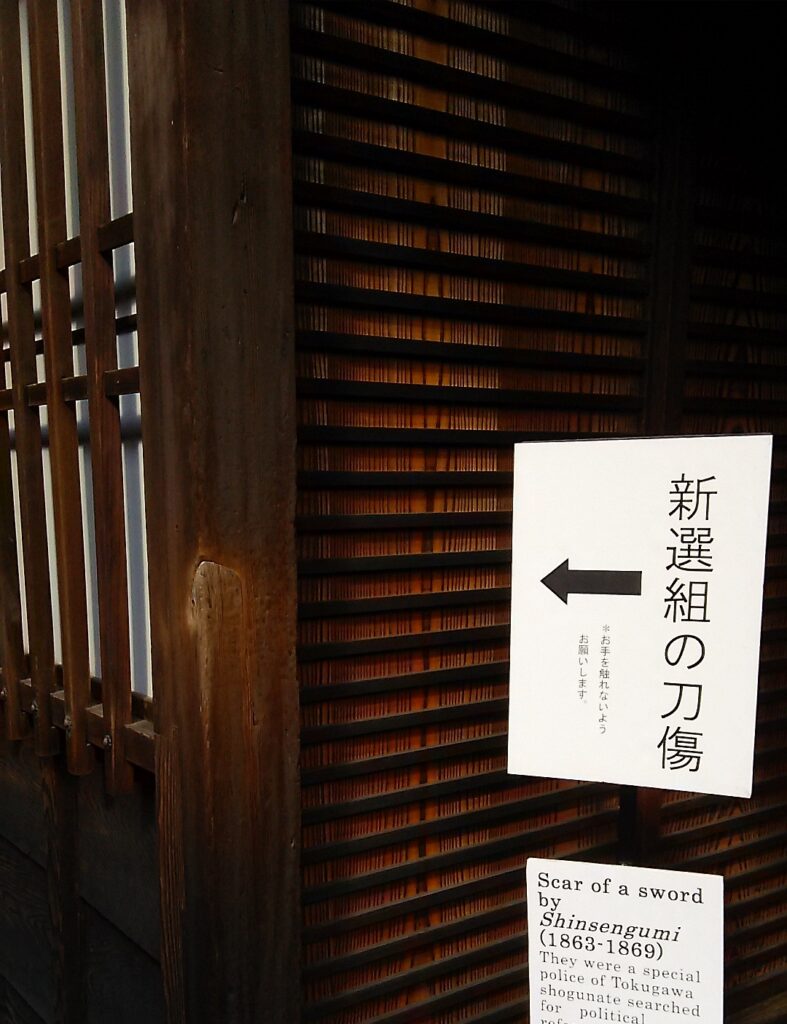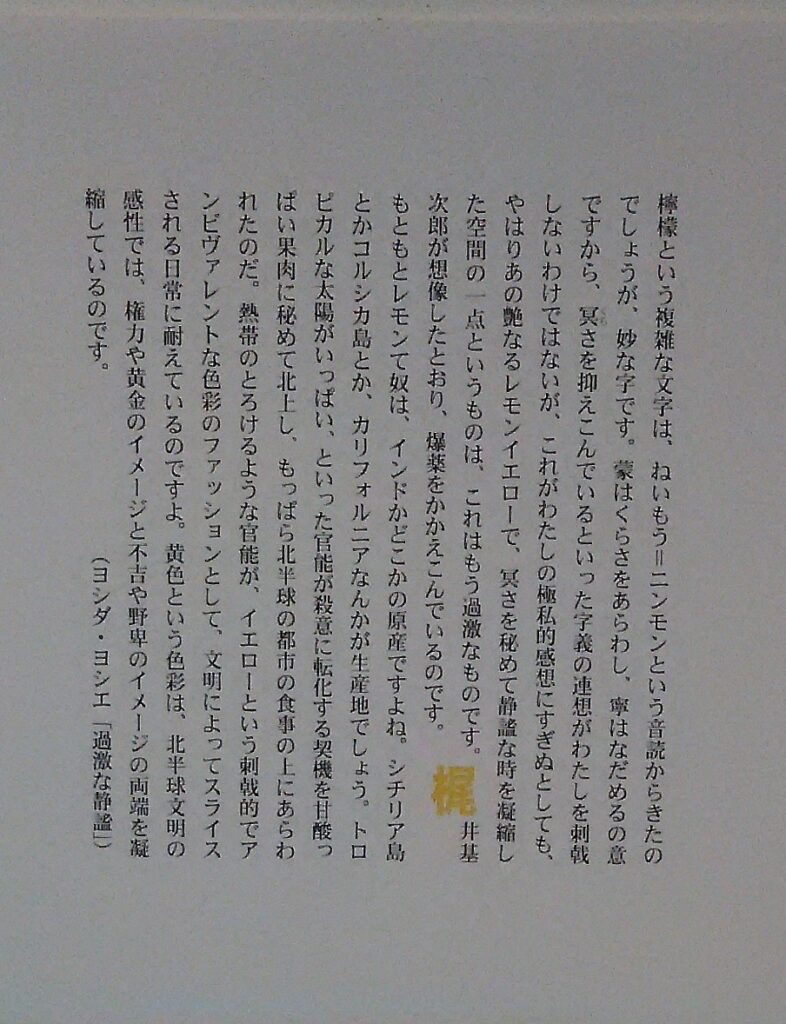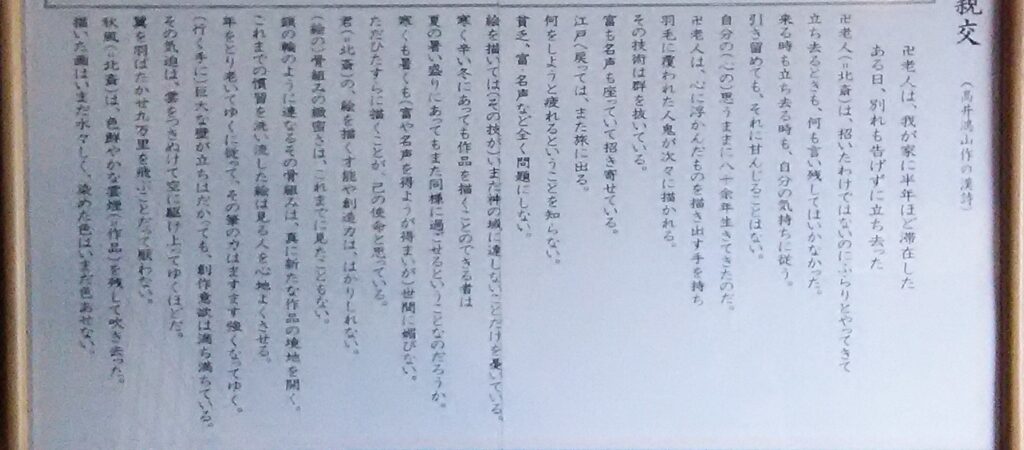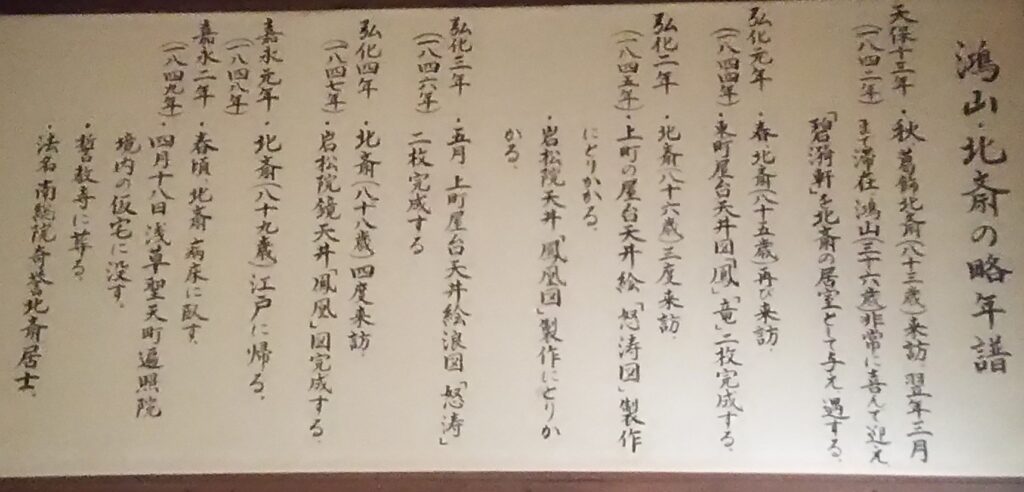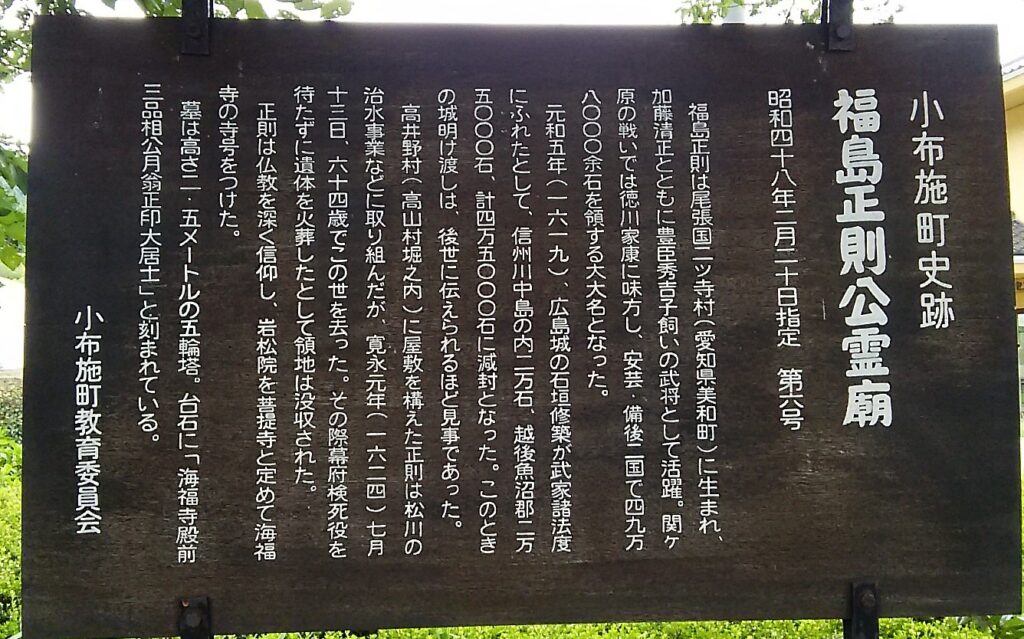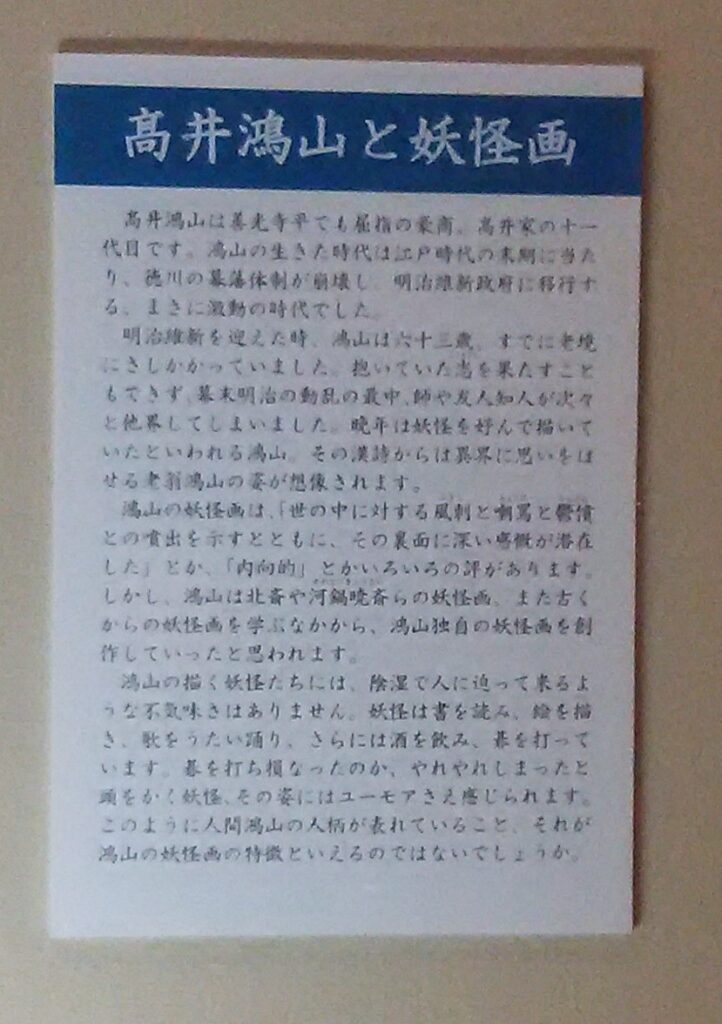一日二つは無理でしょと思いましたが新たな視点を分断させるのは嫌だなとの想いで『ゴッホ展 巡りゆく日本の夢』(東京都美術館)『北斎とジャポニスム』(国立西洋美術館)と二箇所続けて鑑賞しました。混んでいましたが、浮世絵のほうは今まで少し観ていますから人の多い絵は人と人の間から覗き込み時間を多くとらず、観たい絵だけ集中し今回の展示の意図を頭の中で組み立てました。
楽しかったです。芸術品を鑑賞するというよりも、見たことも会ったこともない国の人々が絵を通して交信し合っているのです。これは、遅く生まれてきた人に与えられた特権でしょうか。そういう企画を実行してくれたことに感謝です。
ゴッホさんに関しては、弟・テオさんに多くの手紙を出していますので、そこからの研究も多く生前売れた絵は一枚だけだそうで、テオさんの経済的援助で成り立っている制作です。ゴッホさんの望みは、テオさんの生活を脅かすことなく絵についてテオさんと語り合えることだったと思います。残念ながらその現実に負けてしまいました。押し寄せる状況に疲れてしまったのでしょう。
『ゴッホ展 巡りゆく日本の夢』では、多くの日本人がオーヴェールを訪れていて、ゴッホさんと最後まで交友のあったガシェ医師のもとに訪れた人の名前が記載された「芳名録」も残されていて紹介されていました。画家たちも訪れていて、日本画家・橋本関雪さんが訪れときの映像もありました。
佐伯裕三さんはオーヴェールの教会を描き、前田寛治さんは、ゴッホのお墓を描き、横尾忠則さんも訪れています。
ゴッホさんに関する研究者であり精神科医・式場隆三郎さんの資料も多数ありました。斎藤茂吉さんにオーヴェールを訪ねるように薦めたのは式場さんです。 『炎の人 式場隆三郎 -医学と芸術のはざまで-』
ゴッホさんがパリに出て来た時、絵を描く人が多いのに刺激を受けたことでしょう。そんなとき浮世絵に会うわけです。独力のゴッホさんにとって、線、構図、描かれている庶民、風景、花々に大いなる違う世界をみられ、親戚に日本に来たかたもいて話しを聞かれたらしいのですがどんな話を聴かれたかは記録には残っていません。
広重の『亀戸梅屋敷』などは模写をし、そこから自分の絵に木を中心に大きく描いたり、英泉の花魁の絵を模写して、その周囲にも他の浮世絵をモチーフに描いたりしています。それがどの浮世絵からとったのかも解説してくれていまして、こういう浮世絵も観ていたのかと注目しました。ただ色はゴッホさんの色です。
ゴッホさんの色というのはゴッホさんのもので、『表現への情熱 カンディンスキー、ルオー と色の冒険者たち』(パナソニック汐留ミュージアム 2017年12月20日まで)でカンディンスキーがゴッホから原色を含む激しい色づかいを学んでいます。
ゴッホさんにも優しい色づかいはあり、ゴッホ=ひまわりから離れて、浮世絵との関係から、夢中になって模索するゴッホさんの絵があります。日本初公開の絵もあり、その後のゴッホさんの苦しみとは違うゴッホさんの絵に触れているんだという感覚が新鮮で、その風が日本からのものであり、巡り巡って、ゴッホさんが日本に向けて風を返してくれ、文化というものはいい風を吹かせるものだと明るい気持ちになりました。
もしこの風域に境界をもうけるようなことがあればそれは無粋というものです。浮世絵を江戸の庶民誰もが楽しんでいたことをゴッホさんは知っていたでしょうか。おそらく知っていたでしょう。
式場隆三郎さんに関しては、山梨県甲府の昇仙峡そばにある『影絵の森美術館』で山下清展も開催されていて、ペン画や美しい色に複製された張り絵などがあり、式場さんのことをふっと思い出して忘れられてしまうのかなと思ったりしましたので、今回その仕事ぶりがきちんと紹介されていて嬉しかったです。さて浮世絵は、まだ風を起こします。