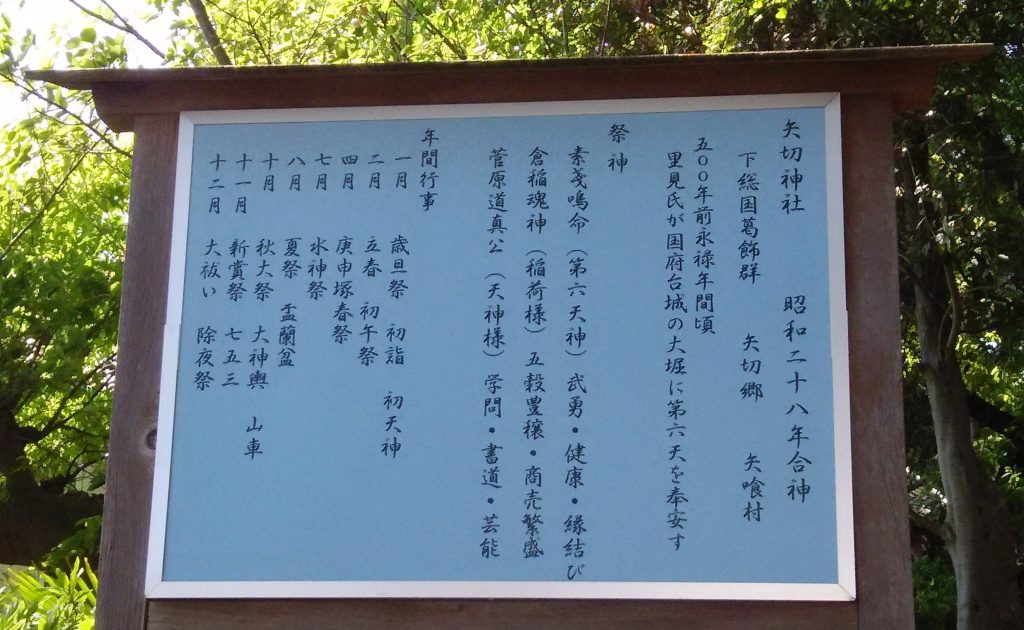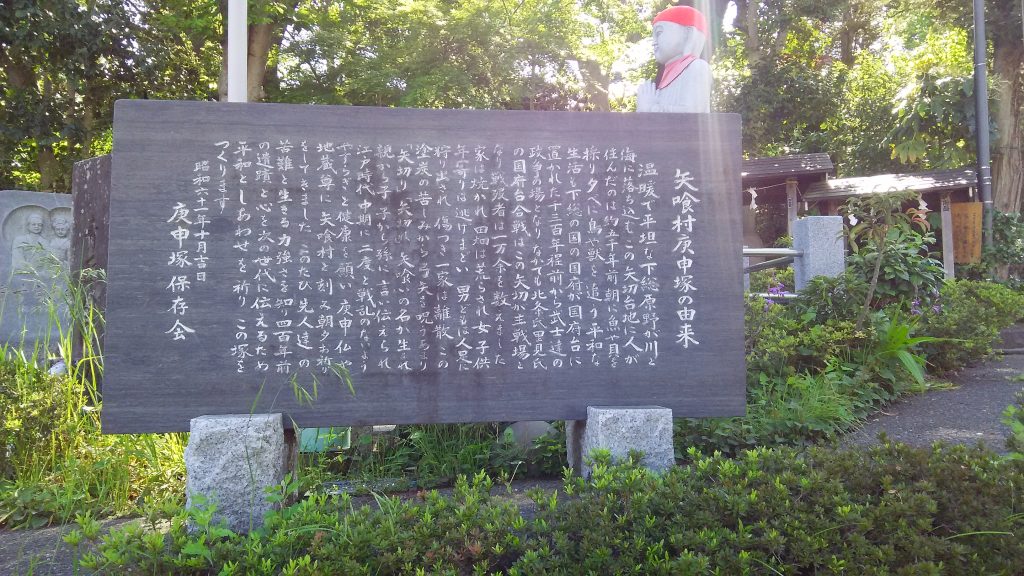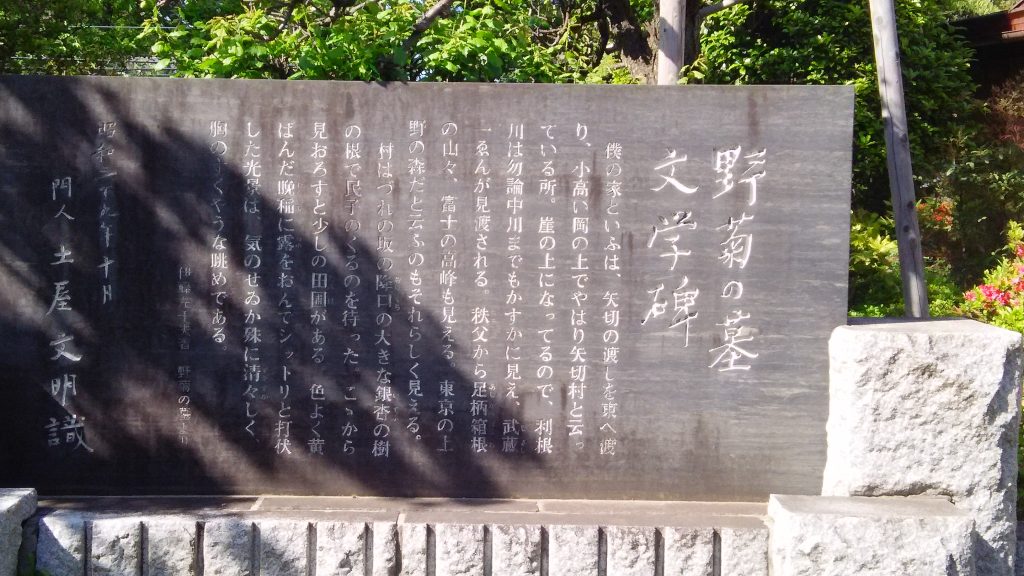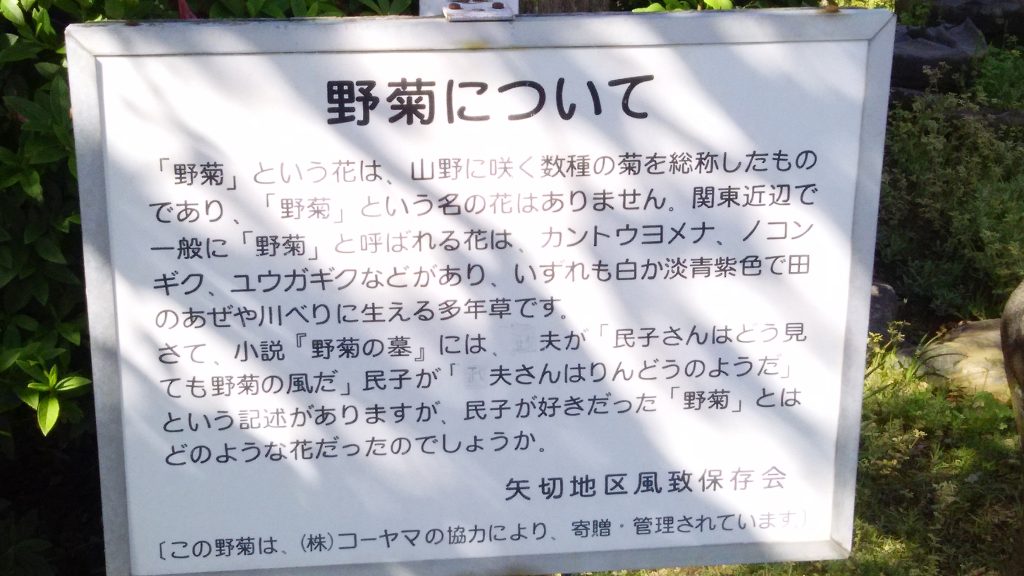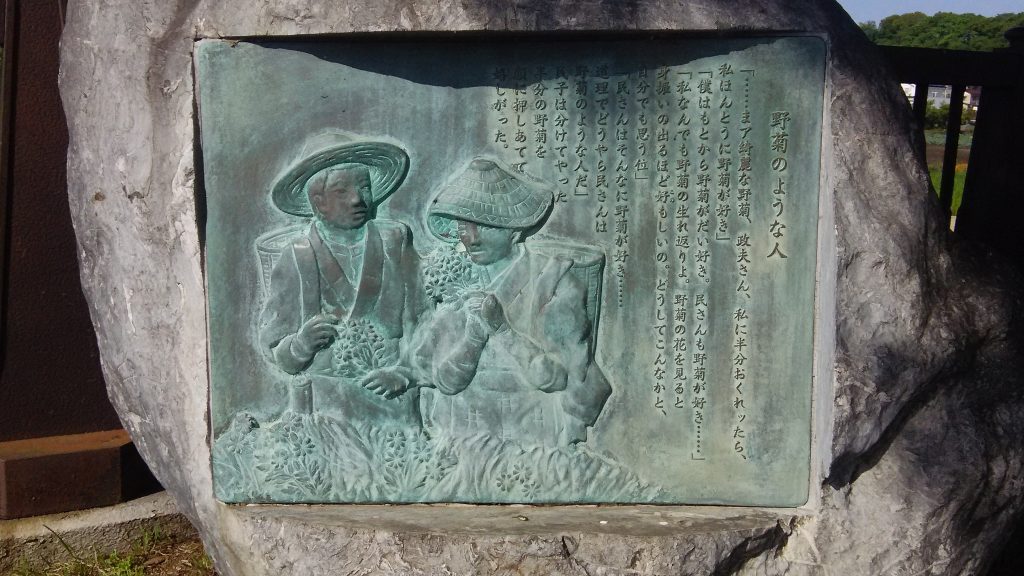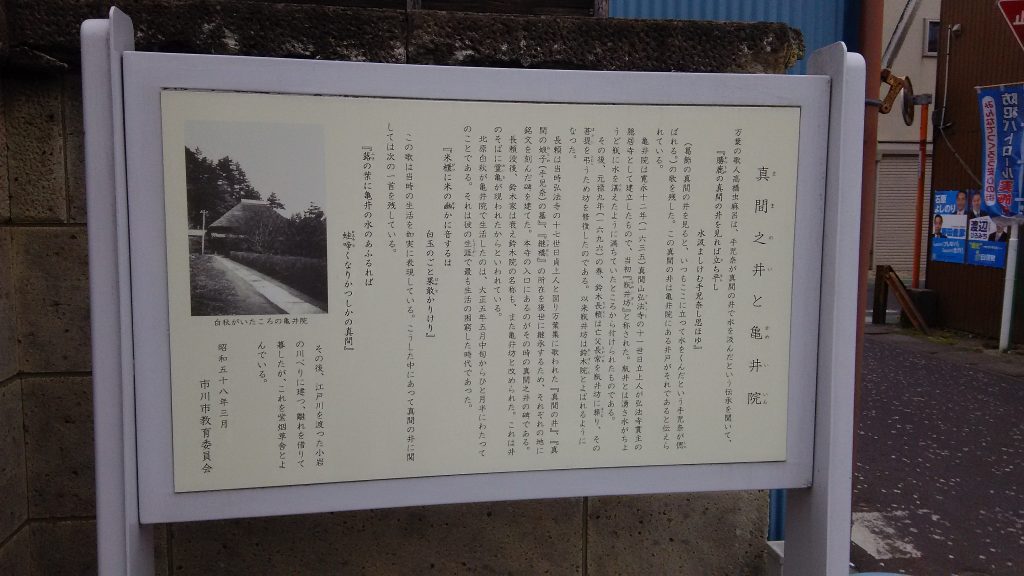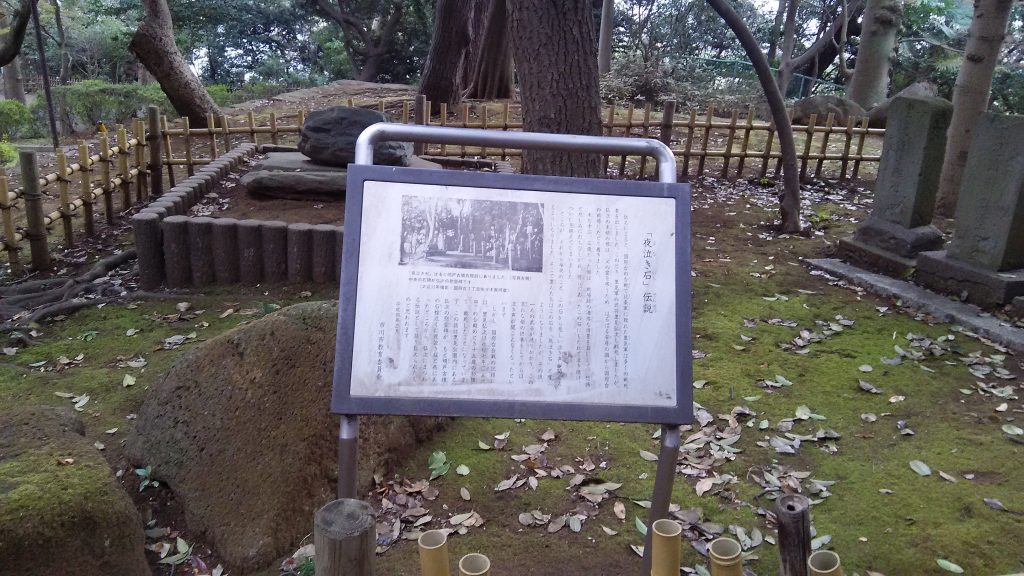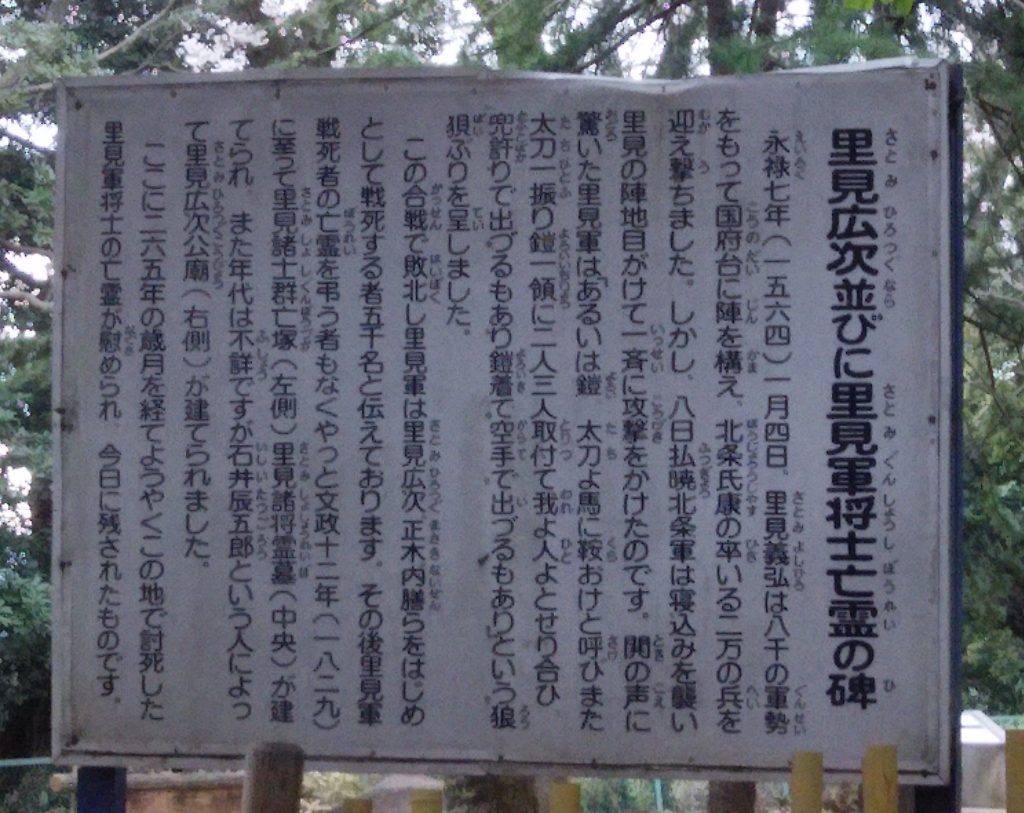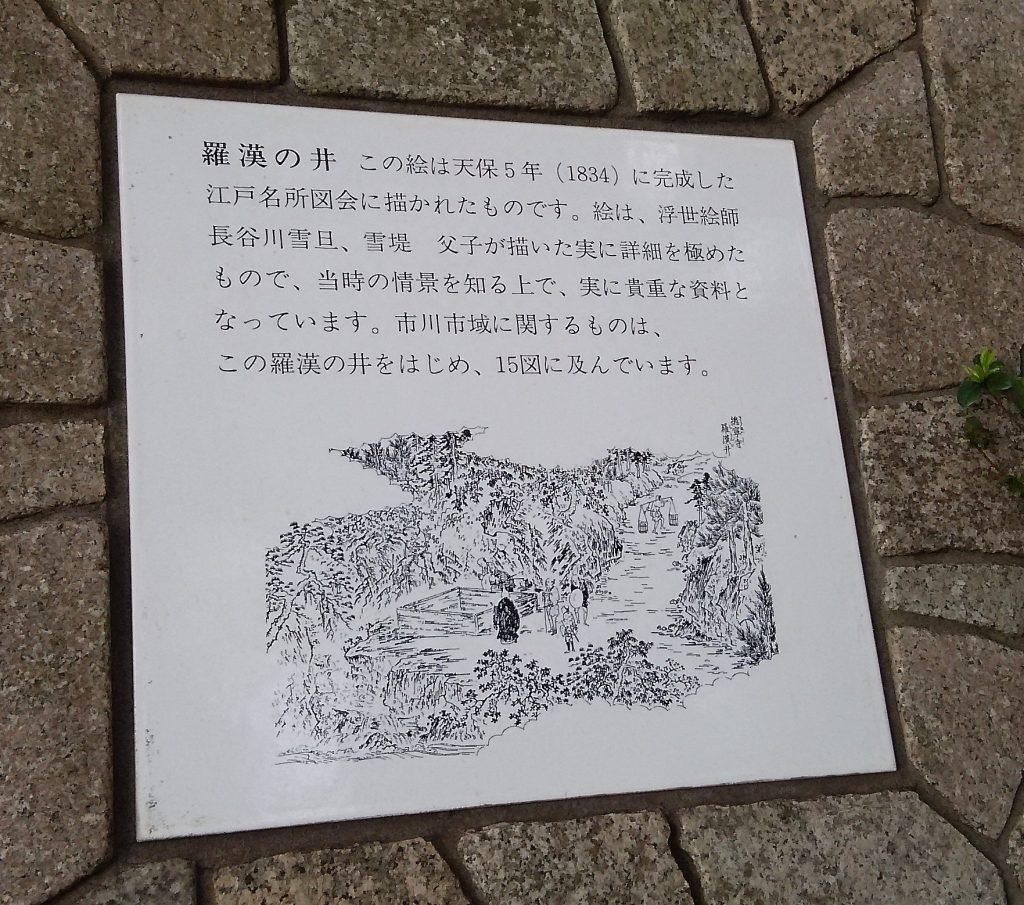森類さんの著書『森家の人びと 鷗外の末子の眼から』にて思いもかけない方向に導いてくれる。第一部・エッセイと第二部・小説となっている。森類さんの抑制のきいた文章がいい。朝井まかてさんの『類』から想像していたよりも冷静な視線で変に感傷的でないのが信用できる。
優しかった父・鷗外を思い出す場面も本屋の仕事の合間に煙草を一服吸うような感じである。鷗外を背負うわけでもなく、嘆くわけでもない。読者は父鷗外の愛をそっと抱えて鷗外の子の枠からいい意味で解放される類さんの文章の世界に添う。文章は淡々としている。
佐藤春夫さんとの気を使っているようないないような微妙な関係が『亜藤夫人』に書かれている。「来たいから来ただけで、用がないから黙っている。先生の方も来たから座らせてあるだけで黙って居られる。」佐藤春夫さんは、校正刷りにさらに手を加えらているがなかなか終わらない。そんな長い時間の中でふっと先生は安宅さんの奥さんの様子をたずねられる。
「安宅さんの奥さんと云うのは僕の妻の母で、先生が昭和25年の「群像」十月号に書かれた『観潮楼付近』の主人公亜藤夫人である。」安宅夫人はかつて佐藤春夫さんと恋人であった。そして、類さんが佐藤春夫さん宅を訪れるきっかけを作ってくれた人である。
類さんは、入ってきた奥さんと先生のやりとりに夫婦の愛情が籠っているのを感じる。この奥さんが谷崎潤一郎元夫人の千代さんである。
『観潮楼付近』を読んだ。わたくし(佐藤春夫)と観潮楼の関係、亜藤夫人との若かりしころの出会いと別れが書かれている。わたくしは郷里から出てきて生田長江の門下生となる。そして、観潮楼のすぐ前の下宿屋に住んだことがあったのである。わたくしは、森鷗外と観潮楼にあこがれをもって外からながめるだけであった。
その新しく出来た下宿に対して、鷗外が小説『二人の友』の中でこの家を描いている。「眺望の好かった私の家は、其二階家が出来たため陰気な住いになった。」
生田長江さんのところに出入りしていたO女(尾竹紅吉)が生田長江門下生の秀才を妹の結婚相手にしたいと提案した。その秀才がわたくしであった。一年半ほど妹と付き合うが、恋人は亜藤画伯と結婚することになってしまう。わたくしは落第生であり詩人ともいえない状態だったので彼女を祝福したのである。
O女は青鞜廃刊後、同人誌を発刊することになる。同人誌名『蕃紅花(サフラン)』は聖書から選んで命名したのがわたくしであった。「その創刊号には雑誌名と同題で鷗外の一文が寄せ与えられている。」鷗外さんも力添えしていたのである。
森鷗外記念館のため観潮楼址の地鎮祭と記念事業の奉告式があり、そこで、わたくしは若い夫人から一礼され「母から、よろしく申し上げよと申しつかってまいりました。」といわれる。その若い夫人が森類さんの妻であり、母が亜藤夫人であることを知るのである。わたくしはお共に頼んで来てもらった青年詩人Fに誰かと尋ねられ「夫人の方はむかし僕に『ためいき』という詩を書かせた原動力になった人の娘さん」とこたえるのである。
どんな詩なのであろうかと興味がわいた。『観潮楼周辺』には『ためいき』の詩も載っていた。恋に破れて故郷にもどって作られた詩であった。
その後、わたくしの家に亜藤夫人、森類夫婦、森茉莉の4人が訪れるのである。
小説『類』のラストは、類さんが茉莉さんの没後に書いた随筆『硝子の水槽の中の茉莉』がベスト・エッセイに選ばれたため家族がお祝いのため日在の家に集まってくれたところで終わっている。そのエッセイは類さんが茉莉さんのマンションを訪ねときの茉莉さんとのその独特の交流を描いたものである。茉莉さんの様子を「硝子の水槽の中の茉莉」と表現したのは茉莉さんとかつてのように交信できなくなった淋しさと茉莉さんの世界観をそっとしておく類さんの心である。
かつて茉莉さんのことをリアルに描いた類さんを通過しての表現者としての類さんである。
佐藤春夫さんの『観潮楼周辺』は観潮楼の建物を中心に、その中に住んだ者、その周辺をウロウロした者、そして周辺の風景が上手く交差しつつ描かれている。わたくしの「青春時代のわが聖地」であったと今回初めて知ったのである。
小説『類』で、斎藤茂吉さんは本屋の名前の候補を二つ出している。『鴎外書店』と『千朶(せんだ)書房』で、「千朶」はどこから考えられたのかと疑問におもっていた。それは、鴎外さんが前妻の登志子さんとうまく行かず離れて住んだのが千朶山房であったと『観潮楼周辺』に書かれている。この家はその10年後夏目漱石さんが住み、『吾輩は猫である』を書かれたので「猫の家」と言われている。住所の千駄木とも重ねて「千朶」が浮かんだのかもしれない。
前妻の登志子さんとの子が於菟(おと)さんで、類さんより21歳年上である。類さんと於菟さんの関係は、祖先から続く森家の構造、異母兄弟、年の差などが複雑にからんでいる。
『観潮楼周辺』のわたくしは、於菟さんはちょっと苦手のようである。亜藤夫人の娘婿でもあるゆえか類さんには好意的である。亜藤夫人たちが帰った後、わたくしの奥さんは詳しく客の説明を聴いて亜藤夫人はこんなところに嫁に来なくて良かったと思ったでしょうという。わたくしには複数の女性関係があり、今の夫人とは二回目の結婚である。奥さんの言葉に対してわたくしは「それとも自分が来ればこの人もそんなに度々結婚しないでも一度で納ったろうと思ったか、どちらかだね。」といって笑うのである。
お二人には揺るぎない関係が存在しているが、わたくしはハッピイエンド観の小詩をしたためて満足する辺りが作家のサガであろう。
類さんは、『亜藤夫人』の中で、義母が先生の家に何回行こうがどうでもいいことだが「一緒に並んで行くのが厭だった。岳父が心の底からこれを楽しめないとすれば、先生の奥様にとっても、心から楽しい筈がないのである。」と書いている。
類さんには彼特有の周囲に対する観察力がある。その観察力で自分が主導権を握るとか、強く自己主張するというのとは違う。自分の中で調節して決まれば自分の考えとして自分で納得するのである。そして世間の喧騒から身を引くのである。
佐藤春夫さんは喧騒に立ち向かう方である。
朝井まかてさんは、『類』のラストで、類さんが自分なりの父と母のつながりを完成させ納得する類さんを描かれている。それは朝井まかてさんの類さんに対する上等のプレゼントのように思えた。